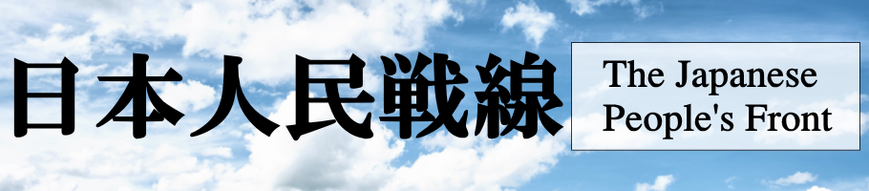〈学習のすすめ〉
マルクス主義の原点は哲学にある。哲学を基礎に正統マルクス主義を掌握せよ!
―唯物論・弁証法・史的唯物論を思想体系としてつかみ、マルクス主義を深く認識しよう―
日本共産党(行動派)議長
大武礼一郎
発行 日本共産党(行動派)中央委員会
著者前書
現代世界はすべての面で新しい転換期の時代である。この歴史時代がもう一度正統的マルクス主義の復興を求めて動きはじめている。最近内外でマルクス主義・共産主義に関する出版物が増えているのはその現象である。しかしその多くは国際共産主義運動を変質させたフルシチョフによる「スターリン批判」という名のブルジョア的修正主義思想に影響されており、その結果マルクス主義がわい曲され、修正され、自由主義的に解釈されている。これは歴史科学の法則として必然であり、弁証法的運動法則にもとづいて必ずそれは正しい方向に収れんされていく。そのためにもここでマルクス主義の絶対的真理を、その原点たる哲学(唯物論・弁証法・史的唯物論)にもとづいて全面的に論ずる。その核心は以下のとおりである。
第一節では、マルクス、エンゲルスとは何者か。その生涯は何であったのか。このことを有名なエピソードをふくめて正確に、はっきりと明らかにした。
第二節では、マルクス主義的世界観、歴史観、運動法則とは、すべてを発展と前進と止揚であるという、弁証法的哲学であることを論じた。
第三節では、マルクス主義の原点たるその哲学を、唯物論・弁証法・史的唯物論について全面的に論じた。
第四節では、経済学の諸問題を全面的に論じた。
第五節では、社会主義経済学、社会主義について、そしてレーニンとスターリンのソビエト社会主義の本質とその巨大な勝利を史実にもとづいて明確にした。あわせて、ソビエト社会主義がなぜ途中で、一時的に、未来のために崩壊したのかを論じ、同時にスターリンや毛沢東の時代が、その歴史的制約のもとで解決できなかった課題をいかに「止揚」すべきかという、われわれの任務について論じた。
以上である。もう一度強調しておきたいのは、すべては哲学であり、哲学原理から理論と実践、闘いと運動を支配せよ、ということである。そういう正統マルクス主義の原理・理念・原則によってこの文献は貫かれていることに留意していただきたい。
(以上)
《目次》
著者序文
序論
第1章
マルクスとエンゲルスとは何者か?彼らの人生はどのようなものだったのか?有名なエピソードを交えながら、正確かつ明快に解き明かす!
1 カール・マルクス、その生涯
2 1879年の出来事--そのエピソードの中にマルクスの生きた姿がある。歴史的事実を通してマルクスの人間性、人格、人間像をしっかりと認識し、私たちの中にも定着させましょう!
3 フリードリヒ・エンゲルスとその生涯 エンゲルスは、マルクスにすべてを捧げ、思想、政治、理論、実践において、つねにマルクスと一体であった。エンゲルスのそのような人生そのものに、二人が一体であったこと、二人を切り離すことができないことの証明がある。
第2章
マルクス主義の世界観、歴史観、運動法則観は、すべてが発展、進歩、昇華であるという弁証法的哲学観であることを確認しよう!
1 歴史的出来事をどう見るかの教科書は、『ルイ・ボナパルトの18ブルメイエ』(マルクス、1851-52)である。つまり、哲学的原理(歴史科学)と『共産党宣言』から演繹的に歴史的事件を見るとき、ソ連・東欧崩壊の根本原因・犯人は、党と権力の変質と、"スターリン批判 "の名の下にフルシチョフの修正主義がマルクス主義を完全に放棄した結果である。すべては権力の問題であり、すべては哲学理論に内包されている!
2 マルクス主義とは何か?どのように生まれ、育まれ、完成されたのか?その原理からすれば、ソ連、東欧、中国における社会主義の崩壊は、社会主義と共産主義の最終的な勝利に向けた必要な一歩である。歴史はこのように必然性と偶然性の統一的な発展と進歩であり、この社会主義の崩壊は弁証法的な歴史発展の素晴らしい証明である。弁証法的歴史科学からすべてを見よ!
第3章
マルクス主義の出発点、その原点は哲学である。唯物論、弁証法、史的唯物論を正確に認識せよ
1 マルクスのフォイエルバッハ論について!このテーゼについて、エンゲルスがその歴史的意義、綱領的意義、マルクス主義哲学の核心としての意義を語ったエンゲルスの思想的認識を深く認識しなければならない。これがマルクス主義哲学を学ぶ出発点である!
2 「フォイエルバッハに関するテーゼ」の第一テーゼには、唯物論の原点がある。ここに万物を支配する哲学的原理がある。このテーゼを深く、しっかりと、明確に、正確に理解できるかどうかで、あなたが真のマルクス主義者かどうかが決まる。
3 「フォイエルバッハに関するテーゼ」の第11テーゼの深遠な思想的・政治的意味を把握せよ。"哲学者たちは世界をさまざまに解釈してきたにすぎない。そして、哲学者が保つべき人格、人間性、人間像を説くマルクスの心を理解する!
4 マルクス主義哲学が「弁証法的唯物論」と「史的唯物論」から構成されていることは、エンゲルスやレーニンも明確に確認している。しかし、敗北主義的修正主義者には、このことが理解できない。ここにも、彼らの浅薄さ、薄っぺらさの原型がある。これもまた、われわれが否定的な例として学ばなければならない教訓である。
5 歴史的唯物論について!
第4章
経済学とは何か?経済学の基本原理を学ぼう。
1 アダム・スミスと古典派経済学の歴史における位置づけ、その形而上学的・観念論的性格について!
2 歴史社会科学としてのマルクス主義経済学について!
第5章
社会主義経済学、すなわち社会主義とは何か?レーニンとスターリンの偉大なソビエト社会主義建設の勝利を確認せよ。そして、これを正しく昇華させなければならない!
1 マルクス主義経済学とは、目的を持った、科学的な、計画された、社会(社会主義)計画経済である。レーニン・スターリンの40年にわたるソビエト社会主義の建設は、偉大な勝利として、その正しさをはっきりと証明している。その歴史的、客観的事実を確認せよ。
2 ソビエト社会主義の偉大な勝利とその成果が崩壊したのは、フルシチョフの「スターリン批判」という反マルクス主義のブルジョア思想によるソビエト党と国家のブルジョア化の結果であった。そして、これこそが、マルクスが予言し、レーニンが予言し、警告したことであった。社会主義の最終的な勝利に必要な歴史的過程全体の必然性の中の偶発性であった!
3 レーニンとスターリンの偉大なソビエト社会主義は、内部からの変革によって崩壊した。それは、フルシチョフと中国の鄧小平という裏切り者が出現したためであった。したがって、社会主義はもう一度最初からやり直さなければならなかった。これらはすべて、マルクスとレーニンが早くから予測し、予言し、警告してきたことであり、その歴史的意味をよく理解しなければならない!
4 マルクスが提案し、レーニンが実現したプロレタリア独裁(労働者階級と人民の支配とその権力)の物質的表現であり、社会主義建設の勝利の鍵である「評議会」(ソビエト)の思想的(理論的)意義をしっかりと把握せよ。それを堅持し、それに依拠して権力を実行しよう!
5 われわれは、レーニンとスターリンによる偉大なソビエト社会主義建設の勝利と成果を「昇華」しなければならない。言い換えれば、われわれは、レーニンとスターリンによる原則に基づく根本的勝利の部分を断固として継承する。同時に、後継者であるわれわれは、その時代に解決できなかった部分、達成できなかった部分を必ず解決し、新しいものを加えて完成させなければならない。これが "昇華 "の哲学的原理であり、科学的法則である。
6 レーニンとスターリンの偉大な社会主義が "昇華 "されなければならないもう一つの側面とは何か。すなわち、レーニン以後の社会主義運動が歴史的制約のために未解決のままにしてきた未完の仕事とは何か、歴史がわれわれに解決を求め、マルクス主義運動のさらなる発展と前進を託し、昇華することを求めてきた問題とは何か。
結論
われわれの将来展望とスローガン
あとがき
著者プロフィール
序論
最近、マルクス主義に関する出版が相次いでいる。マルクスに関する本もたくさん出ている。なぜだろうか。それは近代史の時代の産物である。
すなわち、2001年9月、3000人の死者を出したアメリカ中枢機関への同時多発テロに代表される、多民族国家と大衆による反米・反帝国主義の嵐である。イラクとアフガニスタンにおける泥沼の戦争。 2008年9月15日の米大手証券会社リーマン・ブラザーズの破綻に続く、世界的な金融・経済危機と米国経済の衰退。2010年末にチュニジアで始まった北アフリカと中東の民衆蜂起と反乱に対処できなかった米国。これらの出来事や事実は、アメリカとその帝国主義がもはや経済的、軍事的、政治的に世界を支配する力を持っていないことを証明している。現代の独占資本主義とアメリカ帝国主義に未来はない。世界はどこへ行くのか?資本主義陣営と対立していたソ連や中国の社会主義は、その質を変えた。そして、アメリカも失敗したとなれば、世界はナショナリズムの道を歩むのだろうか。
しかし、そのナショナリズムや我が道を行くという道は、すでに通ってしまった悲劇の歴史の道である。歴史が教えてきたように、ナショナリズムは対立、紛争、戦争を伴うものだった。つまり、ナショナリズムが戦争の原因だったのだ。そして、歴史はもはや過去に戻ることはできない。歴史は前進するのであって、後退することはない。時代は、私たちに何をすべきかを問い続けている。こうして、先進的で前衛的な分子、知識人たちは、「歴史には社会主義以外の道はない。しかし、なぜソ連や中国では変わったのだろう?"と。そして、もう一度マルクスを読み直そうと考える。ここに歴史の流れがある。歴史科学の法則は必然である。人類最初の社会は原始共同体であり、それが奴隷制、封建制、資本主義へと発展したが、資本主義の頂点である独占資本主義と帝国主義は、今や完全に行き詰まり、崩壊し始めている。一方、歴史は歴史科学の法則に従って、無階級社会、社会主義、人民の世界を求めて激動している。だから、マルクスを読み直す動きは、歴史科学の法則から見た進歩、前進、発展なのである。したがって、これらの書物を執筆・出版した学者、文化人、出版社に敬意を表したい。
しかし、ここで問題提起をしたい。どんな運動にも、最初は必ずある種の誤り、認識不足、不正確さ、不十分さがあることは避けられない。この種の本も同様である。結論から言えば、これらの学者や知識人の多くは、マルクス主義の原点が哲学であること、その哲学の本質が科学と哲学の統一であること、歴史が科学であることを認識しておらず、したがって、彼らが活動的でなく軽薄であることを露呈している。ここで、否定的な例としてこの問題を取り上げる。
最初の典型例として、マルクス主義全般を論じ、『マルクスの実像~マルクス再読の意味』(新泉社、2006年10月初版)を著した上村邦彦氏(一橋大学大学院博士課程、社会学博士、関西大学経済学部教授-社会哲学)を紹介する。
次に、マルクス主義哲学を論じ、『マルクスと哲学~方法としてのマルクス再読』(新泉社、2004年6月初版)を著した田端実氏(大阪大学大学院文学研究科哲学・哲学史専攻、大阪経済大学人間科学部教授)を紹介する。
最後に、マルクス経済学を論じた伊藤真氏(東京大学経済学部卒、東京大学名誉教授、國學院大學教授、日本学士院会員、理論経済学専攻)の『資本論を読む』(講談社、2006年12月刊)を紹介する。
これらを代表的な出版物として紹介したが、その他も含めて、よくある誤り、不正確さ、不十分さ、不完全さなども明らかにしておきたい。
第1章
マルクスとエンゲルスとは何者か?彼らの人生はどのようなものだったのか?有名なエピソードを紹介しながら、これらを正確に、はっきりと明らかにする。
第1節
カール・マルクス、その生涯
1818年5月5日、マルクスはドイツ第一の商工業地区であるライン州のトリーアの町で、自由主義的な弁護士を父に、9人兄弟の3番目の次男として生まれた。父はこの子に弁護士になることを勧め、1835年にボン大学、1836年にベルリン大学に進学させた。しかし、マルクスは哲学と歴史に興味を持ち、それらにエネルギーを注いだ。ドイツは哲学の国で、全国どこの大学でもヘーゲルの弁証法やフォイエルバッハの唯物論が流行のように論じられていた。ベルリン大学の学生運動は必然的に左派と右派に分裂した。左派は青年ヘーゲル派を形成し、マルクスは左派の中心に座った。
1841年に同大学を卒業するまでに、マルクスはヘーゲルとフォイエルバッハを完全に昇華させていた。ヘーゲルは、すべてのものは進化し、前進し、爆発し、収斂し、転換しており、その原動力は対立物の闘争であると主張した。この弁証法的方法論は正しかった。しかし、ヘーゲルがこれを観念の世界に限定したのに対し、マルクスは弁証法哲学を次のように完成させた: 「弁証法哲学によれば、宇宙と人間世界は物質の運動であり、物質の運動そのものが対立物の存在と闘争であり、それが人間の頭脳に反映されている。そして、ここから現れる真理によって、物質の運動は発展、進歩、爆発、転換(革命)を経て収束する。" フォイエルバッハの「神とは人間が作った人間世界である」という唯物論的な考えは正しかったが、フォイエルバッハは人間を社会的な人間とは見ていなかった。マルクスは次のように哲学的唯物論に到達した:人間は生産力と生産関係における社会的人間である。人間の意志や認識は、社会的存在を人間の脳に反映させることによって生み出される。その人間の意志や認識は、物質的存在を支配する。このようにして、マルクスはヘーゲルとフォイエルバッハを昇華させた(正しい核心を引き継ぎ、未解決、不十分、不完全な部分を解決した)。こうしてマルクスは、哲学的弁証法的唯物論を完成させたのである。マルクスは哲学から出発した。だから、エンゲルスは後に「ドイツ哲学がなければ、マルクス主義は生まれなかった」(『ドイツ農民戦争』1875年)と述べている。
ベルリン大学を卒業したマルクスは、その哲学的原理を実践し、行動し始めた。1842年1月、彼は『ライン新聞』の編集長となり、革命運動に身を投じた。当時のラインラントでは、農民の反乱、農民の暴動、農民の武装戦争が勃発していた。各地の重税、弾圧、土地没収に対する農民の怒りが爆発し、ラインラントは自由民権運動の旗印として戦っていた。マルクスは戦闘的な論説で農民運動を支持し、プロレタリアートとの同盟を訴えた。エンゲルスも当時ラインシュ・ツァイトゥングに寄稿しており、そこでマルクスの名前を知った。政府はこの新聞とマルクスを危険分子とみなし、1843年5月に新聞の発行を禁止し、マルクスを国外追放にした。
1843年6月、国を追放されたマルクスはパリに向かった。この時、マルクスの姉ソフィーの友人で、トリーアの町に住む貴族の政府参事官の娘ジェニーがマルクスに同行した。マルクスとジェニーは、ベルリン大学の学生時代からの知り合いで、婚約もしていた。ここから二人の苦難の道が始まった。貴族階級、美貌、結婚の申し出の数々--ジェニーがそれらすべてを捨て、4歳年下のマルクスと恋に落ちたのは、彼の溢れんばかりの情熱と輝きのためだった。マルクスがフランス、ベルギー、そしてイギリスへの逃亡を余儀なくされる間、彼女はマルクスに同行した。晩年、彼女は貧困と病気のマルクスを助けるため、二人の子供を相次いで亡くし、弾圧と迫害のもとで真摯に努力した。悪筆で有名なマルクスの原稿はすべて、ジェニーによってきれいに書き直され、エンゲルスや出版社にもたらされた。1881年12月2日、肝臓病で67歳の生涯を閉じたジェニーは、以前エンゲルスに、マルクスに満足しており、人生に悔いはないと語っていた。パリに移ったマルクスは、1844年2月に『ドイツ・フランス年誌』という革命的な出版物を刊行し、エンゲルスもそれに原稿を寄せた。これに関連して、エンゲルスは8月にパリにマルクスを訪ねて初めて会い、二人は思想と政治で完全に一致した。この時の二人の交流は10日間だったが、エンゲルスは後に "私の人生でこの10日間ほど楽しいものはなかった "と語っている。その後、二人は40年にわたって生涯の同志的友情を交わした。マルクスは1845年2月、ドイツ政府の強い要請により、パリからベルギーのブリュッセルに追放された。さらにベルギーからも追放され、1849年8月にロンドンに移った。その後、ロンドンはマルクスとエンゲルスの終生の住まいとなった。
パリからブリュッセルへの亡命期間とロンドンでの40年間は、マルクスとエンゲルスにとって戦いの連続であった。ドイツでは農民戦争、イギリスでは労働運動とチャーティスト運動、フランスでは二月革命(1848年2月~3月)、ドイツでは三月革命が次々と勃発した。マルクスとエンゲルスは、ヨーロッパの社会主義者、民主主義者、自由主義的人権活動家たちの革命運動に参加し、組織と理論で指導し、多大な貢献をした。彼ら自身、休む暇はなかった。
1846年初頭、マルクスとエンゲルスはブリュッセルで共産主義者通信委員会を組織した。それは1847年6月に共産主義者同盟へと発展した。同盟の要請を受けたマルクスとエンゲルスは、翌年2月に同盟の綱領となる『共産党宣言』を書き上げた。1864年9月、マルクスとエンゲルスは労働運動の国際連合である第一インターナショナルを結成。1871年、パリ・コミューンが勃発。マルクスはこの事件の研究に全精力を注ぎ、プロレタリア独裁の理論を完成させ、『フランス内戦』(1871年6月~7月)に結実させた。そしてマルクスは、この事件の実践的教訓として書いた『ゴータ綱領批判』(1875年)を通じて、ドイツの労働運動を指導した。
マルクスは1850年頃から喘息と肝臓病を患っており、長年の貧困と過酷な労働のために体調を崩していた。当時、エンゲルスから経済的援助を受けることを申し訳なく思っていたマルクスは、感謝の気持ちを込めて手紙を書き、その中で自らの人生観を「この世に生を受けた以上、価値ある仕事をしたい。それは、プロレタリアの歴史的使命とプロレタリアの解放、そして人類の未来を明らかにすることである。私はこの仕事に身を捧げたい。" エンゲルスはマルクスとの深い同志関係の中で献身した。
そして、マルクスが完成させなければならなかったのが経済学批判であり、その集大成が『資本論』であった。その頃、エンゲルスは長男として父から受け継いだ紡績工場と商社を処分し、マルクスの『資本論』の完成に注ぎ込んだ。第1巻は1867年9月に出版された。以来、マルクスは闘病しながら第2巻、第3巻の完成準備を続けていた。1883年3月14日、エンゲルスはいつものようにマルクスの家を訪れた。二年前にジェニーが亡くなってから年をとったマルクスを心配したエンゲルスは、近くに引っ越していつもマルクスを訪ねていた。その日の14時45分、マルクスは机の上の原稿に頭を乗せて眠っていた。エンゲルスは手を伸ばしたが、マルクスは起きなかった。65歳のマルクスは永遠に眠りについた。6人の子供のうち3人は生まれてすぐに亡くなり、長女はその2ヶ月前に亡くなり、生き残った子供は次女のラウラと四女のエリナだけだった。エンゲルスは、少女時代からジェニーと同居していたヘレナ・デムートと、マルクスの2人の娘を預かり、最後まで面倒を見た。そして、彼の机の上に残っていた『資本論』の原稿はすべてエンゲルスによって整理され、第2巻、第3巻として出版された。二人の娘も社会主義運動に生涯を捧げた。
三月十七日、エンゲルスはロンドン郊外のハイゲート墓地にマルクスを葬ったが、その告別の日には十四人が参加。エンゲルスはマルクスにつぎのような告別の辞を送っている。
「多くの未完成の仕事に当面し、それを完成することの不可能なことを思いつつ、タンタロスの苦しみ(註・ギリシャ神話の物語で、国王・タンタロスは神の怒りにふれて奈落の底に突き落とされ、永遠の飢えと渇きと恐怖のなかで死んだという苦しみ)に悩まされながらも生きることは、マルクスにとっては、いま彼の運命のうえに落ちてきたこの平和な死にくらべると、千倍も恐ろしいことであったろう」
「それはともあれ、人類は頭一つだけ低くなった。人類がもたされていた、もっとも天才的な頭一つだけ」
「それにもかかわらず労働者階級の最後の勝利はうたがうべくもない。しかし回り道が、ただでさえさけられないこの回り道が、いまや大変多くなるだろう。しかしわれわれはわれわれの力でやっていこう。他にどんな方法があるというのか。勇気を失うまい」と。
そしてエンゲルスは一八八八年一月三十日に書いた『共語版序文の中で次のように書いている。「この二十五年間に事情がどんなに大きく変化したにしても、この宣言の中に述べられている一般的な諸原則は今日にお いても依然として正しい。あちこちで、細部の点では改善 の余地があるであろう。これらの諸原則を実際にどう適用 するかということは、宣言そのものが述べているように、 いつどこでも、当面する歴史的条件によって決まるであろ う」と。
つまりエンゲルスはこのように、マルクス主義者はつね に理論上の原則は堅持しつつ、実践的には歴史的情勢と条 件によってその方法上においては“止揚"せよと言ってい るのである。
第2節
一八七九年の出来事、そのエピソードの中にマルクスの生きた姿がある。歴史上の事実を通じてマルクスの人間性、人格、人間像をしっかり認識し、われわれの中にもそれを確立しよう!
マルクスについてのエピソード、出来事を書いたのは、イギリスのジャーナリストで、伝記作家で、ラジオ・キャスターで、コラムニストとして名高い、フランシス・ウィーン氏であった。氏はドイツを追われてロンドンで生涯を終わった赤い革命家マルクスのことを知り、大いに興味をもち、時間をかけてあらゆる資料をかき集め、マルクスの生涯をくわしくまとめて出版した。これが『カール・マルクスの生涯』(一九九九年刊行)であり、日本語版は二〇〇二年に朝日新聞社から出版された。著者は一人のジャーナリストとして、思想性、政治性を離れて、客観的事実だけを、きわめて実務的に、たんたんと記録していった。したがってこういう作品は読む人によってそのとらえ方が違ってくる。この種類の本、特にマルクスに関するものは、本当のマルクス主義者、マルクス主義の思想と理論の全著作を読み、身につけていないと、客観的事実の中にふくまれているその本質、背景を正確に理解することは難しい。マルクス主義を身につけていないと、この本は単なる平凡な読み物に終わる。われわれ真のマルクス主義者は、客観的事実の背後にある本質的なもの、その真実を知るために眼を皿のようにして読む。そのとき深い感動が全身にみなぎる。著者が書いた事実の中のマルクスを語るその典型的一例をここに紹介する。
それは一八七九年のことであった。この時代のマルクスは晩年であり、病気がちであった。ジェニーも病床にあり、二人枕を並べることは常であった。一八八一年にジェニーは死んだし、一八八三年一月には長女も死んだ。ヨーロッパ労働運動は退潮期に入り、一八七一年のパリ・コミューンの敗北、一八七五年にはドイツ労働運動も右派が支配し(『ゴータ綱領批判』)、一八七六年には第一インターはついに解散してしまった。マルクスにとって、この時期はまさに内外共に苦難のどん底にあった。こんなときにこの出来事がおこった。このエピソードと物語について、フランシス・ウィーン氏はつぎのように記録している。
イギリスの王室に連なるある一族の要望に従って、イギリス政界の大物が呼びかけ、政界、財界、官界、言論界の有志が集まり、豪華な宴会場にマルクスを招待して昼食会を開いた。その意図は、過激な思想とスローガンでヨーロッパの各国政府を恐れさせている赤いテロリストの頭目たるマルクスなる人物がロンドンに住みつき、いまや老いている。一度招いて話を聞いてみてはどうかという、興味本位と好奇心が背景にあった。マルクスはこの招待を受けて出席をした。
<マルクスが自ら起草した『共産党宣言』の最後には、共産主義者の心構えとしてつぎの一文がある。「共産主義者は自分の姿を隠すことを恥とする。……支配階級をしてプロレタリア革命を前に恐怖させよ。……プロレタリアはこの革命によって失うものは何もない。得るものは全世界である」と宣言している。つまり、ブルジョアとその権力はプロレタリア革命によって自己の名誉と地位と財産を失うことに対する恐怖におののいている。その自分の恐怖を共産主義への恐怖にすりかえているのだ。だからわれわれは何も恐れることはない。いつでも、どこでも毅然たれ、ということである。マルクスは共産党宣言で示されている共産主義的心構えのとおりに行動した>
さて、参加者一同が待っているシャンデリアの間にマルクスが姿を見せたときみな「おや!」と思った。それは予想していた「恐しい怪物」ではなかった。意外に小柄で、色浅黒く、白髪、白いあごひげ、絹のような黒い口ひげ、静かな風情の普通の人間であった。
〈『共産党宣言』の書き出しはあの有名な言葉「一つの妖怪がヨーロッパ中を動きまわっている……共産主義という妖怪が。古いヨーロッパのすべての強国が、この妖怪を退治しようとして神聖同盟を結んでいる」というものである。この一文を参会者はみな知っているので、どういう「妖怪」かといろいろ想像していた。ところが姿を見せたその人物をみて「おや!」と思った、というわけである〉
〈ブルジョア観念論者たちはみな「外因論」者である。つまり、外見でものごとを判断する。反対に弁証法哲学は「内因論」であり、内因、つまり、すべては内部の力であり、人間においてはその人物の思想・政治意識であり、人間の心、精神、エネルギーであり、この内因が決定権をもっている。これが弁証法哲学の内因論である。一国の外交、対外政策もすべてはその内政の延長であり、反映であり、クラウゼヴィッッの戦争論で言う、戦争は政治の延長であるというのはこのことである。そしてこの日の宴会場は、内因論によって小柄なマルクスが巨大なマルクスに変わる場となった〉
宴会がはじまり、雑談がつづき、やがて出席者からマルクスへの質問や、政治的意見が出始めたころから、会場の空気は変わってきた。マルクスはどんな質問に対しても、まじめに、真剣に、そして明快に、理路整然と答えた。それはどんな質問に対してでもそうであった。各方面のあらゆる問題に対するその豊富な博学、知識、知的水準の高さに一同は驚いた。
〈マルクスがエンゲルスと共同して執筆したフォイエルバッハを批判した文書『ドイツ・イデオロギー』(一八四五年)の中で言っているとおり、観念論者は問題の枝葉末節と表面的現象だけを論ずるが、われわれ唯物論者はそうではなく、哲学思想にもとづく根本原理、根本原則と核心をつかみ、そこから一切を解明する。だからマルクスにとってはあらゆる問題が明快だったのである。哲学こそが万物の知的根源であった〉
そこで出席者のなかからきびしい質問が出されてきた。マルクスが主張するプロレタリア革命なるものはみな失敗しているではないか。労働運動も退潮してもう終わりではないか、という。そのときマルクスの眼は鋭く光り、態度は毅然として、きっぱりと答えた。歴史というものはけっして一直線に進むものではない。ヨーロッパの歴史、イギリスの王室の歴史をみても、すべては曲がりくねって進んできた。しかし歴史は科学である限り、必ず到達すべきところに到達するのだ、と確信的に、厳として答えた。
〈マルクスのおかれていた当時の情勢は最大の苦境であったが、明確な思想意識と科学的歴史観によってびくともしなかった。そしてマルクスが確信したとおり、その後歴史は第二インターの結成、ロシア革命の勝利、帝国主義崩壊という歴史時代が到来したのであり、思想が物質的な力となって歴史は動いていくのである〉
そうすると、出席者の一人が、生産性が高まり、国が豊かになり、貧しい人びとへの福祉政策が整備されれば社会は安定するのではないか、と言ったとき、マルクスは、それは不可能だと言い切った。なぜなら、資本主義の経済法則として、その国家維持と権力機構の拡大、そして戦争による軍事費の増大で福祉への余裕はなくなるからである、と。
〈現代世界の時代がマルクスの証言どおりである。格差社会は一国から世界的にますます拡大していく。戦争は終わることなく、軍事費は拡大しつづける。人民大衆は発展し、変化していく文化水準に追いつくために、ますます強く、多く、激しく働かねばならなくなっており、「ワーキング・プア」(働けど働けど楽にならない)問題が大きな課題になっているという現実がマルクスの予言の正しさを証明している〉
昼食会が終わったあと、出席者一同が誠に感心したのは、マルクスの発言は誠に、すべてにわたって、厳然としており、確信に満ちており、いささかも自説を曲げることはなかった。しかしその言葉使いは誠にていねいで、出席者の誰に対しても粗野でなく、辛辣(らつ)な表現はなかった。そして一貫して礼儀正しく、イギリス王室にかかわる話題においても常に敬語を使った。
〈マルクスの態度の中にマルクス主義がある。その名著『経済学批判・序言』(一八五九年)、『資本論・第一巻・序文』(一八六七年)のなかで明確に述べているとおり、対立と抗争、怒りと憎しみは階級的なものであって、個人的なものではないのである。とくに『経済学批判・序言』の中の「人間は自分の意志とは無関係に目の前にある生産関係に遭遇する」というこの一文の意味をよく認識しなければならない。つまり、自分がどういう境遇に生を受けたかは、それは自分の意志ではなく運命であり、誰の責任でもない。故に個人的敵対は人間道徳に反する。すべては階級的なものであり、階級対立、階級闘争、階級的運動の中における対立と抗争こそ社会変革と歴史の進歩である。マルクスにとってこの日の催しはあくまで私的性格の場であったゆえに、このような態度に徹したのであった〉
すべてが終わったあと、出席した一同に共通したマルクスへの感情は、すべてがそう快で、個人的にはマルクスへの不快感や悪感情は一切なかった。そして機会があれば、もう一度会って話をしてみたい、というのが共通の認識であった。
〈階級的に激しい怒りと闘争。だが個人的には極めて親愛の情。すべてに対立物の統一としての二つの側面があり、いつ、どこで、どのように、二つの内の一つの側面が主要な側面として発揮されるのか、それは運動と闘い、情勢と条件が決定していく。ここに弁証法的哲学がある〉
マルクスは哲学と科学に関する思想と理論に徹して行動した。すべてに哲学科学思想と理論を貫いた。
マルクスはどんな苦境にあっても哲学科学思想と理論を確信していた。故に常に明快、厳然、毅然、断固としていた。
真のマルクス主義者は、人格、人間性、人物像としてのマルクスをよく認識し、マルクスに対する尊敬と敬愛の念を堅持してマルクスに学ばなければならない。
第3節
フリードリヒ・エンゲルスとその生涯。すべてをマルクスにささげつつ、思想的・政治的・理論と実践において、常に一体となったその一生のなかにこそ、二人は一つであり、二人を切り離すことはできないことの証明がある!
マルクスの在るところ常にエンゲルスがいた。そしてエンゲルスの一生で明確なとおり、この二人は、思想的、理論的、政治的、人間的に、完全に統一された一つであった。このような歴史的事実を確認すれば、マルクス主義を論ずる人びとのなかにある、二人を分離したり、分割したり、あるいは対立させたりするような発想は生まれてこないはずである。客観的事実、歴史的事実をはっきり確認し、二人を一つとして認識するよう強く訴えたい!
マルクスはエンゲルスについて、一八五九年一月に書いた『経済学批判・序言』の中でつぎのように語っている。
「エンゲルスと私は、経済学批判に関する彼の天才的な叙述が『独仏年誌』に発表されて以来、いつも互いの手紙で意見の交換を行ってきた。彼は私とは別の道を通って同じ結論に達した。彼が一八四五年の春以来、私と同じようにブリュッセルに移り住むようになってから、私たちは、ドイツ哲学のイデオロギー的見解と対立する私たちの見解を共同でまとめあげることにした。実際に私たちはこのことを通じて、これまでの古い哲学思想を完全に清算することができた」(註・これがマルクス主義哲学の原点となり、出発点となった一八四五年発表の二人の共著『ドイツ・イデオロギー』である)。
マルクスが語っているとおり、二人はまったく異なった道を通った。まさに弁証法哲学の示す「対立物の統一」そのものである。まずその風貌(ぼう)から違っていた。エンゲルスは大柄な偉丈夫であった。二十一歳の頃にはドイツ陸軍に入隊して軍事教育を受け、これを武器に三十一歳頃にはドイツ農民戦争(農民一揆)に参加指導し、そして軍事科学にも長じていたので後には「将軍」というニックネームもついた。彼はマルクスと違って高等教育も、大学教育も受けず、すべて独学で学び、十二カ国語を使い分け、その博学多識ぶりから「百科事典」と呼ばれた。
エンゲルスはマルクスより二年後れの一八二〇年十一月二十八日、ドイツのライン州北部にある工業都市バルメンで、大きな紡績工場と商社を経営する裕福な一家で八人兄弟の長男として生まれた。異常なほど熱心なカトリック教徒だった父親は、この長男を一家のあと継ぎにすることを決め、きびしいしつけをした。幼い頃から工場内を連れ歩き、仕事になじませようとした。エンゲルスは広い工場内を飛びまわり、高音で激しく動くいろいろな機械に目を見張り、次々に繰り出される各種の織物に強い好奇心をもった。こうした幼児期の環境が後年のエンゲルスにその行動力と頭脳労働を作り出した。
向学心の強い青年になったエンゲルスは父親とその宗教に反抗して、二十歳のとき自ら志願して一年間、ドイツ陸軍砲兵連帯に入隊。軍事訓練の合間をみつけてはベルリン大学の聴講生として、哲学と科学の究明にとりくみ、マルクスと同じ青年ヘーゲル派に属してドイツ哲学論争に参加した。こうしてエンゲルスはフォイエルバッハ唯物論を究明し、ヘーゲルの弁証法を乗り越え、マルクスと同じ哲学科学思想を獲得した。この科学的哲学思想があの名著『自然弁証法』(一八七五年)、『空想から科学への社会主義の発展』(一八八〇年)などに結びつくのである。その当時マルクスはベルリン大学を卒業し、ライン新聞でドイツ農民戦争を闘っており、エンゲルスはこれに投稿してマルクスの名を知った。そしてエンゲルスは三十一歳の頃には直接農民戦争(農民一揆)に参加、武器を持って戦っている。
父は何としても実業の世界に引き入れようと、一八四二年にはこの長男をマンチェスターに送り出した。マンチェスターはイギリス最大の工業都市で、綿織物工業が発達しており、イギリス産業革命の発祥地でもあった。父はここに共同出資して綿織物工場と貿易商社を持っていた。しかしエンゲルスはこの機会を利用して、市の図書館に通いづめで勉学、イギリス古典経済学を究明。パリに行ってはフランス社会主義を研究した。その成果が『イギリスにおける労働者階級の状態』(一八四五年)となった。
そのころマルクスはドイツを追放され、ジェニーと共にパリに住み、ここで革命的出版物『独仏年誌』を発行、エンゲルスはこれを知り、ここに『国民経済学批判大綱』を投稿、マルクスはこれを大いに評価、このことを機会にエンゲルスは一八四四年八月にイギリスからドイツへの帰途パリに立ち寄り、マルクスと交流した。二人ははじめて顔を合わせ、大いに議論し、それは十日間にもわたった。そしてここで二人の世界観、哲学、経済学、社会主義について、すべての面で完全に一致した。エンゲルスはドイツに帰ってすぐに手紙を書き「パリの十日間は私の人生の中で最高の喜びと楽しいひとときであった」とマルクスに書き送っている。このときから四十年、一五〇〇通にのぼる二人の往復書簡のはじまりとなった。そしてここから二人の固き友情と共同の事業が開始されたのである。
一八四五年一月、パリで革命的活動をしていたマルクスにフランス政府は二十四時間以内の国外追放命令を出した。これはドイツ政府の要求によるものであった。冬の寒さ、金もなく、生後八カ月の長女を抱え、どこに行くか、困り果てていたとき、これを知ったエンゲルスは直ちにベルギーへの脱出、ブリュッセル行きを手配、自らも後にブリュッセルへ行った。一八四五年二月二十一日付のエンゲルスからマルクスへの手紙には「少なくとも政府の卑劣な行為で君を経済的に困らせるということは絶対にさせない」と書いている。以後エンゲルスは父親の経営活動へ参加した一八四五年代から一八七〇年代までの期間、それはマルクスとの共同行動のための資金づくりの期間となった。
一八四五年、マルクスと共著した『ドイツ・イデオロギー』の出版、「ブリュッセル共産主義通信委員会」の設立。そして一八四九年八月にはマルクスはベルギー政府からも追放され、ロンドンに脱出するが、すべてエンゲルスが手配した。一八四七年の「共産主義者同盟」の結成と『共産党宣言』の起草、一八六四年の「第一インタナショナル」の創立、一八七一年の「パリ・コミューン」の対応へと二人は一致して行動した。
それとあわせて、エンゲルスは独自の活動も展開した。一八四八年のドイツ三月革命、一八五〇年のドイツ農民一揆への参加。それと共に、自らの著作と執筆活動も展開、多くの名著を残した。『国民経済学批判大綱』(一八四四年)、『イギリスにおける労働者階級の状態』(一八四五年)、共産党宣言のための学習書である『共産主義の原理』(一八四七年)、『ドイツにおける革命と反革命』(一八五一―五三年)、『ドイツ農民戦争』(一八五一年、一八七五年)、『自然弁証法』(一八七五年)、『猿が人間になるにあたっての労働の役割』(一八七六年)、『反デューリング論』(一八七七―七八年)、『空想から科学への社会主義の発展』(一八八〇年)、『家族・私有財産・国家の起源』(一八八四年)、『ルードヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』(一八八六年)などである。エンゲルスの著作で目を引くのは、全宇宙と人類の歴史を、永遠の過去から永遠の未来に向かって、常に弁証法的法則のもとに発展、前進しつづけるという科学思想である。
一八七〇年代からのエンゲルスは父親からの遺産を整理して、マルクスの活動と生活に注ぐ一方、病身のマルクスを案じて近くに居を移して面倒を見るようにした。そして第一節のマルクスの生涯の項でも明らかにしたように、その死を弔い、遺児たちの引き取りなど、すべてを取り仕切っていった。
こうしてマルクスが残した仕事として『資本論』第二巻を一八八五年に、第三巻を一八九四年に完成、出版した。さらには一八八九年に結成された第二インタナショナルの指導に最後まで力を注いだ。
敗北的修正主義者が出したマルクスの本では、しばしばマルクスとエンゲルスの関係について誤ったことを書いている。「この二人は完全に一致していたわけではなかった」とか。あるいは「エンゲルスの方が正しかった」とか。「エンゲルスはマルクスのことを完全には理解していなかった」とか、である。マルクスが死んだあとすぐエンゲルスは親しい友人のヨハン・フィリップ・ベッケルに手紙(一八八四年十月十五日付)を書いたが、その中で彼はつぎのように書いてる。
「不幸というのはむしろ、僕たちがマルクスを失っていらい、僕が彼の代わりをつとめなければならないという点にある。僕は一生の間、それをなすのが僕の本領であるところの仕事、すなわち第二ヴァイオリンを弾くということをやってきたのであって、そしてまた僕は自分の仕事を全く相当にやりとげたと信じている。そして僕は、マルクスのようにあんな抜群の第一ヴァイオリンをもっているのを嬉しく思っていた。だが、さて僕が急に理論の仕事においてマルクスの位置を引き受けて、第一ヴァイオリンを弾かなければならないという段になると、僕は勢い失策なしにその仕事をやり通せない。しかも、僕ほどにこのことを痛感しているものはないのだ。そして時勢が多少とも動きだすというようなことになれば、われわれはマルクスの死によってどんな損失をしたかを、初めて本当に悟るであろう。急速に処置せられなければならぬような万一の瞬間にも、つねにそれによって彼が事物の核心をとらえ、直ちに決定的な急所につっこんでゆく洞察力、それはわれわれの誰もがもっていないものである。なるほど、平穏無事のときには、事件がときどきマルクスに反して、僕の方が正しかったことを立証したことも、あるにはあったが、革命的瞬間には、彼の判断にはほとんど一点の非も打ち難きものがあった」(向坂逸郎著『マルクス伝』新潮社一九六二年五月刊)。二人の間の関係についてあれこれ言う敗北的修正主義者はこの一文をどう読むのであろうか。
エンゲルスのマルクスに対する同志愛と友情、そして生涯を通じたその人間性と人生観について!
エンゲルスは一八九五年のはじめに末期的食道ガンの進行が発見され、八月五日午後十時半に息を引き取った。七十四歳であった。エンゲルスは個人的には家族をもたなかったので、マルクスの遺児たちが最後まで看取った。遺産はマルクスに連なる人びとに分配された。遺言により、遺体はロンドンに近いワーキング火葬場で灰にされ、それはイギリスとヨーロッパ大陸を結ぶ海峡(イギリス海峡)にまかれた。告別式などは禁じられていたが、社会主義運動の幹部や活動家たちは八月十日、ウォタールー駅の構内で追悼の集まりを開催、多くの社会主義者や第二インターの幹部が集まった。
エンゲルスの生涯で特筆すべきは、その人間性である。マルクスと同じくらいの知的水準をもちながらも常にマルクスを前面に立て、自分は一歩後に下がり、彼が言うところの「犬の仕事」として、マルクス主義運動の「資金づくり」に精を出した。マルクスに対するこのような態度はつぎの一文を見ればよくわかる。
「共産党宣言を貫いている根本思想は、ただマルクスだけに属するものである。―そしてこの思想は、ダーウィンの学説が自然科学の進歩の基礎となったと同様に、歴史科学の進歩の基礎となる使命をもつものである」(『一八八三年の共産党宣言ドイツ語版への序文』一八八三年六月二十八日)
「『共産党宣言』はマルクスと私の共同の著作であるが、私は、その核心をなす基本思想はマルクスのものであることをのべる義務がある」(一八八八年一月三十日『共産党宣言』英語版への序文)。
一八五〇年代に入り、ヨーロッパの労働運動は高揚期を迎え、一八八九年七月には第二インタナショナルがパリにて結成され、一八九〇年五月一日、全世界の労働者がいっせいに決起して「万国のプロレタリア団結せよ!」との共産党宣言のスローガンのもと、世界的規模のメーデーが決行された。エンゲルスはロンドンのメーデーに参加「ああ、マルクスが私と並んでここにたつことができ、これを自分の眼で見ることができたなら!」と叫んだ(『共産党宣言・ドイツ語版への序文』一八九〇年五月一日)。
マルクス主義の正しさを、歴史上はじめてロシア革命によって立証したレーニンは、一九一三年に書いた『マルクス・エンゲルスの往復書簡について』のなかで、二人の固き友情についてつぎのように語っている。
「いにしえの伝説は、人を感動させる友情について多くの物語を伝えている。ヨーロッパのプロレタリアートは、自分たちの科学的理論はマルクスとエンゲルスという二人の学者であり、革命家であるこの人によってつくりだされたが、二人のあいだの友情は、人間の友情について古人の語っている最も人を感動させる物語のすべてを凌駕(りょうが)するものであった。エンゲルスは、常に自分をマルクスの後ろにおいた。彼はある旧友への手紙に書いた。〝マルクスのいたあいだは私は常に第二バイオリンを弾いた〟と。生前のマルクスに対する彼の愛情と、死後のマルクスに対する彼の崇敬とは、誠にかぎりないものであった。この峻厳な闘士であり、厳格な思想家であった人の胸には、深く人を愛する心がやどっていたのだ」と。
第2章
マルクス主義的世界観・歴史観・運動法則とは、すべては発展と前進と止揚という弁証法的哲学観であることを確認せよ!
学習のすすめ「序論」でマルクス主義を読み直そうという目的で、最近多くのマルクス主義に関する出版物が出ているが、その中の代表的な力作として三冊を紹介した。そのうちの一冊『マルクスのアクチュアリティ』には著者によるつぎの一文がある。「東欧革命とソヴィエト連邦の崩壊によってマルクス主義が一つのオーソドクシーとしての地位を失い、さらに冷戦構造が解体して<帝国>と呼ばれる世界規模の経済的・政治的状況が生まれてから、十数年が経過した。二一世紀に入って、このような状況の変化に対応するマルクス研究の新しい傾向もまたようやく明確になってきたようである」と。
また別の一冊『マルクス主義と哲学』の中ではその著者はつぎのように書いている。「この本は<もう一度>マルクスを読む試みである。<もう一度>というのは、言うまでもなく、ソ連型社会主義体制の生成と展開と大崩壊という二〇世紀の歴史の現実をふまえて、<もう一度>という意味である。あたかも何事もなかったかのように、マルクスを読むことではない。正反対なのである。再読は当然、これまでの読み方への異議申し立てに至りつくだろう。その意味で言えば、この本は、マルクス像の変革を目指していると言い換えてもよい」と。
以上のように、この著者たちの文を読めばよくおわかりのように、ソ連や、東欧の社会主義国家はみな敗北して失敗をした。社会主義と共産主義は敗北した。しかしこれはマルクス主義そのものの誤りではなく、マルクス主義を正しく理解していなかったからだ。だからもう一度、始めからマルクス主義を読み直そう、というのである。こういう立場、こういう観点、こういう歴史観が実は敗北主義なのである。負けた、失敗した、などというのが敗北主義なのだ。そういう敗北主義から出発しているから、これらの本の中身はすべてマルクス主義の修正と、自己流の勝手気ままなマルクス主義の解釈に終わってしまった。なぜそうなったのか。結局これらの本の執筆者たちには、マルクス主義の根本原理たる唯物論がなく、その思想理念たる弁証法的歴史観もなく、科学的歴史観としての史的唯物論もなく、『共産党宣言』で示されているマルクス主義の政治上(理論上)の原則もない(これを政治思想として身につけていない)結果である。だからそこにあるのは誠に敗北的で、後退的で、思想的には敗北的修正主義になってしまった。
これとはまったく反対に、われわれ正統マルクス主義は、ソ連・東欧・中国などの社会主義崩壊は歴史の進歩であり、発展であり、前進であるとみる。つまり社会主義と共産主義が最終的に勝利するための必要なステップであり、歴史の必然性をめざす偶然性であり、労働者階級と人民は最後の勝利のために、もう一度原点に帰れと求めた巨大な歴史的産物としてみる。巨大な事件ほど、その内部には重大な真理がかくされている。それはどういうことかということをこれから考察する。
第1節
歴史的事件をどうみるかの教科書は『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』(マルクス、一八五一―五二年)である。つまり歴史的事件を哲学原理(歴史科学)と『共産党宣言』から演繹的にみるとき、ソ連・東欧の崩壊の根源、元凶はフルシチョフの「スターリン批判」という名の修正主義によって、党と権力が変質し、マルクス主義が完全に放棄された結果であった。すべては権力問題であり、すべては哲学的内因論にある!
まず最初の出発点は、ソ連・東欧などの社会主義崩壊というこの存在(事実)をどう見るかということである。哲学(唯物論)的にどうみるのか。マルクス主義の原点・原理たる唯物論的にみるとはどういうことか。それは①客観的な存在、その事実を観照的、現象的、表面的に見るのではなく、その本質をしっかりつかむ。②その本質とは、マルクス主義の政治上・理論上の原則(それは『共産党宣言』の核心たる、すべては権力問題である。すべては階級対立と階級闘争である。すべてはプロレタリア独裁が解決する、という政治上・理論上の原則)から導き出す。③この本質をつかんで「革命的実践活動」(『フォイエルバッハにかんするテーゼ』でマルクスが強調したこの活動)を重視し、実践する。これが唯物論の原理であり、この立場から一切を支配しなければならない。
こうしてみるとき、ソ連・東欧・中国の社会主義崩壊の本質、その根本原因、その元凶は、あのフルシチョフによる「スターリン批判」という名の修正主義によって、中国では鄧小平によるあの「白猫・黒猫」論に代表される修正主義(経済主義)によって、その党と権力が変質し、マルクス主義が完全に放棄された結果であった。すべては思想問題であり、すべては権力問題であり、すべては哲学的内因論にある。そして歴史的事実と各種の証言で明らかなとおり、ソ連や中国がおかしくなったのは、みなフルシチョフや、鄧小平以後であった。
修正主義に毒されるまでの社会主義は偉大であった。くわしくは第四・五節で述べるのでよく学習していただきたいが、ここではその代表的一例を述べておく。
人類の歴史上はじめてマルクス主義にもとづく社会主義を実現させたのはレーニンであった。レーニンほど徹底的にマルクス主義の原理・理念・理論上の原則を守りぬき、実践した革命家は他にいない。それは第二インターとカウツキーに対する徹底的な闘争をみればわかる。これがあったから十月革命は勝利したのである。
そして一九一八年から一九二二年までの五年間にわたる外国干渉軍と国内反乱軍との戦いとその勝利である。若いソビエトに国外から帝国主義と資本主義の十六カ国がいっせいに攻め込んできた。それに呼応して国内の反乱軍も蜂起した。歴史上このような過酷な戦争があっただろうか。一五〇〇万人の犠牲を出してソビエト社会主義は勝利した。偉大な社会主義と共産主義は勝利したのである。
レーニンのあとを引き継いだスターリンは社会主義建設五カ年計画を連続して実施、おくれた農業国のロシアを、近代的重工業国家に仕立てあげた。その急速な計画経済の成功については当時の世界経済統計をみてもはっきりしている。そして一九七一年代のアメリカ経済学会の会長で、アメリカ経済界の大御所であり、米国の知性の代表として知られたジョン・K・ガルブレイスもその出版物でソビエトの発展と成長を高く評価している。そして日本においては、第一級の知識人にして、反マルクス主義の闘将として名高い小泉信三も、その出版物『マルクス死後五十年―マルクシズムの理論と実践―』(一九三三年出版)のなかで、マルクス主義の理論問題では激しく批判しつつ(もちろんこの批判は的外れ的笑い話にすぎないが)、それでもソビエト社会主義建設の巨大な成功には目を見張り、自分の認識不足を反省し、スターリン以下のソビエト幹部の指導力に脱帽しているのである。
そして第二次世界大戦中に、アメリカ軍の戦略諜報機関「OSS」の幹部としてヨーロッパ戦線で活動し、戦後はアメリカの「CIA」監察官になったジョン・H・ウォラーが書いた『見えない戦争』(日本語版は『ヒトラー暗殺計画とスパイ戦争』として、二〇〇五年一月に、鳥影社が出版)では「スターリンの大粛清事件」の背景が明らかにされている。第二次世界大戦前夜のヨーロッパは各国の諜報・スパイ活動が入り乱れていた。その中でアメリカ諜報機関はソビエト赤軍内の反乱計画もつかんだ。後でOSSもこれを確認した。それは、ソビエト赤軍の最高幹部で、参謀総長のトハチェフスキー元帥がナチス・ヒトラーと手を結び、ドイツがソ連に進攻したときにあわせて、ソビエト内で反革命軍の蜂起を謀る、というものであった。だがこのことはやがてソビエト諜報機関も二重スパイを通じて掌握するに至った。そして独・ソ開戦前(一九三七年六月)にスターリンとソビエト政府は、軍と政府と党の内部に組織されていたトハチェフスキーに連なる旧帝政時代の生き残り組を中心にした反革命組織を一連の芋づる式摘発によって一網打尽にした。このことをブルジョアジーたちは「スターリンの大粛清事件」という。しかしこの問題の本質は、「OSS」のウォラー氏の記録にもあるとおり、これはまったく明らかなように、まさに独・ソ戦の前しょう戦だったのである。スターリンはこの前しょう戦に勝利したから、一九四一年六月二十二日にナチス・ドイツのソ連進攻にはじまる独・ソ戦の本戦に、ソビエト政権は党・政府・赤軍の三位一体によって勝利したのである。この問題については第五節で詳しく書いてあるとおり、イギリスの軍事科学者リデル・ハートも認めているのである。スターリンの粛清とは、ナチスと外国軍と結んだ国内の反革命軍に対する戦いであって、帝国主義による侵略的弾圧とは質が異なる。この階級的性格がわかるか、わからないか、これは革命か反革命かの分水嶺(れい)である。歴史が証明するとおりスターリンは偉大であった。
レーニン、スターリンのソビエト社会主義はマルクス主義の原理・理念・原則に忠実であったが故に勝利した。そしてフルシチョフ、鄧小平の変質によって党と権力がマルクス主義の原理・理念・原則を放棄したときにそれは敗北した。歴史はこのことをわれわれに教えた。ここに歴史の教訓があり、ここにマルクス主義の偉大さがある。
第2節
マルクス主義とは何か。それはどのようにして生まれ、成長し、完成されたのか。その原理からみるとき、ソビエト、東欧、中国の社会主義崩壊は、社会主義と共産主義の最終的勝利のために必要なステップである。歴史とはこのような必然と偶然の統一された発展と前進であり、弁証法的歴史発展のみごとな証明である。弁証法的歴史科学からすべてをみつめよ!
レーニンは一九一四年に執筆した論文『カール・マルクス―略伝とマルクス主義の解説』のなかでつぎのように書いている。「マルクス主義とは、マルクスの見解と学説の体系である。マルクスは、人類の三つのもっとも先進的な国に属する十九世紀の三つの主要な思想的潮流の継承者であり、天才的な完成者であった。それはドイツの古典哲学、イギリスの古典経済学、そして一般にフランスの革命的諸学説とむすびついたフランス社会主義である」と。そしてまたレーニンは一八九四年に執筆した論文『人民の友とは何か』の中で「マルクス主義の正しさは、それが最高度の厳密な科学性と革命性(註・哲学と科学)が結合しているからであり、この二つの特性が切っても切り離せない統一が理論そのものの中にあるからである」と書いている。注目せよ。マルクス主義は人類の歴史が到達した英知の「止揚」の産物であり、哲学的であると同時に科学的なのである。
レーニンは明確に断言している。マルクス主義とは最高度の厳密な科学性(科学的法則)と革命性(哲学思想)との結合である、と。そしてレーニンは、マルクス主義とは、人類が十九世紀に到達した英知としてのドイツ哲学、イギリス経済学、そしてフランス社会主義の継承、発展、前進、止揚、完成、であった、と明言している。つまり、一切は、すべては、継承・発展・前進・止揚・完成、という弁証法的歴史観、史的唯物論の歴史観がマルクス主義の本質的原理なのである。
だからエンゲルスは『共産党宣言』の一八七二年ドイツ語版の序文のなかでつぎのように言っている。「事情がどんなに大きく変化したにしても、この『宣言』のなかに述べられている一般的諸原則は今日でも完全に正しい。個々の点、部分的な点はあくまで改善の余地があるであろう。それはいつでも、どこでも、当面する歴史的事情がこれを決定するであろう」と。
エンゲルスは言っている。マルクス主義の諸原則は絶対に正しい。そして個々の問題、手段や方法や、形式上の問題は常に歴史の発展によって変化され、改革され、改善されるものである。つまり、発展・前進・止揚されるのだと言っているのだ。エンゲルスが主張し、レーニンが実践したとおり、マルクス主義の原理、理念、原則は断固として守りぬく。同時に具体的な問題、戦略、戦術上の問題は歴史時代と情勢と条件によって常に発展、前進、止揚されていく。これが弁証法であり、マルクス主義であり、これがマルクス主義の哲学科学思想なのである。
エンゲルスはもっとくわしく、もっと厳密に、全宇宙と人類世界の運動法則を解明した文献『自然弁証法』を一八七五年に執筆している。人類世界とそのすべては常に運動し、発展し、前進し、止揚され、転換されていくのであって、どのような事件、事物も決して否定的で後退的で無意味なものはない、としている。否定、停止、後退は死滅であって、運動している限りそういうものはこの世には存在しない。
人類の歴史を知ればはっきりしている。人類が出現した当初は生産力がなく、自然採集経済であったため、その社会は国家と権力はなく、原始的共同体(コミュニティー)社会であった。やがて生産活動が始まり、生産力が高まり、財産が出来てから国家と権力が生まれた。その国家と権力と社会も、生産力の発達に合わせて変化していった。歴史上それは、原始共同体―奴隷制―封建制―資本主義社会―独占支配と帝国主義の時代―最高に登り詰めた帝国主義の崩壊から人民の社会・近代コミュニティー・社会主義へ、これが人類史の歴史的発展法則である。
このように歴史は一貫して、前へ、前へと前進しているのであって、後退ということはありえない。そしてまた、科学的法則からいって、資本主義と独占資本がこのまま、そこで止まってしまって動かなくなるということもありえない。それは死であるからだ。歴史は一貫した運動・発展・前進・止揚・転換するのであって、どこにも否定や、後退や、停止はない。
エンゲルスはその自然弁証法でくわしく弁証法的運動法則を説いているが、それの核心はつぎのとおりである。①すべては必然と偶然の連関し、統一された運動する世界である。②すべては止揚による発展と前進と転換の世界である。③運動する力は内部(内因)の対立物の矛盾と闘争である。④発展・前進・転換は根本的で、質的なものである。⑤最後は爆発と収れんによってすべては成る。
以上のような、弁証法的・哲学的・科学的歴史観からみるとき、さきに紹介したマルクス本の『マルクスのアクチュアリティ』や『マルクスと哲学』などの著者がいうような「ソ連の崩壊によってマルクス主義の正統性はなくなった」とか、「これまでのマルクス像の変革をめざしてマルクスを再読しよう」などということが、如何に哲学を知らない非マルクス主義であり、敗北的修正主義の見本であり、マルクス読みのマルクス知らずであるということが理解されよう。
そしてこうした敗北的修正主義者たちは、マルクスやレーニンの文献をよく読んでいないか、読んでも理解できないのである。フルシチョフや鄧小平などの裏切り者は革命運動の途中では必ず出現するのだということは早くから予告されていた。一九二一年六月に開かれた第三インタナショナル第三回世界大会の席上レーニンはつぎのように演説している。「革命に勝利したからといって絶対に安心してはならない。資本主義陣営に包囲され、帝国主義が存在し、国内にはまだブルジョア思想と旧体制の残りかすを捨て切れない人間はいくらでもいる。党と国家権力は益々内部を浄化し、裏切り者に対処しなければならない」と予告した。そしてマルクスも『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』(一八五一―五二年)のなかで「労働者階級は最終的勝利のために、必ず一度は途中で立ち止まり、理論上の原則にもとづいて、最初からやり直すことが必要である」と予言している。歴史は、ソ連や中国の社会主義の崩壊という事実を通じて、マルクスの予言とレーニンの予告の正しさを証明した。あわせて歴史はこのことを通じて、われわれ正統マルクス主義者に、その後のスターリンや、毛沢東など、マルクス・レーニンの継承者が、いくつかの歴史的条件のもとで、右の予言と予告の正しい認識とその実行を実現できなかったことに警告を発した。ソ連・東欧・中国などの社会主義崩壊における最大の歴史的意義はここにある。故にこの事件はマルクス主義運動における偉大な勝利なのである。われわれは歴史の要求に答えて、断固として、歴史を「止揚」しなければならない。肝に銘ずべきは、歴史的事件を敗北的修正主義としてとらえて動揺することなく、いかに歴史を〝止揚〟するかについて、実践的に議論し、自ら行動することである。
マルクス主義哲学の原点たる『フォイエルバッハにかんするテーゼ』(一八四五―四六年)の中の第一の項で<これまでの唯物論(フォイエルバッハのをもふくめて)の主要な欠陥は…「革命的」な活動、「実践的に批判的な」活動の意義を理解しない>と強く主張している。実践的に、行動的に哲学をつかめ、哲学的唯物論の原理と弁証法的理念にもとづいて実践し、行動せよとマルクスは強く主張している。ソ連、東欧、中国などの社会主義崩壊とは何かを正しく理解し、どう実践するのか、これが正統マルクス主義者か否かの分かれ道である。われわれは歴史の要求に答えて必ず歴史を〝止揚〟するであろう。
第3章
マルクス主義の原点、その原点は哲学である。唯物論、弁証法、史的唯物論を正しく認識せよ!
万物を支配する根本原理は哲学であり、科学と結合した絶対的真理は唯物論である。マルクス主義的唯物論の核心は『フォイエルバッハにかんするテーゼ』にある。哲学学習の出発点をこの「テーゼ」に求めなければならない。
エンゲルスは一八八六年に『ルードヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』を書いたが、その中でつぎのように言っている。「物質と観念の相互関係に関する認識において哲学者たちは二つの大きな陣営に分裂した。自然に対する精神の根源性を主張し、したがって結局はなにかしら世界創造を想定した人びとは……観念論の陣営をかたちづくった。自然を根源的なものとみなした他の人びとは唯物論のいろいろな学派に属した」と。エンゲルスの説くとおり、哲学は唯物論か、観念論か、であってその中間はありえない。つまり、自然と物質と存在と事物を一切の土台としてみる唯物論か、反対に人間の意識、精神、思考を一切の土台としてみる観念論か、である。そしてこの観念論と対立する唯物論を完成させたのがマルクスであった。そのときマルクスは思いつきや、突然変異ではなく、当時のドイツ哲学界の最高峰であったヘーゲルとフォイエルバッハを徹底的に究明し、これを止揚して(肯定的部分は引き継ぎ、弱点や誤りを克服して、正しいものに前進させて)完成させた。このことは〈学習のすすめ〉第一節の、マルクス・エンゲルスの生涯でくわしく解明されている。こうしてマルクスの革命運動とその生涯は哲学からはじまった。だからエンゲルスは一八七五年の『ドイツ農民戦争』のなかで「もしもドイツ哲学がなかったらマルクス主義は生まれなかったであろう」と書き、マルクスは一八四四年二月に執筆した論文『ヘーゲル法哲学批判・序論』の中で「哲学はプロレタリアートの中にその物質的な武器をさがしあてる。同時にプロレタリアートは哲学のなかに精神的な武器をさがしあてる」と書いた。マルクスは同じ文書の中で「思想が大衆をとらえたとき、それは物質的な力となる」と言っているのはこのことなのである。哲学とその思想こそが万物を動かす原動力なのである。
哲学の役割についてエンゲルスは一八七五―六年に執筆した『自然弁証法』のなかでつぎのように書いている。「現代の自然科学は、運動の不滅の命題を哲学から採用しなければならなかった。それなしには自然科学は存在できなかった」と。このことを立証した現代の科学者はたくさんいるが、二〇〇二年度のノーベル物理学賞を受けた東大特別栄誉教授の小柴昌俊氏は、二〇〇三年二月十七日付の日本経済新聞『私の履歴書』の中で「私たち現代の科学者が実験と研究によって証明していることがらはみな、古代ギリシャの哲学者たちが、宇宙のあり方について予言したことを、一つ一つの実験と研究で科学的に立証している」と語った。まさにエンゲルスが言っているとおり、哲学ぬきに科学はありえないし、科学は哲学(理論と思想)を導きにして進む。ではこの偉大な哲学を学ぶためには何からはじめるべきか。これこそ『フォイエルバッハにかんするテーゼ』である。
ところが〈学習のすすめ〉序論で紹介した、マルクスを再読しようという目的で出版されたマルクス本の代表作の一冊『マルクスのアクチュアリティ』の著者はその中でつぎのように書いている。「フォイエルバッハに関するテーゼは、たぶんその短さと歯切れの良さによって長く愛好されてきた。マルクスに関心をもったことのある人なら、だれも一度は引用文という形でどこかで目にしたことがあるはずである。……このテーゼというのは、マルクスが一八四五年の春にノートに書き留めていた一種のメモである」と。ごらんのとおりこの著者は「テーゼ」について語るとき、簡単に、茶化し、単なるメモだというだけであって、エンゲルスがその著『ルードヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』で明確にした、この「テーゼ」のもつ歴史的意義と、綱領的意義と、マルクス主義的哲学の核心的意義については何一つ語らないのである。それはつまり、この著者は、この「テーゼ」のもつその価値がわからないのである。
「寸鉄人を刺す」という言葉がある。光り輝く短い言葉のことである。短いがその中には人の心を揺り動かす力強く深遠な意味がふくまれているということである。われわれ真のマルクス主義者は、マルクスの短い言葉の中にある、深く、光り輝く、その思想を学びとるだけの思想・政治能力を持たねばならない。マルクス主義の研究家として名高い人びと自身が、この「テーゼ」に関してかくも浅薄なのはなぜか。これこそマルクス読みのマルクス知らずであり、マルクスを読めないのであり、読んでもわからないのであり、マルクスの生涯を知らないのであり、マルクスのように自らの実践と行動のなかでマルクスを学ぶことができないのである。われわれは反面教師としてこのような事実からも学ぶ。
第1節
マルクスの『フォイエルバッハにかんするテーゼ』について!
この「テーゼ」の歴史的意義、綱領的意義、マルクス主義哲学の核心としての意義を語ったエンゲルスの思想認識を深く知らねばならない。このことがマルクス主義哲学学習の出発点である。
第一章のマルクスとエンゲルスの生涯で明らかにされているとおり、マルクスもエンゲルスも、ベルリン大学におけるヘーゲル左派運動を通じて二人はヘーゲルとフォイエルバッハを完全に克服(止揚)して彼らの哲学(マルクス主義哲学)を完成させた。二人は共同してドイツの古典哲学に宣戦布告をしたが、その歴史的文献が『ドイツ・イデオロギー』(一八四五年)である。この文献こそマルクスとエンゲルスの共著によるマルクス主義哲学の歴史的宣言の第一歩であった。
このことについて一八五九年一月に執筆した『経済学批判・序言』の中でマルクスはつぎのように言っている。「エンゲルスと私は別の道を通って同じ結論に達した。彼が一八四五年の春以来、私と同じようにブリュッセルに移り住むようになってから、私たちは、ドイツ哲学のイデオロギー的見解と対立する私たちの見解を共同でまとめあげることにした。実際に私たちはこのことを通じて、これまでの古い哲学思想を完全に清算することができた」と。だからこの『ドイツ・イデオロギー』こそマルクス主義哲学の記念碑的文献なのである。
さて、マルクスが死んだあと、エンゲルスはマルクスが残した多くの原稿や書類や未発表の文書を整理していたとき、マルクスの手帳に一つのメモを発見した。それは「フォイエルバッハについて」と記した十一の項目にわたる短いメモ書きであった。このメモをみたときエンゲルスは、二人で相談して書いた『ドイツ・イデオロギー』の骨格がここにあることを知った。つまりマルクス主義哲学(唯物論)の骨格だったのである。だからエンゲルスは一八八六年に『ルードヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』を発表したときつぎのように書いた。「マルクスのこの一文の中には新しい世界観の天才的な芽ばえがかくされている最初の記録として極めて貴重な文献である」とのべ、エンゲルスは正式に『フォイエルバッハにかんするテーゼ』と命名した。テーゼとは綱領のことであり、基本的方針のことである。エンゲルスは『ドイツ・イデオロギー』の共同執筆者として、このようにこの「テーゼ」のもつ思想的意義を深く認識していたのである。この「テーゼ」のもつ歴史的意義、綱領的意義、核心的意義としてのこの「テーゼ」の十一の項目を本当に理解できるかどうか、ここに正統マルクス主義者か否かの分かれ道がある。以下その全文を、大月書店発刊(一九六三年)大内兵衛、細川嘉六監訳『マルクス=エンゲルス全集・第三巻』から紹介する。
マルクス『フォイエルバッハにかんするテーゼ』(フォイエルバッハについて)
一
これまでのあらゆる唯物論(フォイエルバッハのをもふくめて)の主要欠陥は対象、現実、感性がただ客体の、または観照の形式のもとでのみとらえられて、感性的人間的な活動、実践として、主体的にとらえられないことである。それゆえ能動的側面は、唯物論に対立して抽象的に観念論―これはもちろん現実的な感性的な活動をそのようなものとしては知らない―によって展開されることになった。フォイエルバッハは感性的な―思惟客体とは現実的に区別された―客体を欲するが、しかし彼は人間的活動そのものを対象的活動としてとらえない。それゆえ彼は『キリスト教の本質』においてただ観想的態度のみを真に人間的な態度とみなし、それにたいして、他方、実践はただそのさもしくユダヤ人的な現象形態においてのみとらえられ固定される。それゆえ彼は「革命的な」活動、「実践的に批判的な」活動の意義を理解しない。
二
人間的思惟に対象的真理がとどくかどうかの問題はなんら観想の問題などではなくて、一つの実践的な問題である。実践において人間は彼の思惟の真理性、すなわち現実性と力、此岸性を証明しなければならない。思惟―実践から切り離された思惟―が現実的か非現実的かの争いは一つの純スコラ的な問題である。
三
環境と教育の変化にかんする唯物論的教説は、環境が人間によって変えられ、そして教育者自身が教育されねばならぬことを忘れている。それゆえこの教説は社会を二つの部分―そのうちの一方の部分は社会を超えたところにある―に分けざるを得ない。
環境の変更と人間的活動または自然変革との一致はただ革命的実践としてのみとらえられるし、合理的に理解されうる。
四
フォイエルバッハは宗教的自己疎外、すなわち宗教的世界と世俗的世界への世界の二重化、の事実から出発する。彼の仕事は宗教的世界をそれの世俗的基礎へ解消するところにある。しかし世俗的基礎がそれ自身から離脱して、雲のなかに一つの自立的な王国を自身のためにしつらえるということは、ただこの世俗的基礎の自己滅裂状態と自己矛盾からのみ明らかにされるべきである。それゆえにこの世俗的基礎そのものがそれ自体において矛盾したものとして理解されるとともにまたそれ自体において実践的に変革されねばならない。したがってたとえば地上の家族が聖なる家族の秘密としてあばかれた以上は、こんどは前者そのものが理論的かつ実践的になくされねばならない。
五
フォイエルバッハは抽象的思惟にあきたらず、直観を欲する。しかし、彼は感性を実践的な、人間的感性的な活動としてとらえない。
六
フォイエルバッハは、宗教性を人間性へ解消する。しかし、人間性は個人に内在する抽象物ではおよそない。その現実性においてはそれは社会的諸関係の総体である。この現実的なあり方の批判へ乗り出すことをしないフォイエルバッハはそれゆえにいやおうなしに、
(一)歴史的経過を切り捨て、宗教的心情をそれだけとして固定して、一つの抽象的―孤立的―人間としての個体を前提せざるをえない。
(二)本質はそれゆえにただ「類」としてのみ、内なる、無言の、多数個人を自然的に、結び合わせる普遍性としてのみとらえられる。
七
それゆえフォイエルバッハは、「宗教的心情」そのものが一つの社会的産物であること、そして彼が分析する抽象的個人が或る特定の社会形態に属することを見ない。
八
あらゆる社会的生活は本質的に実践的である。観想を神秘主義へ誘うあらゆる神秘はそれの合理的解決を人間的実践のうちとこの実践の把握のうちに見いだす。
九
観照的唯物論、すなわち感性を実践活動として把握することをしない唯物論が到達するところはせいぜい個々の個人と市民社会との観照である。
一〇
古い唯物論の立場は市民社会であり、新しい唯物論の立場は人間的社会もしくは社会的人類である。
十一
哲学者たちは世界をたださまざまに解釈してきただけである。肝腎なのはそれを変えることである。
第2節
『フォイエルバッハにかんするテーゼ』の第一の項に唯物論の原点がある。ここに万物を支配する哲学原理がある。この項を深く、しっかり、はっきり、正確に理解できるか、できないか、ここで本当のマルクス主義者か、否かが決定される!
マルクスの本をはじめから読み直そうという目的で出版された出版物の中の『マルクスのアクチュアリティ』の著者はマルクスの『フォイエルバッハにかんするテーゼ』についてつぎのように書いている。「テーゼは、すべてがフォイエルバッハの観想的で直感的な唯物論に関するマルクスの批判的コメントであり、いわば、実践的で主体的な唯物論のすすめ、にすぎない」と。誠に、あっさりと、いとも簡単に、これは単なるコメントだという。ここにはエンゲルスのこの「テーゼ」に対する深遠な思想認識もなければ、エンゲルスがなぜわざわざ「テーゼ」と名づけたのかについてもまったく理解できない。だから「テーゼ」の中身についての論述は何もないのである。この「テーゼ」の寸鉄人を刺すその内容を深く知ろうともしないのである。これが本当のマルクス主義者であろうか? われわれ正統マルクス主義者はつぎのように考える。
『フォイエルバッハにかんするテーゼ』の第一の項は、まさにマルクス主義哲学の土台であり、万物を支配する根本原理たる唯物論の根幹が、正確に、厳格に、きびしく定式化されている。唯物論がここにある。この「テーゼ」にもとづいて『ドイツ・イデオロギー』が展開されている。だからこの項にあわせて『ドイツ・イデオロギー』を読まねばならない。そうすればこの第一の項の内容がよくわかる。
マルクスはこの項の中でつぎのように言っている。「これまでのあらゆる唯物論(フォイエルバッハのをもふくめて)の主要欠陥は、対象、現実、感性がただ客体の、または観照の形式のもとでのみとらえられて、感性的人間的な活動、実践として、主体的にとらえられないことである」と。つまり、フォイエルバッハをふくめた古い唯物論は、目の前に存在している(出現した)事実、現実、事物、事件、事故を、観照的に、そのままに、感覚的に、感情的に、直感的にとらえるだけである。したがって感性的、理性的、理論的、知性的にとらえることができない。だから結果として、客観的存在(現実、事物、事実、事件、事故)が人間(の頭脳)に何を反映させているのか、何を求めているのか、その能動性、知性、目的・意識性は何か、ということがとらえられない、とマルクスは言ってるのである。
そしてマルクスはつづけてつぎのように書いている。「それゆえ能動的側面は、唯物論に対立して抽象的に観念論―によって展開されることになった。……それゆえに彼は〝革命的な〟活動、〝実践的に批判的な〟活動の意義を理解しない」と。つまり、フォイエルバッハなどの古い唯物論は、結果として、存在(現実、事物、事実、事件、事故)がそのことを通じて何を求めているのかという意識性、能動性、知的要求、目的・意識性をつかめない故に、革命的な実践活動、批判的活動(変革のための行動)の重要さを理解できない。つまりは実践しない、行動しない、ただおしゃべりをするだけだときびしく提起しているのであり、革命的実践活動をきびしく求めているのである。
この第一の項にもとづいて『ドイツ・イデオロギー』ではつぎのことが強く展開されている。つまり、自然科学の法則と違って、社会科学においては人間が主体なのである。人間とは社会的人間である。だから人間の社会生活(生産力と生産関係の相互関係)の中から意識されてくるその思想性(認識)による実践と行動が現実を支配していく。つまり、存在が意識を生み出し、その意識が実践と行動を通じて存在を支配していく。だから存在を(客観的現実を)変革する決定的要因は目的意識性なのである。そして、存在という現実(物質運動)は常に変化し、発展していくものであり、それにつれて人間の意識もまた常に変化し、発展していくものである。故に人間の思想、意識は常に変化し、発展し、こうして存在に働きかけていかねばならない。マルクスはこうして目的・意識的な実践活動の決定的意義を強く主張している。
『フォイエルバッハにかんするテーゼ』と『ドイツ・イデオロギー』で展開されているマルクス主義唯物論の骨格は何であるか。それはつぎの三項目に集約される。
第一、全宇宙と万物は運動する物質である。これが存在であり、一切の土台である。存在とは客観的事実であり、現実、現象、事件、事故である。そしてその存在は運動し、発展し、転換していく歴史的必然性が生み出す偶然性である。故にあらゆる存在を運動する歴史の必然性(歴史的段階と歴史時代)の産物としてとらえる。けっして観照的、感覚的、表面的にとらえてはならない。
〈故に先進分子と前衛党の活動と政策決定にあたっては、まずその存在、客観的事実、事件、事故などの偶然性を、すべては歴史の必然性としてとらえる。つまりは『歴史科学と現代帝国主義論』にもとづく歴史時代認識の必然性としてとらえる〉
第二、確認され、とらえられた客観的事実、存在、事件、事故というその偶然性の中に貫かれている歴史の必然性とは何か、その本質を徹底的に明らかにする。この必然性を、思想的、政治的、理論的に(知性的に)明確にされてこそ、はじめてわれわれは何をなすべきかという、実践と行動指針と政策が明らかになる。つまり、存在が意識を生み、意識が存在を支配していく。
〈故に先進分子と前衛党の活動と政策決定にあたっては、偶然性の中に貫かれる必然性を、思想的(人民戦線綱領とその思想)、政治的(人民戦線政策)、理論的(理論上の三原則)を指針にして、はっきり、しっかり、正確に、一貫して、強く、正面から提起(指導)する〉
第三、唯物論と観念論の決定的な違いは、人類社会と社会科学においては、人間の能動性としての目的・意識(革命的意識にもとづく実践と行動)の重要さを認めるかどうかにある。唯物論の核心は、革命的実践によってのみ歴史がめざすその必然性は実現される、ということにある。物質(存在)が意識(精神)を生み出す。ひとたび生み出された意識(思想・精神)は、独自の機能(働き)によって存在(物質)を支配する。その結果として、人間の意識によって存在(現実)は支配される。ここに「人間は環境の産物であると同時に、環境は人間によって支配される」(マルクス・エンゲルス『ドイツ・イデオロギー』一八四五年)、「批判の武器は、武器による批判にとってかわることはできない。物質的な力を倒すには物質的な力をもっていなければならない。そして理論も、大衆をとらえるやいなや、それは物質的な力となる」(マルクス『ヘーゲル法哲学批判・序論』一八四四年)ということの意味がある。偶然性を必然性に転化させるための「革命的活動、実践的に批判的な活動」を目的・意識的に展開する。
〈故に先進分子と前衛党の活動と政策決定にあたっては、偶然性を必然性に転化させる決定的要因としての「革命的実践」(革命的綱領、人民戦線綱領、人民戦線政策の目的意識的な展開)を重視する。ここに正統マルクス主義と前衛の果たすべき歴史上の使命がある〉
第3節
マルクス主義哲学の核心たる『フォイエルバッハにかんするテーゼ』の第十一の項「哲学者たちは世界をたださまざまに解釈してきただけである。肝腎なのはそれを変えることである」というこの一文のもつ深遠な思想的・政治的意味をよくつかめ。そして哲学者たる者の保持すべき人格、人間性、人間像とは何かを説くマルクスの心を知れ!
『フォイエルバッハにかんするテーゼ』とは何かについてはすでに第三章の前文と(一)の項でくわしく展開した。とくに重要なことは、エンゲルスが一八八六年に書いた『ルードヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』の中身をよく認識すべきことも説いた。そしてこの「テーゼ」の全十一の項目に目を通せばつぎのことは明白になる。つまり、全十一の項目の中では第一と第十一の項が重要であり、この二つの項目は結びついており、関連しており、そしてこの二つの項が全十一の項を支配する二本足になっていることがはっきりする。だからこの第一と第十一の項をしっかり認識すれば全体をつかむことができる。そしてこの第一の項(唯物論)はすでに第三節の(二)でくわしく解明したので、ここでは第十一の項について論ずることにする。
マルクスはこの項でつぎのように主張している。「哲学者たちは世界をたださまざまに解釈してきただけである」と。つまり、フォイエルバッハをふくめた古い唯物論は、宇宙と人類と人間の歴史について、その過去と未来について、いろいろと、さまざまに、解釈したり、解説したり、論評したり、おしゃべりをしただけである。文章だけ、言葉だけ、おしゃべりだけでは何の役にも立たない、といっているのだ。
そしてマルクスはつづけてつぎのようにいう。「肝腎なことはそれを変えることである」と。つまり、大切なこと、決定的なことは、世界を変革すること、革命を実現すること、そのために運動し、行動し、実践すること、闘うことだ、といっている。宇宙と人類世界、そして人間の歴史は常に運動しており、動いており、物質の運動法則として常にそこでは力が作用している。故に真の哲学者(唯物論)は物質の運動法則に従って、運動し、実践し、行動し、闘わねばならない。これが世界を変革する力となって発展と前進に貢献することだ、と説く。だからマルクスが「テーゼ」の第一の項で「古い唯物論は、人間の意識的な、批判的な、実践と行動の意義を理解しない」といっているのはこのことなのである。
そしてマルクスが『ヘーゲル法哲学批判・序論』(一八四四年)の中で「哲学はプロレタリアートの中にその物質的な武器をさがしあてる。同時にプロレタリアートは哲学の中に精神的な武器をさがしあてる」と書き、また「批判の武器(註・解釈、解説、おしゃべり、評論)は、武器による批判(註・実力、力、権力とその行使)にとってかわること(註・それに打ち勝つこと)はできない。物質的な力を倒すには物質的な力をもっていなければならない。そして理論も、大衆をとらえるや否や、それは物質的な力となる(註・力には力をもって対抗しなければならない。そして人民大衆は理論、思想、政治的自覚を身につけたとき、実践と行動と実力を発揮する)」と書いているのは、まさにこの「テーゼ」の第一と第十一の項の意味なのである。
つまり、マルクスはこの「テーゼ」の中で、その短い一文の中で、深遠な思想を展開している。とくに注目すべきは、マルクスはここで弁証法的哲学を展開している。弁証法は物質の運動法則であり、弁証法的歴史観であり、人間の生き方であり、哲学者の人間性についてである。つまり、哲学は闘いであり、行動であり、唯物論とは運動する哲学であり、闘う哲学である、ということ。故に真の哲学(者)は運動し、闘わねばならない。だから哲学者は行動派でなければならず、革命家でなければならない。そしてマルクスは自らそのように行動した。このことは<学習のすすめ>第一節でその生涯を明らかにしたが、マルクスとエンゲルスは哲学者であると同時に実践家であり、革命家であった。したがってこの「テーゼ」の第十一の項は、真の哲学者とは何か、哲学者たる者の生き方、その人間性、人格、人間像を示した深遠な一文なのである。これがわからないようでは哲学者たり得ないだろう。
マルクスを再読しようとして出版された本の執筆者たち(古いマルクス主義学者)は哲学原理がさっぱりわかっていないため、その中身はまったく浅薄(せんぱく)な見本となってしまった。その事実を見よ!
この「テーゼ」に関する歴史的経過とその価値、その意義、マルクス主義哲学の骨格としての政治的意味については第三節の(一)、(二)でくわしく述べたとおりである。そしてマルクスを再読しようという目的で出版された各種の本の執筆者たちが、このことをまったく知らないが故に、第一歩からマルクス主義哲学を理解できなかったことについても明らかにしておいた。その結果として、この「テーゼ」の最後の項、つまり第十一の項についてもその理解は驚くほどの無知・無能で、思わず笑いたくなる。
『マルクスのアクチュアリティ』の著者はこの第十一の項についてはつぎのように書いている。
「第十一テーゼでいわれている〝世界を変革する〟とはどのようなことであり、どのような〝世界〟をどのように〝変革〟すべきなのかということについては、先行するこれらのテーゼを読んだだけではわからないのである。だからその結果として、これらのテーゼそのものもまた哲学者たちによってさまざまに解釈されてきた」と。このとおり、前節でわれわれが明確にしたこの第十一の項の意義、哲学者たる者の保持すべき人格、人間性、人間像とは何かについてのマルクスの心について、何一つ理解できないから「わからない」のであり、わからないから、自分もフォイエルバッハと同じように「さまざまに解釈」しているのである。そして自分自身がフォイエルバッハになり下がっていることにはまったく気がつかない。これはまったくの喜劇(悲劇)である。
この著者は「マルクスは世界を変革せよというが、どう変革するかについては語っていない」という。そんなことをここで語る必要はないのだ。マルクスがここで語る目的は哲学原理であり、深遠な思想原理を「寸鉄人を刺す」短い言葉で語るのが目的であり、その外のくわしい学説は別の場所があるのだ。このようなものごとの分別さえわからないのであろうか。
哲学に関するくわしい学説に関しては『ヘーゲル法哲学批判・序論』(一八四四年)、『ドイツ・イデオロギー』(一八四五年)、『哲学の貧困』(一八四七年)、『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』(一八五一―五二年)、『経済学批判・要綱』(一八五七―五八年)、『経済学批判・序言』(一八五九年)、『経済学批判』(一八六一―六三年)。
そして世界を変革するとはどういうことか、そのためには何が必要か、その戦略・戦術問題については『共産党宣言』(一八四八年)、『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』(一八五一―五二年)、『ドイツにおける革命と反革命』(一八五一―五二年)、『フランスにおける階級闘争』(一八五〇年)、『フランスの内乱』(一八七一年)、『ゴータ綱領批判』(一八七五年)。その他至るところで世界の変革についてマルクスは多く語っているではないか。マルクス主義学者を自認するこれらの諸先生方はいったいマルクスの本を読んでいるのであろうか。マルクス読みのマルクス知らずとはこのことである。
マルクスを読み直そうという目的の代表的出版物のもう一つ『マルクスと哲学』の著者はつぎのように書いている「(この第十一の項は)しばしば<変革の哲学>の宣言として受けとめられてきた。しかしこれはまったくの誤解である。そうではない。哲学とは所詮世界解釈以上のものではない。フォイエルバッハを含めて哲学者たちは結局世界解釈以上のことをやる気はないのだという、哲学および哲学者との決別宣言なのだ。マルクス自身も、後年ブリュッセル期に〝われわれのそれまでの哲学的良心を清算した〟と述懐しているとおりである」と。
ごらんのとおり、この著者は「マルクスのテーゼは変革の哲学宣言と受けとめられてきたが、これはまったくの誤解である」というが、そのことが「まったくの誤解」なのだ。このことについては「第三節」の前文で、エンゲルスが『ルードヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』(一八八六年)の中で、マルクスの『フォイエルバッハにかんするテーゼ』のもつ歴史的意義、綱領的意義、マルクス主義哲学の核心としての意義について論じたこの深遠な思想を理解すればわかることである。まさにこの「テーゼ」は変革の哲学なのだ。だからエンゲルスがマルクスのこのメモ(「テーゼ」)を発見したとき「ここに新しい世界観の天才的な芽ばえがあり、極めて重要な文献である」と言い切ったのであり、だからエンゲルスはこれに「綱領」という名をつけたのである。故にマルクスの哲学は革命の哲学であり、変革の哲学なのだ。マルクスはその第十一の項で、変革の哲学、革命の哲学を強く、決意をこめて、はっきりと主張している。その第十一の項「哲学者たちは世界をさまざまに解釈してきただけである。肝腎なのはそれを変えることである」といっているのである。それはつまり、いろいろ解釈したり、解説したり、評論するだけではだめなのだ。弁証法の法則が示すとおり、物質の運動法則どおりに、物質的な運動、闘い、実践と行動、革命的な行動に身をおくことこそ真の哲学者なのだ、そして自らも革命家たれ、というこのことが第十一の項の内容である。このように、その中身を深く認識できないところにこれらの本の著者たちの浅薄さがある。
われわれ正統マルクス主義者、真のマルクス主義者は、断固としてこの「テーゼ」が説く、マルクス主義的人格、人間像、人間性の獲得を一貫して追求せんことを誓う!
第4節
マルクス主義哲学は「弁証法的唯物論」と「史的唯物論」によって構成されている。エンゲルスとレーニンもはっきり確認しているとおりである。ところが敗北的修正主義はこのことが理解できない。ここにも彼らの浅くて、薄っぺらな(浅薄な)典型がある。反面教師としてここからもわれわれは学ばねばならない!
〈学習のすすめ〉序論で紹介したとおり、最近「マルクスをもう一度読み直そう」として出版されている多くのマルクス本の中身は、驚くほどマルクス読みのマルクス知らずに満ちている。その典型的な一例として、〈学習のすすめ〉第三節(一)(二)(三)で『フォイエルバッハにかんするテーゼ』をとりあげ、くわしく論じておいた。これをみればわかるとおり、敗北的修正主義のマルクス論は、敗北主義であるが故に、徹底した修正主義であり、勝手気ままなマルクス主義の解釈に終始している。
彼らのマルクス論の特徴は、マルクス自身がその『フォイエルバッハにかんするテーゼ』で強く主張しているところの「いろいろと解釈したり、解説したりするのではなく、その問題の本質を深くつかみ、それにもとづいて実践し、行動することである」というこの哲学的思想認識がなく、まさに「いろいろと解釈したり、解説するだけ」なのである。いまここでとりあげる「弁証法的唯物論」と「史的唯物論」の問題も同じであって、マルクスとエンゲルスとレーニンを統一的に認識し、理解し、深く学びとることのできない、浅薄さの典型がここにもある。『マルクスのアクチュアリティ』や『マルクスと哲学』の著者たちがあちこちで、マルクス主義には「弁証法的唯物論」や「史的唯物論」などなどという言葉はない、と書いている。こういうマルクス主義哲学についての無知についてはすでにこの第三節でくわしく論じておいたのでもうあれこれ言う必要はない。そこでここでは、反面教師として、われわれ自身がもう一度この問題について、はっきり、しっかり認識するために、改めてその基礎的なことを明らかにしておきたい。
なおマルクス主義を深く、広く、正確につかむためには、マルクスとあわせてエンゲルスとレーニンを学ばねばならない。エンゲルスは<学習のすすめ>第一節(その生涯)で明らかなように、この二人は生涯を通じて協力と共同と一体であった。だからエンゲルスの言うことはマルクスの言うことである。そしてレーニンは、メンシェビキや、第二インターの修正主義と闘い、マルクス主義を守り通し、実際にロシア革命の勝利によって、マルクス主義を歴史上初めて実現したというこのことによって、歴史がレーニンを第一級のマルクス主義擁護者たらしめたのである。したがって、マルクス、エンゲルス、レーニンを統一的に学ぶことによって、より深く、より広く、より正確にマルクス主義を認識することができる。こうしてこそ浅薄さを克服することができるのである。
さて本論に移る。
弁証法的唯物論について!
まず弁証法とは何か。弁証法とは、古代ギリシャ哲学用語「ディアレクティク」が語源である。その意味は、真理に到達するための唯一の方法は、互いに対立し、異なる双方の考えや、意見や、その矛盾を大いに闘わせ、論争し、双方の矛盾を暴き出し、その中から新たな飛躍と発展にもとづく真理(正当性)に到達させる。そういう思想方法論のことである。こうして以後ヨーロッパの哲学は自然成長性、形而上学、機械論的唯物論などを経てドイツ哲学のヘーゲル(一七七〇―一八三一)弁証法と、フォイエルバッハ(一八〇四―一八七二)の唯物論へ到達した。こうして哲学はマルクスとエンゲルスによって、ヘーゲルの弁証法とフォイエルバッハの唯物論が止揚され、その結果としてのマルクス主義哲学「弁証法的唯物論」として完成したのである。この歴史的経過については<学習のすすめ>第一回、第二回、第三回でくわしく論じたとおりである。この歴史を正しく認識すれば「弁証法的唯物論」がマルクス主義哲学の基本であることがわかる。
つまり、マルクス主義哲学は、十九世紀に到達したドイツ古典哲学の最高峰としてのヘーゲル弁証法と、フォイエルバッハの唯物論を統一させ、この二つにある共通の弱点たる観念論を克服したこと、つまりはこうして弁証法的唯物論が完成したということなのである。そしてこの哲学思想を体系づけて世に出したのが、マルクスとエンゲルスの共著による『ドイツ・イデオロギー』(一八四五年)であった。だから『ドイツ・イデオロギー』をよく読めば、そこにはヘーゲルの弁証法と、フォイエルバッハの唯物論が統一的に、しかも完全に観念論が徹底的に克服されているのが理解できる。だから敗北的マルクス主義者が弁証法的唯物論を否定するのはこの『ドイツ・イデオロギー』が読めないのであり、読んでもわからないのである。
マルクスは『資本論・第二版・後記』(一八七二年)の中でつぎのように書いている。「私の弁証法は根本的にヘーゲルのそれとは違うだけでなく、その正反対である。ヘーゲルにあっては現実、存在とは理念・思考の産物とみる。私のはその反対に、理念・思考とは人間の頭脳に反映・転移された物質的存在なのである」と弁証法に唯物論を結合させている。そしてマルクスは『フォイエルバッハについて』(一八四五年)の中で「フォイエルバッハをふくめた古い唯物論は、あらゆる現象をただ感覚的にとらえるだけで、問題を本質的に、弁証法的運動の歴史上の産物としてみない。そして批判的に、実践的にとらえることができない」と論破している。エンゲルスは『ルードヴィツヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』(一八八六年)の中で、ヘーゲルとフォイエルバッハを批判してつぎのように書いている。「かれは哲学者としてもまた中途半端であって、下半身は唯物論で、上半身は観念論者であった。……われわれは、現実の事物を絶対的概念のあれこれの段階の模写と見ないで、再び唯物論的にわれわれの頭脳のうちにある概念を現実の事物の映像と見た。このことによって弁証法は科学となった。……この弁証法的唯物論はわれわれの最良の道具となり、武器となった」と書き、そして『反デューリング論』(一八七六―八年)の中でつぎのように書いている。「唯物史観は、すべての社会的変化と政治的変化は一生産、交換様式の変化のうちに求められるべきものである」。「歴史の中での諸事件の外観的な偶然性を支配しているのと同じ弁証法的唯物論の法則が、自然においても、無数の変化の紛糾のうちに自己を貫徹している」と。すなわち、一切の現象の中に、偶然性の中に、弁証法的唯物論の必然性が貫徹されている、といっているのである。
「弁証法的唯物論」を体系的に述べたのがエンゲルスの『自然弁証法・序論』(一八七五年)である。この論文の中でエンゲルスはつぎの諸点をくわしく論じている。①大自然と人類社会は永遠の過去から永遠の未来に向かって絶え間なく運動し、発展する物質世界である。②あらゆる物質と運動は相互に関連しており、統一的に、止揚されつつ前進していく。③発展と前進は内部の矛盾と対立物の闘争(内因論)であり、その運動の量的変化が質的な変化を促していく。量から質への転化の法則。④質的転化は根本的で、全面的で、革命的なものであり、故に爆発であり、力が作用する。⑤発展と前進の一段階毎の終結は、常に爆発と収れんであり、破壊と建設であり、対立物の相互転移であり、これが物質運動の法則である。そしてエンゲルスは弁証法の中につぎの有名な言葉で唯物論を説いている。「全自然が、最小のものから最大のものに至るまで、砂粒から太陽に至るまで、原生物から人類に至るまで、一切が永遠の発生と消滅のうちに、絶え間なき流転のうちに、休みなき運動と変化のうちに存在する」と。
そして、だからこそ、レーニンはその著作『マルクス主義の三つの源泉と三つの構成部分』(一九一三年)の中でつぎのように主張した。「マルクスは十八世紀の唯物論にとどまってはいないで、哲学をさらに前進させた。彼はドイツ古典哲学、特にヘーゲルの体系の諸成果によって哲学を豊かにしたのである。そしてこの体系はまたそれとしてフォイエルバッハの唯物論へと導いていったのである。これらの成果の主要なものは弁証法である。すなわち、最も完全な、深い、一面性をまぬがれた形での発展についての学説、永遠に発展していく物質の反映をわれわれにあたえる、人間の知識の相対性についての学説である。自然科学の世界における最新の発見は、マルクスの弁証法的唯物論の正しさを立派に確証した」と。さらにレーニンは『唯物論と経験批判論』(一九〇八年)の中で強く、つぎのように主張した。「マルクスは常に弁証法的唯物論よりも弁証法的唯物論をより多く強調した。そして史的唯物論よりも史的唯物論をずっと強く主張した」と。まさにマルクス主義哲学とは「弁証法的唯物論」と「史的唯物論」なのである。このことをはっきりと確認しよう。
第5節
史的唯物論について
〈学習のすすめ〉序論の前文で紹介した「マルクスをもう一度読み直そう」という目的で出版されたマルクス本の中の一冊『マルクスと哲学―方法としてのマルクス再読―』の著者(マルクス主義哲学者)は、その大作の「まえがき」の中で、はっきりと次のように書いている。「マルクスと哲学、という本書のタイトルを見た読者はおそらく、弁証法的唯物論、や、史的唯物論、あるいは、唯物論的歴史観、などといった言葉を思い起こされたことだろう。では、マルクスは、弁証法的唯物論、とか、史的唯物論、唯物論的歴史観、などといった言葉を、一度も使っていない、と申し上げると、たいへん驚かれるのではないだろうか。……マルクスは弁証法的唯物論などとは(史的唯物論とか、唯物論的歴史観とも)一言も言っていないのである。そもそもマルクスは、自分の哲学的見解として、何かを論じたのではない」と。
右のこの一文を見ただけで、この著者もふくめた多くのマルクス主義学者が、如何にマルクス主義を知らず、理解できず、まさにマルクス読みのマルクス知らずであるかがわかる。ここに、われわれがはじめから指摘しているとおり、ソ連や東欧の社会主義崩壊を敗北主義的に受けとめた結果としての、思想上の敗北主義が生み出した現代の「敗北的修正主義」がある。それはつまり勝手気ままなマルクス主義論であり、修正し、ねじ曲げたマルクス論なのである。敗北的修正主義の本質については〈学習のすすめ〉第二節で詳しく論じたとおりである。したがって、今さらここでくどくどと論ずる必要はない。ただわれわれはこれを反面教師として、マルクス主義哲学の根本理論を、改めてわれわれ自身が再確認したいのである。
マルクスとエンゲルスは、二人の共著『ドイツ・イデオロギー』(一八四五年)で、はっきりと、明確に「弁証法的唯物論」と、「史的唯物論」を展開している。これがわからないようではマルクス主義者たりえないであろう!
史的唯物論とは、弁証法的唯物論という哲学科学思想によって世界と人類の歴史をみつめ、とらえ、判断し、解明するという科学的歴史観のことであり、実践と行動のための思想原理である。このことを、エンゲルスがいろいろなところで言っているように「唯物史観」ともいう。そしてマルクスとエンゲルスが歴史上はじめて、理論的に、体系的に、歴史的にこの史的唯物論を世界に向かって展開したのが『ドイツ・イデオロギー』であった。このことについてエンゲルスは後ではっきりと定式化している(あとで詳しく紹介するように『反デューリング論』、『経済学批判・序論』で)。この『ドイツ・イデオロギー』の中でマルクス・エンゲルスは次のことを強く主張している。「人間は歴史を作る。しかしその歴史創造の大前提はまず生きることであり、そのためには何をおいてもまず食わねばならない。そして衣と住も必要である。原始時代はそのすべてを大自然から獲得していた。やがて生産することをおぼえ、生産力は人間の生きる要求から発展し、前進していった。生産力の発展(道具や機械の発達)によって、それに応じて、生産関係(分配と処分のための機構としての国家と社会構造)が変化し、発展していった。こうして人間の歴史の変化と発展の土台には生産力と生産関係が存在しつづける。人類の歴史全体を貫くのは生産力と生産関係である。そして生産力は無限に発展、前進していくが故に、生産関係と人間の歴史もまた無限に発展し、前進していく。この歴史観、つまり「史的唯物論」が『ドイツ・イデオロギー』の中で詳しく展開されている。それを整理、まとめると次のようになる。
(1)生産力こそが人類社会発展のエネルギー(力)である。
人間は生きるために食わねばならない。そのために生産活動がある。生産活動は労働力(人間の労働能力)と生産手段(道具、機械、土地、建物、原料)が結びついて可能となる。この二つの側面のうち労働力こそが決定的要因であり、これは人間の生きるためのエネルギーがその力の源泉になっている。そしてこのエネルギー(生きる意欲)によって生産力は常に向上、発展、前進、成長という特質をもっている。この生産力は必然的に社会的性格を帯びざるを得ない。なぜなら、生産力はそれに携わる人びとの協力と共同と連携という社会性なしには成立しないし、生産目的もまた多くの人びとと社会のためという社会的な性格を高めるからである。
(2)生産力と生産関係という総体が現実の土台であって、そのうえに人間の思想・意識が上部構造として成立していく。
故に唯物論哲学の示すとおり、存在が意識を決定していく。そしてその存在としての生産力と生産関係は常に変化・発展・成長していくのである限り、上部構造としての人間の思想意識も変化・発展・成長していく。生産力と生産関係はその運動の過程では互いに矛盾する関係である。なぜなら、生産力の発展はますます社会的になる(人間関係も、生産目的も)にもかかわらず、所有と分配を支配するのは生産手段と生産物を占有する一部の階級(人間の集団)によって左右されていくからである。ここから生産物(富)をめぐる分裂と対立、紛争と抗争、つまり階級対立と階級闘争が発生する。その反映としての思想と意識、理念と理論、イデオロギーの分野にも対立と抗争が激しくなる。
(3)生産力の発展と向上と成長は必然的に生産関係をそれに合致させるよう促し、それに照応させていく。
生産力の発展と向上は人間関係をいよいよ社会化させる。人びとの協力、共同、連携は必然となり、生産目的もまた広く社会的目的を帯びていく。したがって生産力の発展と向上は現存する生産関係(人間相互の関係、生産物の支配と分配を支配する国家と社会構造)と矛盾していく。ここから経済上、政治上の矛盾(分裂、対立、抗争)が生まれる。階級対立と階級闘争である。この矛盾を解決するには生産力の発展に合致した生産関係(国家と社会構造)にする以外にはない。歴史の発展法則はこのことを求めて激動する。そして最後は爆発と収れん(革命)によってこれは達成される。
(4)生産力の成長発展は自然発生的であるが、生産関係の成長発展(変革)は爆発と収れんである。
生産力の発展、前進、成長は自然発生的である。それは人間の労働能力は学習と経験の積み重ねであり、生産手段の発達と向上も研究と改良の積み重ねであるからである。それに比べて、生産関係(人と人の相互関係、国家と社会制度)の変革は、人間の感情、思想意識が介在しており、人間の感情と思想・意識による対立と抗争は激烈が必然的とならざるを得ない。こうして人類の歴史は、その転換期に必ず暴力、戦争、内乱が付きまとう。人類社会の発展、前進、転換は爆発と収れんである。
(5)生産力の発展に伴う生産関係(国家と社会)の変化、転換、そのときの爆発と収れんは思想的理論的核としての前衛の存在とその力が決定的に作用する。
生産関係の変更は革命的転換である。人類の歴史(原始制社会―奴隷制社会―封建制社会―資本主義社会―独占と帝国主義時代―社会主義社会)はみなこのように、生産力の発展に伴う生産関係の変化という法則の結果である。そしてよく理解しなければならないのは、歴史上の国家と社会制度の変化と発展は常に爆発と収れん(戦争と暴力、革命的手段と方法)であったということである。それは自然科学の世界では核爆発であり、社会科学の世界では核としての前衛と、それに結合した大衆の力(闘争)である。それは歴史が示しているとおり科学的必然性をもって展開されていく。
マルクスと一心同体であったエンゲルス、マルクス主義の最大擁護者として歴史が証明したレーニンは、はっきりと、明確に「弁証法的唯物論」と「史的唯物論」をその哲学用語として確認している。エンゲルスとレーニンの文献をよく読め!
オイゲン・デューリング(一八三三―一九二一)はドイツにおける有名な哲学者であり、経済学者で、一八六三―七七年にかけてはベルリン大学の講師を勤めた。彼はマルクスの学説に反対する独自の哲学・社会主義論を展開した。それは革命ではなくて改良であり、階級闘争ではなく資本と労働の協調による社会改革をとなえた。これはドイツ労働運動に一定の動揺をあたえ、『ゴータ綱領批判』(マルクス、一八七五年)を生み出した事件、革命的アイゼナッハ派と改良的ラッサール派の妥協による合同(ゴータ合同大会)を引き起こしたのである。マルクスとエンゲルスは黙っているわけにはいかなくなり、二人は共同してデューリング批判を展開した。その内容は哲学、経済学、社会主義に至る広範囲にわたり、ドイツ社会民主党(共産党の前身)の機関紙に、一八七七年から七八年にかけて連続して発表された。それが一八七八年八月に『オイゲン・デューリング氏の科学の変革』と題した一冊の本となった。これがエンゲルスの『反デューリング論』である。そしてその内容からみて、これは『共産党宣言』、『資本論』と並ぶ基本文献と位置づけられた。
ところでエンゲルスはこの論文を書くとき『共産党宣言』の場合と同じように、常にマルクスと相談し、協力して書いた。とくに経済学の部分についてはマルクス自身が筆を執った。だからその内容はまさに、マルクスとエンゲルスの共同の意思なのである。そして、その中の社会主義に関する理論上の問題と実践的課題の部分を、多くの社会主義運動家の求めに応じて、別の小冊子として出版されたのが『空想から科学への社会主義の発展』(一八八〇年)である。エンゲルスはこの本の中で、第一に労働者階級と人民は革命運動を通じて何よりも権力を獲得しなければならない。すべては権力が決定すること。第二は労働者階級と人民は権力を運用し、執行することを通じて国家と社会を労働者階級と人民のものに変革する。第三は資本主義とは利益追求だけの盲目的無政府主義である。社会主義は社会的要求と人民の要求を満たすための計画的経済である。第四は生産力の向上と発展に応じて、肉体労働と知的労働の差、工業と農業の差、都市と農村の差が解消されたとき、社会主義は共産主義に成長転化する。第五に、人類社会は生産力の発展の帰結として共産主義に到達したとき、階級社会は消滅し、必然の結果として国家は消滅する。国家は「廃止される」のではなく「死滅する」のである。以上のことをマルクスとエンゲルスは詳しく論じているが、これが唯物史観、つまりは史的唯物論なのである。
この本の中でエンゲルスは(マルクスと共に)徹底してその哲学、つまり弁証法的唯物論を説き、唯物史観(唯物論的歴史観)を説き、そして史的唯物論を説いている。敗北的修正主義者たちがどんなに泣きわめいても、マルクスとエンゲルスはこの本の中で、はっきりと弁証法的唯物論と唯物史観と史的唯物論を説いている。そしてエンゲルスは次のとおり、明確に主張している。この本の一八八二年に書いた第一版の序文では「唯物史観の、プロレタリアートとブルジョアジーのあいだの現代の階級闘争への適用は、ただ弁証法によってのみ可能であった」(唯物論と弁証法は結合してのみ、つまりは弁証法的唯物論としてのみ階級闘争の世界に通用するのである)と書いている。また本論の(二)の項では「現代の唯物論は本質的には弁証法的である」と書いている。そしてエンゲルスは一八九二年に書いた『英語版への特別の序文』の中で次のように書いている。「この本はわれわれが史的唯物論と呼んでいるものを擁護している。私が史的唯物論という用語を使っても、イギリスのお上品な人びとがあまりひどく衝撃を受けないよう希望する」と。エンゲルスはマルクスの同意のもとで書いた論文のいたるところで、弁証法的唯物論、唯物史観、史的唯物論という言葉をはっきりと使っているのである。
だからレーニンはマルクス主義哲学の原理を守り通して反マルクス主義と徹底的に闘った。ロシアにおける哲学と経済学会の重鎮で、哲学の世界にプラグマティズムを持ち込んでレーニンと対立したボグダーノフ(一八七三―一九二八)に向かってレーニンはその名著『唯物論と経験批判論』(一九〇八年)の中で次のように言っている。「この人たちはみな、マルクスやエンゲルスが何十回となく自分の哲学的見解を弁証法的唯物論と呼んだことを知らないはずがない」(つまり、マルクスやエンゲルスはその哲学を弁証法的唯物論だと言っていることをみな知っているはずだ。マルクス主義哲学とは弁証法的唯物論なのだ)と。そしてレーニンはつづけて次のことを強く主張している。「マルクスとエンゲルスは一貫して、すべては運動する物質であるという原理から、弁証法的唯物論よりも、弁証法的唯物論をより多く強調した。そして史的唯物論よりも史的唯物論をずっと強く主張した」(同上)と。このようにエンゲルスとレーニンは弁証法的唯物論と史的唯物論こそマルクス主義哲学の根本だということをいたるところで主張しているのである。
「史的唯物論」を定式化したマルクスの『経済学批判・序言』
マルクスは大著『資本論』のための準備として『経済学批判』のための『序論』を一八五九年に執筆したが、エンゲルスにその書評を書くように頼んだ。エンゲルスは喜んで執筆した。この文書『カール・マルクスの経済学批判・書評』(一八五九年)でエンゲルスは次のように書いている。「この本は根本において唯物史観にもとづいており、この史観、史的唯物論の要綱はその序文のうちに簡潔に述べられている」と。この一文こそ、エンゲルスが規定したマルクス主義の「史的唯物論」の定式化である。その全文は次のとおりである〈次が大月書店発刊(一九六四年)大内兵衛、細川嘉六監訳『マルクス=エンゲルス全集第13巻『経済学批判・序言』の中の一節の全文である〉
『人間は、彼らの生活の社会的生産において、一定の、必然的な、彼らの意志から独立した諸関係に、すなわち、彼らの物質的生産諸力の一定の発展段階に対応する生産諸関係にはいる。
これらの生産諸関係の総体は、社会の経済的構造を形成する。これが実在的土台であり、その上に一つの法律的および政治的上部構造がそびえ立ち、そしてそれに一定の社会的諸意識形態が対応する。
物質的生産の生産様式が、社会的、政治的および精神的生活過程一般を制約する。人間の意識が彼らの存在を規定するのではなく、彼らの社会的存在が彼らの意識を規定するのである。
社会の物質的生産諸力は、その発展のある段階で、それらがそれまでその内部で運動してきた既存の生産諸関係と、あるいはそれの法律的表現にすぎないものである所有諸関係と矛盾するようになる。これらの諸関係は、生産諸力の発展諸形態からその桎梏に一変する。そのときに社会革命の時期が始まる。経済的基礎の変化とともに、巨大な上部構造全体が、あるいは徐々に、あるいは急激にくつがえる。
このような諸変革の考察にあたっては、経済的生産諸条件における物質的な、自然科学的に正確に確認できる変革と、それで人間がこの衝突を意識するようになり、これとたたかって決着をつけるところの法律的な、政治的な、宗教的な、芸術的または哲学的な諸形態、簡単にいえばイデオロギー諸形態とをつねに区別しなければならない。ある個人がなんであるかをその個人が自分自身をなんと考えているかによって判断しないのと同様に、このような変革の時期の意識から判断することはできないのであって、むしろこの意識を物質的生活の諸矛盾から、社会的生産諸力と生産諸関係とのあいだに現存する衝突から説明しなければならない。
一つの社会構成は、それが生産諸力にとって十分の余地をもち、この生産諸力がすべて発展しきるまでは、けっして没落するものではなく、新しい、さらに高度の生産諸関係は、その物質的存在条件が古い社会自体の胎内で孵化されてしまうまでは、けっして古いものにとって代わることはない。それだから、人間はつねに、自分が解決しうる課題だけを自分に提起する。なぜならば、もっと詳しく考察してみると、課題そのものは、その解決の物質的諸条件がすでに存在しているか、またはすくなくとも生まれつつある場合にだけ発生することが、つねに見られるであろうからだ。
大づかみにいって、アジア的、古代的、封建的および近代ブルジョア的生産様式が経済的社会構成のあいつぐ諸時期として表示されうる。ブルジョア的生産諸関係は、社会的生産過程の最後の敵対的形態である。敵対的というのは、個人的敵対という意味ではなく、諸個人の社会的生活諸条件から生じてくる敵対という意味である。しかしブルジョア社会の胎内で発展しつつある生産諸力は、同時にこの敵対の解決のための物質的諸条件をもつくりだす。したがってこの社会構成でもって人間社会の前史は終わる』
第4章
経済学とは何か。経済学の根本原則をしっかりと学べ!
経済とは「経国済民」という古来中国の歴史書からきた言葉である。「経国」とは国を治めることであり、「済民」とは民(人民)を救うという意味である。つまり経済とは国家と社会、国民と人民の生活と安全を維持し守るという意味である。そして「経済学」(エコノミクス)はギリシャ語の「エコノミヤ」と「エコス」(家、家政)と「ノモス」(法則)から生まれた言葉である。
エンゲルスの名で一八七八年に出版された『反デューリング論』ではその第二節・経済学の部でつぎのように述べられている。「経済学は、もっとも広い意味では、人間社会における物質的生活財の生産と交換とを支配する諸法則についての科学である。……そして経済学は、本質的には歴史科学なのである。経済学は、ある歴史的な、絶えず変化する材料を取り扱う。つまり、それは、まずはじめに、生産と交換という、個々の発展段階がもつ特別な諸法則を研究し、それから、この研究の終わりにいたってはじめて、生産と交換一般にあてはまる、普遍的な諸法則をうち立てる」と。まさに経済学は社会科学であり、歴史科学であり、人類の歴史の経済法則についての研究なのである。
この根本思想と哲学原理が経済学を論ずる場合の大前提でなければならない。これがないと、結果としてその経済学は、非科学的・非歴史的・空想的・机と紙と数字の上の観念論に終わる。
さて、経済学という学説、理論が体系的に成立したのは十八世紀のイギリスであった。アダム・スミス(一七二三―一七九〇)による古典経済学の完成であり、彼はその創始者となった。
ところで、なぜイギリスがその発祥の地となったのか。それはイギリスが十八世紀における世界資本主義、独占資本主義の総本山だったからである。そういう土台があった。ではイギリスがどうして世界資本主義の総本山になりえたのか。それはまずこの国のおかれた客観的条件としての地政学上から見なければならない。海に囲まれたこの国は、ヨーロッパ大陸のように、国境をめぐる大規模な対立と抗争と戦争は比較的に少なかった。その結果として国土の荒廃と破壊、人的資源のそう失、などの被害も大陸に比べて少なかった。そしてまた島国であったため海外への雄飛、商業と貿易への熱意も高く、そのため商品経済(商業)はどこよりも早く発達した。一七七〇年代(十八世紀後半)から開始された全産業にわたる技術改革(産業革命)は、イギリス資本主義を一変させた。まず綿織物工場の機械化、そして動力源たる蒸気機関の発明、やがて鉄道と蒸気船へと進み、イギリスは世界の大工場となった。
産業革命、機械化、大工場生産はまさに大量生産時代の到来であり、市場の独占化であり、大量の商品の販路を求める帝国主義への指向である。同時に国内においては財産の蓄積であり、物質的財貨とともに知的財産も豊かになる。学問、芸術、そして知識人も豊富になった。こうした歴史的条件とその存在がアダム・スミスとその頭脳を生み出したのである。イギリス古典経済学とは、イギリス資本主義、イギリス独占資本主義の理論上、思想上の体現であり、そのための学説であり、アダム・スミスはその代表者である。イギリス資本主義、独占資本主義が産業活動という実践と行動で到達した結論に、アダム・スミスの頭脳が(学者として)理論的に、思想的に到達した学説である。故に古典経済学とは、資本主義、独占資本主義、帝国主義のための経済学であり、そのための思想原理であり、近代資本主義・独占資本・帝国主義の道しるべであり、その指針・羅針盤である。そしてよく認識しなければならないのは、資本主義経済学、ブルジョア経済学の諸派(学派)はたくさんあるが、そしてそれぞれ独自の学説を展開しているように見えるが、本質的にスミスの思想と理論を原本にしているのであって、根本においてはすべてスミスであることを知らねばならない。
第1節
アダム・スミスと古典経済学の歴史上の位置、その形而上学的・観念論的本質について!
(1)
アダム・スミスはイギリスのスコットランドに生まれた。彼は幼くして父を失い、母一人に育てられた。兄弟もなく、生涯を独身で通し、ひたすら学問に身を投じた。グラスゴー大学、オックスフォード大学に学び、最後はグラスゴー大学の総長になった。多くの学説を発表したが、一七七六年に刊行した『国富論』(原書名『諸国民の富の性質と原因に関する研究』)がその代表的著作になった。これが古典経済学の原書であり、資本主義経済学(ブルジョア経済学)の教典である。
スミスとその古典経済学の理論上、思想上の原理はつぎの点にある。(一)この世の富と財産を作り出すのは人間の労働であり、それは人間の欲望から生まれる。故にその欲望を抑圧してはならず、欲望の自由・放任こそ経済活動の土台である。(二)そのための基礎的条件は自由であること、自由競争であること、市場原理である。(三)自由競争から派生する否定的現象である個人主義、排他性、非道徳などは、市場における人間相互の関係と交流から生まれる相互の感情と道徳と理性(という見えざる神の手)によって自然淘汰(とうた)され、克服される、というものである。
スミスのこの『国富論』はその以前(一七五九年)に執筆された『道徳感情論』が背景にある。この文書を執筆した時代にスミスはグラスゴー大学の論理学・哲学教授として、「人間道徳論」を講義していた。この『道徳感情論』で展開されているその哲学思想の根幹はつぎの点にある。つまり、人間は欲望によって働く。だから人間の欲望は自由放任でなければならない。自由から創意工夫が生まれる。しかし反面その自由放任は個人主義や、野心や、虚栄心や、非道徳、規律違反なども生み出す。しかしこれらは強制ではなく、市場における人間相互の交流から必然的に生まれる道徳的感情による自立的規範によってのみ淘汰される。このような「見えざる神の手」によってはじめて、本当の調和と秩序は生まれる。自由と平等の世界は市場から生まれる。これがスミスの説く『道徳感情論』である。
だが、スミスのこの哲学・経済学は、まったくの形而上学(机と紙と数字の上の固定的形式主義)、観念論(事実、歴史、実際、現実、行動と実践から離れた空論、空想)であることははっきりしている。資本主義と独占支配の世界はまさに戦争と殺りく、暴力と犯罪、欲望のままの世界であり「見えざる神の手」など一つもなかった。
(2)
アダム・スミスの『国富論』の背景にある『道徳感情論』、そして資本主義的ブルジョア経済学の根本思想は「人間欲望の自由放任」であり、自由主義こそが経済繁栄の基礎であり、統制と保護は発展を阻害する、というものである。だから今も最近『自由をいかに守るか、ハイエクを読み直す』(渡部昇一著、PHPビジネス新書)という本が自由、自己流、自分勝手、を謳(おう)歌する。その一方では『欲望資本主義に憑かれた男たち、モラルなき利益至上主義に蝕まれる日本』(伊藤博敏著、講談社刊)の中で、堀江貴文や村上世彰など、拝金主義にまみれた経済犯罪人をとりあげ、欲望の泥沼社会を告発する声も高い。
まさにこの問題こそ経済学の根底にある根本的思想問題なのである。この問題は観念論では解決できない。歴史科学以外に解答はできない。つまり、欲望とは人間のことであり、人間とは何かということであり、それは人間の歴史、人類の歴史をたどることによってのみ答えは出てくる。欲望とは人間のことであり、人間とは歴史が生み出したものであり、故に人間の欲望は常に歴史的なもの、永遠の過去から永遠の未来に向かって変化し、発展し、転化していくものである。欲望は固定したものではなく、歴史と環境によって変化し、転化していくものである。
人類、人間は動物(猿)から分化して進化した。気の遠くなるような長い年月を経て、その姿、形、機能も進化し、発展し、変化してきた。特にその脳は人間だけが保有するその機能によって発達してきた。そしてその脳が生み出す欲望、感情、感覚、知能は決定的に変化していった。人間とその脳はすべて環境の産物であり、環境によってすべて作り出されてきた。そしてまた人間とその脳はその知的能力によって逆に環境を支配していく。それは人類の歴史をみればすぐわかることである。
スミスとブルジョア経済学、渡部昇一とブルジョア自由主義者たちは科学を知らず、人間とは何かを知らず、人類の歴史も知らず、形而上学と観念論の世界におぼれた空想家であって、歴史的にはやがて消滅していく現代のソクラテスである。
(3)
人類の歴史が証明しているように、人間の欲望と道徳感情というものは常に環境によって変化してきた。人類が最初に作り出した生活集団、その社会とは古代から原始にかけて存在したコミュニティーとしての原始共同体社会であった。そこではまだ生きるための欲望たる食も、住も、衣も生産することができないため、すべては大自然に依存していた。つまり、食、住、衣は生産ではなく、大自然からの採集であり、山野からの狩猟であり、河川からの漁労であった。しかも道具類はまだ発明できなかった時代、すべては人間の体、手足が道具となった。これで大自然の猛威と、各種の障害にたちむかっていくためには、人間の集団による一体としての協力と共同と連帯を必要とした。歴史時代とそのような環境が協力と共同と連帯の社会を作った。だからここでは獲得も所有も分配も社会的共有であり、社会的道徳感情論であった。だからそこには支配も、被支配もなく、真の自由と平等の世界があった。対立と抗争と戦争も必要なかった。平和な社会であったということは、歴史学者、人類学者、日本の考古学会の定説でも、縄文時代(原始時代)は平和な時代であったことを証言している。
このような社会が崩壊し、社会的道徳感情がなくなり、支配者と被支配者の対立と抗争、戦争と内乱、犯罪と暴力が出現したのは、生産活動が発達して世の中に富と財産が生まれてからである。人類は大自然からの採集経済から、生産活動、物質生産の時代に移行した。知恵と知能の発達、道具の発明と改良も進み、生産力も高まった。その結果余剰生産物(備蓄)が生まれ、それが財産となった。当初これはコミュニティーの共同管理、共同所有であった。しかしそれが増加するにつれ、やがて力(知能、才覚、腕力)の強い人間とその集団が、自らの本能的欲望自由放任によって自分のものにした。私有化、私有財産が生まれた。彼らは力まかせに、大自然が生み出した人類社会のものである土地や山まで「これもおれのものだ」とばかりに占有し、私物化してしまった。そしてこの自らの所有、私有財産を守るために権力機関、支配機関(国家)を作り上げた。人類の最初の国家、古代奴隷制国家(古代ギリシアの都市国家、古代ローマ帝国)が強大になった代表例である。つまり、生産力の発展が生産関係(人間の相互関係、階級社会、権力と国家)を作り上げたのである。これが科学的にみた経済法則であり、史的唯物論なのである。
こうした歴史時代が、こうした環境が、人間の道徳感情論を変化させ、人類社会に富と財産をめぐる争奪戦たる階級社会と階級闘争の人間道徳論を生み出したのである。すべては歴史と環境が欲望を変化させ、転換させ、その思想・意識が世界を支配していった。つまりは環境が人間を作り、人間が環境を支配していったのである。
原始共同体が崩壊したあとの社会は奴隷制社会である。ヨーロッパでは古代ギリシャの古代都市国家(ポリスとしてのアテネ、スパルタ)、そして古代ローマ帝国であり、日本では弥生時代である。そしてこの時代から人類史上に戦争と内乱、対立と抗争、暴力と犯罪が日常化していった。奴隷制から封建制、資本主義から現代の独占と帝国主義へ、原始共同体が解体された以降、人類社会に戦争のない時代は一度もない。このような対立と抗争、暴力と犯罪、戦争と内乱の原因はみな、経済問題である。つまりは富と財産、土地と領土、金(カネ)をめぐる争いなのであり、根底には人間の欲望の自由放任がある。そこには「見えざる神の手」などひとつもない。まさに「欲望資本主義に?かれた人間たち」の世界なのである。スミスと自由主義、そのブルジョア経済学、歴史上のすべての宗教も、原始共同体社会が崩壊したあとの人間の歴史を貫く富と財産と土地と領土をめぐる対立と抗争、戦争と内乱、暴力と犯罪を何一つ解決できなかった。「見えざる神の手」などは空想の世界の幻影に過ぎない。永遠の過去から永遠の未来に向かって絶えず運動し、発展し、前進し、転換していく人類の歴史が必ず近い将来この問題をきっぱりと解決するであろう。その時代はもう近い。なぜなら人類の歴史は、原始共同体―奴隷制―封建制―資本主義―独占と帝国主義へと、前へ前へと進んできたからには、ここで止まっているわけではなく、つぎの新しい時代へ進む以外にない。それは、大衆的社会・人民の時代、高度に発達した近代的コミュニティーの時代である。それを導く羅針盤こそ、科学的経済学・マルクス主義経済学である。
第2節
歴史科学、社会科学としてのマルクス主義経済学について!
十九世紀の世界に近代労働者階級が巨大な勢力として歴史の舞台に登場した。近代資本主義の発展はそれに対応して働く人びと、労働者を大量に生み出す。彼らは労働という実践と経験の中から現実の矛盾に突き当たる。この階級的矛盾とその矛盾からの脱出を求めて運動と闘いに決起する。そのとき、同時に、これと併行して、マルクスの頭脳が(その頭脳労働が)労働者階級の運動と闘いへの灯台・羅針盤としての思想と理論を生み出した。これがマルクス主義である。その歴史的経過は〈学習のすすめ〉第一回でくわしく紹介したとおりである。そしてその中の経済学の分野は『資本論』(一八六七年)に代表される。
だがここでよく知らねばならないことは、マルクスはその大著『資本論』に到達するまで、多くの頭脳を使って予備的著作を発表している。むしろ『資本論』を正しく理解するためにこそ、この予備的著作をよく読まねばならない。その著作とは『ヘーゲル法哲学批判』(一八四三―四四)、『聖家族』(一八四四)、『独仏年誌』(一八四四)、『ドイツ・イデオロギー』(一八四五)、『経済学批判・要綱』(一八五七―八)、『経済学批判・序言』(一八五九)、『経済学批判』(一八六一―三)、こうして『資本論』に到達した。そしてさらにその補完的著作としての『反デューリング論』(一八七八)、『空想から科学への社会主義の発展』(一八八二)、などエンゲルスの著作がある。
そして重要なのは、マルクスの著作『経済学批判についての書評』(一八五九年に執筆したエンゲルスの一文)にあるつぎの言葉である。「マルクスの経済学は本質的に唯物論的歴史観(史的唯物論)にもとづいている。この歴史観の要点は、マルクスの『経済学批判・序言』のなかで簡潔にのべられている」というこの一言である。
エンゲルスのこの言葉をよくかみしめて理解しなければならない。つまり、マルクス主義経済学(経済学一般に共通する学問)の根幹は『史的唯物論』(人間の生活と生きたその歴史)でなければならない、ということである。その核心を一言で言えば「人間が生きるための力、その生産力の発展が、人間の相互関係、国家と社会制度を変化させていく」という科学的法則である。経済学とは『史的唯物論』にもとづく人間の歴史、その経済史でなければならない。その基本的概略はつぎのとおりである。
(註・『史的唯物論』を定式化したマルクスの『経済学批判・序言』の中の有名な一節は〈学習のすすめ〉第三節・五の項で全文が紹介されている)
(1)、生産力がなく、したがって生産活動もなかった人類最初の社会は、すべてが大自然を相手にした共同採集経済であり、それを土台にした共同体・コミュニティー社会、社会的人間道徳の世界であった!
マルクスは前記『史的唯物論』の最初の書き出しでつぎのように言う。「人間は、彼らの生活の社会的生産において、一定の、必然的な、彼らの意志とは関係なく、独立した諸関係に、すなわち、彼らの物質的生産諸力の一定の発展段階に対応する生産諸関係にはいる」と。つまり、人間は人間としてはじめて存在したそのとき、目の前にある、自然的条件が提供した生活(経済的条件)に遭遇するのである。だから経済学はここから出発しなければならない。
だからマルクスとエンゲルスは共同で執筆した『ドイツ・イデオロギー』(一八四五―六年)の中でつぎのように言う。「われわれはあらゆる人間的な存在の、したがってまたあらゆる歴史の第一の前提、すなわち人間たちは歴史を作り出すために生きることができなければならないという前提を確認することからはじめなければならない。ところで、生きるためには何をさておき、食、飲、住、衣、その他のことがなくてはならない。したがって最初の歴史的行為はこれらの必要な充足のための諸手段の産出、物質的生活そのものの産出であり、しかもこれは、今日もなお何千年前と同じように、人間たちをただ生かせておくだけのために、日々刻々、果たさねばならない一つの歴史的行為であり、あらゆる歴史の根本的条件である」と。つまり人間はまず食わねば生きていけないのだから、経済学とはいかにして食うのか、ということから出発しなければならない、という。
さて、生きるためには食、衣、住を生産しなければならない。生産活動のためには生産力(生産する力)がなければならない。生産力とは何かについて、マルクスは『資本論』第二巻、第一章、第二節ではつぎのように書いている。「生産の社会的形態がどうあろうと、労働力と生産手段とはいつでも生産要因である。およそ生産がおこなわれるためには、この両方(この二つ)が結合していなければならない。この結合が実現される特殊な段階は、そのことによって時代の社会的構造、その経済上の時代を区別していく」と。
つまり、経済活動、生産活動、物を生産するためには労働力(人間の働く力、能力、エネルギー)と、生産手段(道具類、機械類、土地、建物、交通機関)という、この二つが結合しなければならない、ということである。そして重要なことは、この「生産力」の度合い(発展段階)が、その時代の歴史的段階(生産関係、国家と社会制度)を性格づける、ということなのである。マルクスのこの短い一文をよく理解し、認識しなければならない。これが出発点である。
では人類は地球上に出現した当初、生きるためにどのようにして食、飲、衣、住を手にしていたのであろうか。このことについてマルクスは『経済学批判・要綱』(一八五七―八)のなかでつぎの諸点を明らかにしている。
「原初の生産的条件は、それ自体は生産されたものではありえない。つまり生産の結果ではない。自然と人間の物質代謝の自然的条件と、生きて活動する人間とが、一体をなしている姿は説明を要することでもない」
「労働の主な客観的条件はそれ自体労働の生産物として現れるのではなく、自然として見い出される。彼の活動に前提されているのは、ちょうど彼が生きていくプロセスで、彼の皮膚や感覚器官を前提としているのと同じようなものである」
「生産の原初的条件には、果実、動物などのように、生産的労働せずとも、直接消費できる素材が自然に含まれていたのである」と。つまり、人類が人間として存在するに至った原初、その原始時代には、生産活動はなかった。道具類や機械類はまだ発明されておらず、せいぜい大自然から得た石器類や、木材が使われていた。つまり生産力はなかった。この生産力の未発達という条件が、原始時代の生産関係(人間の相互関係、国家と社会制度)を規定していった(生産力が生産関係を規定した)のである。
このことについてマルクスとエンゲルスは『ドイツ・イデオロギー』の中でつぎのように言っている。「人類の原初、最初の所有形態は部族の共同所有である。これは人びとが狩猟と漁労で、牧畜で、あるいはせいぜいのところ農耕で食っているような生産の未発達な段階に対応する」と。
このことについて日本では小学館発行の『日本大百科全書』のなかの縄文時代(原始時代)について、つぎのように記述している。「当時まだ国家というものは成立しておらず、部族社会が中心で、狩猟、採集、漁労にもとづく獲得経済であった」。「縄文時代の生業は狩猟、漁労、木の実類など採集中心の経済で、人びとは自然の産物に生活をゆだねていた」と。これは日本考古学界の定説「縄文時代は国家も権力もなく、共同体社会で、戦争もない平和な社会であった」というのと完全に一致している。
ここに歴史科学があり、史的唯物論がある。このように歴史を科学として見なければならない。つまり、生産力の発達条件、生産力の発展段階が、生産関係としての社会制度を作りあげているのである。原始時代の生産力の状況が、原始的社会制度、原始共同体社会、社会的人間道徳の世界を作り出していたのである。
(2)、生産力の成長と発展による生産活動の飛躍は余剰生産物(備蓄)を生み、財産となる。そこに個人的欲望にもとづく財産をめぐる争い、対立と抗争、戦争と内乱が発生、権力機関としての国家が成立。生産力の発展が生産関係を変化させる第一歩がはじまった!
宇宙と全世界は常に運動している。人類の世界もまた常に運動し、前進する。人口は増大し、知能も発達する。そして経済活動の分野では土地の開拓、灌漑施設の創設、穀物の耕作、農耕栽培、動物の育成が進んでいく。そして、そのために必要な用具類の開発、改良、発明と発見が進み、生産手段は石器、木材から青銅と金属器具の時代へと移行する。つまり、人間の労働力(知能とエネルギー)と、生産手段(道具、機械、土地改良、灌漑という交通)が発達した。生産力の向上である。その結果、生産物は増大し、備蓄は増え、これが余剰生産物となり、財産となる。もちろんこれはコミュニティーのものであり、共同体社会のものであった。しかし人間の本能(動物的本能)にもとづく個人的欲望の強い人間とその集団による力(知能、才覚、実力)によってこの財産は占有・私物化されてしまった。大自然が作り出した社会のものである土地や山までも占有・私物化されてしまった。原始共同体社会を支配していた協力と共同と社会的人間道徳は消滅し、かわりに出現したのは動物的本能と個人的欲望むき出しの「人間道徳論」の世界である。この欲望の世界が、この制度と社会が富と財産の争奪の手段としての戦争と内乱、犯罪をひきおこしていったのである。富と財産を支配し、維持するための手段と制度としての権力、国家、社会制度を生み出していった。その最初の国家が古代奴隷制国家である。
人類最初の階級社会は奴隷制社会である。そこにおける階級関係は、一切の生産物を財産として占有し、土地も、山も、そして個々の人間も、すべてを私有物として占有・支配する奴隷所有者(皇帝、国王、貴族)が権力者として存在する。一方では一切の財産、生産物、生産手段を所有できず、ここから切り離された、牛や馬と同じように奴隷所有者に支配されて労働する人間(奴隷)が存在していく。そして紀元前七三年に発生した史上有名なスパルタクスの反乱は奴隷解放の先駆的事件であった。
人類最初の階級社会、奴隷制国家は、紀元前七五〇―七〇〇年代の古代ギリシャの都市国家(アテネ、スパルタ)であり、紀元前五七五年頃の古代ローマ帝国である。そして権力と国家が生まれた途端に戦争がはじまった。ギリシャではあのトロイの戦争、古代ローマは地中海制覇をめぐる幾多のローマ物語のとおりである。以後の人類世界は戦争の歴史である。日本では紀元前二世紀に生まれた弥生時代からであり、中国の歴史書『三国志』などに記されている「倭国大いに乱れ、百余国に分かれて争う」という世界になったのである。以後今日まで人類世界は戦争の歴史であり、戦争のない時代はなかった。だから小さな戦争たる犯罪と殺人事件と、暴力と抗争は今日でも絶えることがない。すべては社会的人間道徳の消滅と、個人的欲望の世界の産物である。アダム・スミスとブルジョア経済学、自由主義経済、市場原理主義、「見えざる神の手」などの思想原理はまったくの形而上学、観念論であることは明白であり、歴史はもはやここからの脱出以外に前には進めなくなっている。
(3)、生産力の発展が生産関係(国家と社会制度)をつぎつぎに変化させ、発展させた人類の歴史をしっかりとみつめよ。ここに歴史科学・社会科学としての経済学がある!
前項、序論(1)、(2)でくわしく明らかにしたとおり、人類が生まれた当初は生産力がなく、自然採集経済であり、そこでは協力と共同の原始コミュニティー社会があった。やがて道具や機械の改良、改革、発明が進み、生産力が高まり、余剰生産物が財産となり、この財産の支配をめぐる欲望的人間による争奪戦が開始され、ここに人類史上最初の支配権、権力機関としての国家が生まれた。これが古代奴隷制国家である。生産力の発展が生産関係(人間の相互関係、国家と社会制度)を変化させた最初の第一歩であった。以後の人類史はこの法則が一貫して貫かれていく。奴隷制以後はどうなったのか。その基本的法則は以下のとおりである。
原始共同体から奴隷制へ、そしてつぎの封建制へと歴史は転換していく。それを促したのは生産手段の発達(機械と用具の木製から石器類へ、金属製へ、単純なものから複雑なものへ、改良、改革、発明、発見)にもとづく生産力の向上であった。このことがそれまでの奴隷労働(奴隷制)ではなく農奴(封建制)を求めていった。奴隷制国家から封建制国家への転換は歴史の必然であった。
奴隷制時代の中・後半に至ると、人口の増大、土地開発の進行、農地の拡大、山林開発と生産拡大の条件は進化し、発展していく。そして生産力を高めたものこそ、道具、機械の改良、改革、発明、発見であった。木製から石器類へ、そして金属製へ、単純なものから複雑なものへと進んでいく。
それにあわせて大規模な開発、改良、水路と灌漑(かんがい)施設の整備、天候に応じた作業の工夫、など、生産力の発展は必然的に生産関係(人間関係、国家と社会構造)の変化を求めていった。
つまり、奴隷制は不都合になったのである。奴隷労働は非人間的であり、牛や馬のように、労働するだけの食物(や衣服)が支給されるだけで、もちろん家族も持てない。これでは労働意欲も湧くはずがない。これでは道具、機械の使い方、天候に応じた創意工夫も生まれない。こうして労働能力の向上のためには奴隷制ではなく、農奴制を必要としたのである。
農奴は人間奴隷ではない。彼らは一人の人間として認められ、家族を持つことも可能となり、創意工夫して働き、生産物が増大すれば一定の割合で自己所有物(財産)も持てる。労働意欲はいっそう高まる。封建制は奴隷制よりもいっそう人間的であり、より進歩した。しかし、農奴は土地に縛り付けられ、土地から離れることの自由は許されず、本当の人格、人権はなく、そういう意味で農奴なのである。だがここで決定的なことは、奴隷から解放されたということ、生産力向上のための一大変革であったこと、そして生産力の発展と前進が生産関係を変更させたということ、ここに歴史的進歩と歴史科学があり、ここに科学的経済学があるということである。
確認しなければならないことは、紀元前七三年代に発生したローマ時代のスパルタクスの大反乱は、奴隷解放を求める大衆的蜂起であり、西紀三七五年代に発生したいわゆる「ゲルマン民族の大移動」とは、働ける土地と、家族と共に暮す場所を求める奴隷の反乱なのである。こうして歴史は封建制を求めて流れていった。
西紀三九五年にローマは東西に分裂、四七六年に西ローマ帝国は滅亡、五二七年には東ローマ帝国も終わった。以後ヨーロッパ各地に多くの封建王国が成立する。中国では西紀九七九年に宗が全国を統一、日本では一一九二年に鎌倉幕府が成立、奴隷制から封建制へ世界は支配されていった。ここに生産力の発展が生産関係を変化させ、発展させるという歴史科学の法則があり、ここに歴史科学としての経済学がある。
生産用具(生産手段)のいっそうの発展は、手工業的家内工業から、大規模な工場制工業となる。その結果製品は大量となり、交換経済は商品流通を生み、すべては商品となる。そこから貨幣が登場し、貨幣の所有者(ブルジョアジー)が社会の主人公となる。同時に経済活動は自由な商品としての労働力(労働者)を求め、農奴解放(奴隷解放)を求める。近代自由主義、資本主義の到来である。
生産手段(道具、機械、土地、交通手段)の改良、改革、発明、発見は生産物の爆発的増大となり、それは必然的に商品となり、商品交換と販売と販路を求め、そのための流通手段としての貨幣を生み出し、商品経済、貨幣経済を生み出していった。このような生産力の発展が、生産関係としての社会制度と国家形態の変更を求めていく。つまり、封建的な国境、関所、鑑札、身分制、土地に縛り付けられた農奴の解放を求めて動く。とくに商品経済は自由を求める。経済的自由、自由な商品としての労働力を求める。機械や道具を自由に使いこなすための労働力は自由に移動できる人間でないと広く人材を求めることは不可能である。自由こそが商品経済と貨幣経済と工場制大量生産のためには絶対不可欠な社会制度なのである。自由を求めて歴史は動く。
特に注意しなければならないのは、商品経済、貨幣経済、資本主義経済、欲望の自由放任と利益追求第一の経済を貫くものは価値法則である。つまり、利潤、利益を生み出すのは道具や機械そのものではなく、それを使って働く労働、労働力である。商品、品物の価値(価格)はそれに使用された労働量(労働時間)によって決定される。労働、労働力こそが利益、利潤の源泉なのだ。故に、資本は自由に、広く、いたるところから、質のよい労働力(労働者)を求める。この法則が、国境や関所や鑑札や土地に縛りつける農奴制度を拒否するのである。人間欲望の自由放任をふくめて、商品経済、貨幣経済、資本主義経済、ブルジョア社会は、一切の自由を求める。「自由こそわれらの世界」なのである。
十四世紀からヨーロッパに激発した文芸復興運動(ルネッサンス)、一七八九年のフランス大革命と人権宣言の成立などはみな自由主義的ブルジョア革命の雄叫びであった。そして歴史は一六四一年のイギリスにおけるピューリタン革命、ロシアにおける一八六一年の農奴解放令の発布、アメリカの南北戦争と奴隷解放(一八六一年)、日本の明治維新(一八六八年)、中国の辛亥革命(一九一二年)を通じて、世界は封建制から脱却して近代資本主義へと転換していった。すべては生産力の発展が生産関係を変更していったのであり、これが科学的歴史観、科学的経済学の法則の正しさを証明する歴史科学である。
自由主義から出発した近代資本主義、人間欲望の自由放任主義、その自由主義経済はもはやその頂点に達した。独占と帝国主義の時代は登り詰め、らん熟し、腐敗し、能力を失い、次の時代に移行せざるを得ない人類前史の最後の段階である。人類は大衆社会、人民の世界、近代的コミュニティーへの転換を求めて激動しているという、現代の時代認識を知ろう。
一七七〇年代から開始されたイギリスにおける産業革命によって近代資本主義は飛躍的に発展し、新たな時代、独占資本主義と帝国主義の時代に移行した。帝国主義とは、独占資本主義であり、同時に、最大限の利潤を求め、市場原理主義となって世界市場の独占のための、他民族と他国制覇をめざす侵略戦争である。独占資本と帝国主義とは、まさに戦争と暴力、略奪と虐殺、支配と収奪のための殺人マシンである。それは第一次世界大戦(一九一四―一八年)では死傷者三千万人、第二次世界大戦(一九三九―四五年)では民間人を含めた死傷者八千五百万人、そして第二次世界大戦以後の世界の戦争と内乱、テロと暴力による犠牲者はこの三十年間だけで二千万人を超えている。まさに独占資本と帝国主義、現代資本主義は二億人を殺した大量殺人兵器であり、暴力機関であり、歴史はここから脱出しなければならない。そのために世界は激動している。
独占資本と帝国主義の経済法則は、その限りなき欲望の自由放任にもとづく最大限の利潤追求であり、すべては利益第一主義であり、そのための生産第一主義、そして拝金主義である。
そのための方法としての自由競争であり、その場所としての市場原理であり、結果としての弱肉強食であり、格差社会と大衆の貧困化である。
こうして現代独占資本と帝国主義は地球と人類世界を物質万能主義の支配、動物的世界、人格と人間性そう失、地球とその環境破壊を生み出していった。
現代世界に出現している戦争と内乱、暴力とテロ、民族紛争と国境対立、宗教と人種的暴動、あらゆる形の犯罪と殺人、腐敗と堕落はすべて、独占資本と帝国主義の経済法則が生み出したものであり、まさに哲学原理たる「存在(独占と帝国主義)が意識(社会現象)」を生み出す必然性なのである。
「走れメロス」(太宰治の小作品)のように、欲望に憑(つ)かれた独占と帝国主義は、ただ、ひたすら、走りつづけてきた。そして最後の頂上に登り詰めた。もうその先はない。つまり、支配し、収奪し、略奪してしまったそこには、自分の意志とは無関係の世界、大衆的貧困と反乱と暴動と戦争と内乱、あらゆる形の犯罪と混乱と動揺の世界を出現させてしまった。最大限の利潤を求める無限の市場もなくなってしまった。
こうして人類の歴史は、いつまでも同じ所に止まっているわけにはいかず、もうここから脱出しなければ進歩はない、という段階に達してしまった。人類の歴史をみればわかるとおり、爆発と収れんを通じて常に変化と発展を遂げてきた。とくに、独占と帝国主義は、自ら引き起こした戦争を通じて自ら崩壊していったのである。明らかなように、第一次世界大戦ではロシア帝国とドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国とオスマン・トルコ帝国が消えた。第二次世界大戦を通じて日本、ドイツ、イタリアの三国ファシズムが消滅し、フランス、イギリスの帝国主義がその地位を失った。そして地球上最後の帝国、アメリカ帝国主義がイラク戦争を通じて崩壊している。こうして、つぎつぎに新しい時代に移行していく。それはすべて、生産力の発展が生産関係(国家と社会制度)を変更していくという経済法則の産物である。
独占資本主義と帝国主義とは、近代資本主義の最高度に発展した最後の段階である。もう老い朽ちてその先はない。その先に出現するものは、人類史の新たな時代、階級対立と階級闘争を終結させた新しいコミュニティーの歴史時代である。こうして人類はつぎの新たな闘い、宇宙開発という新時代への移行である。経済学の新たな使命はこの闘い、大宇宙の開発に関する追求でなければならない。
価値法則について
資本主義経済は商品経済である。この世界はすべてが商品であり、商品でないものはない。労働者も自分の労働力を商品として資本家に売って生活している。だから労働者も商品となる。
そして商品は互いに交換されることによって経済活動、経済生活が成立する。だから資本主義経済は商品の交換が柱である。これが売買であり、商品の売買によって資本主義は動いている。
商品の売買は等価交換である。それは同じ価格によって交換される。その価格を表現するのが貨幣である。人類社会の当初は物々交換であったが、そのときでも経験則(慣習)によって、自然に等価交換が実現されていた。
等価交換とは、同じ値段で交換する、売買する、ということである。ではまったく姿も形も違う商品を、同じ値段として認めるその尺度、規準は何か。それは商品はどんな物でもみな労働生産物であり、どんな商品でもそこには労働力(働く力、能力、エネルギー、技術力)が使用されているから、万物を支配するこの労働力こそが価格決定の尺度、規準となる。これが労働力の価値である。
商品価格の規準は労働力の価値である。その商品の生産にあたって、どれくらいの労働時間(労働力の使用時間)がかかったのか、ということが価値判断の基準となる。この価値が価格として表現される。
ではその労働力の価値は何で決まるのか。それはその労働力を生み出す労働者の、その歴史時代が必要とする生きていくため生活費の総額である。
ところが、資本主義社会では、その商品に使用された労働力の使用量(価値、価格)で売買されても、資本家が労働者に渡す代金(賃金)は、価値の総額ではなく、その中の一部でしかない。つまり労働者の受け取る賃金とは食うことがやっとだというくらいのものであって、あとの価値の大部分は資本家の利潤となる。これが剰余価値であり、剰余労働である。
これが価値法則であり、この価値法則が存在するかぎり、資本主義社会では貧富の格差拡大は必然であり、富める者はますます富み、貧しい者はいつまでも貧しいのは当たり前である。
社会主義制度では、商品経済は消滅し、すべては共同体の中での生産活動であるから、共同生産、共同分配、共同労働として運営される。ただし、社会主義の初期段階の農業分野ではまだ価値法則は部分的に残っており、これは機械化の発展と生産力の向上によって、工業と農業の差、都市と農村の差、知的労働と肉体労働の差がなくなったとき、価値法則は完全に消滅し、そこでは能力に応じて労働し、必用に応じて得るという共産主義が実現される。
第5章
社会主義経済学、社会主義とは何か。レーニン、スターリンの偉大なソビエト社会主義建設の勝利を確認せよ。そしてわれわれはこれを正しく「止揚」しなければならない!社会主義経済学とは何か?社会主義とは何か? レーニンとスターリンの偉大なソビエト社会主義建設の勝利を確認する。そして、それを正しく昇華させなければならない!
マルクスは一八四三年、ドイツ政府に危険分子という烙印(らくいん)を押され国外追放された。パリに移ったマルクスはここで新たな革命運動を開始、一八四四年に『独仏年誌』を発刊した。エンゲルスはこのことを知り、イギリス資本主義の現状を分析した貴重な文書『経済学批判大綱』を寄稿した。マルクスはこの文書を高く評価、これをきっかけにマルクスも経済学批判に取り組むようになり、それが『資本論』へと発展していく。
エンゲルスはこの論文の中でつぎのように論じた。資本主義経済はますます機械化された大工業となる。大量の労働者とその労働は必然的に協力と協同と連帯の作業、つまりは社会的な性質を帯びてくる。その生産物もまた大量となり、広く社会的な需要を考慮せざるを得なくなる。ここにも社会的要素が強くなる。にもかかわらず、イギリス資本主義は、すべてが個人主義であり、個人的欲望と利益追求だけである。その結果、すべての経済活動は盲目的となり、無政府的となる。生産活動に従事する働く人びと(労働者)は、生産物は増大するのに得るものは少なく、社会的不公平と不平等は拡大する。この矛盾を解決するためには、生産手段(土地、工場、建物、機械、道具、交通手段)を社会的所有、公のもの、社会主義に移行させることである、と。
エンゲルスと一致してマルクスもまた『資本論』を通じて、とくに一八八二年一月二十一日に書いた『共産党宣言』のロシア語版の序論で「ロシアに残っている原始的農民共同体、土地の共同所有形態が、プロレタリア革命と結合したとき、共産主義的共同体への出発点となる」と書いた。
マルクスとエンゲルスは一貫して、生産手段(土地、工場、建物、機械、道具、交通手段)の社会的所有、共同体、コミュニティー、社会主義化をとなえた。
そしてエンゲルスは『共産主義の原理』(一八四七年)の中で、真の自由と民主主義、真の平等と公平と人間性の豊かさは、国家と社会そのものが、協力と共同のコミュニティーでなければならず、生産活動もまた個人主義ではなく、社会的欲望(社会の需要)と社会的人間の欲望(大衆的人間の需要)に答えられる目的・意識的、計画的生産、計画経済でなければならない、と主張した。
エンゲルスは『空想から科学への社会主義の発展』(一八八〇-八二年)でつぎのように論じている。資本主義経済は欲望的自由主義であり、必然的にそれは行き当たり的、無計画的、無政府的になる。これに反して社会主義は、社会のため、人民のため、コミュニティーを豊かにするため、そのための目的・意識的、計画的な経済活動である。社会主義は計画経済である、と。そして『共産主義の原理』でも、社会主義的計画経済を通じて、工業化、機械化、化学技術が発展し、生産力が高度に発達したとき、工業と農業、都市と農村、知的労働と肉体労働の差がなくなる。そうなったとき、共産主義の低い段階の社会主義から、社会主義の高度な段階の共産主義に到達する。これが国際的規模にも達したとき、そのときに国家というものは「廃止される」のではなく「死滅する」のである、と。
マルクスは一八七五年に発表した『ゴータ綱領批判』の中で、資本主義における自由主義と自由競争とは個人的欲望にもとづく排他的競争である。その結果は必然的に弱肉強食の世界を作り出す。これに対して社会主義における競争、社会主義競争とは、社会のため、われわれのコミュニティーのため、みんなのための競い合い、励まし合いなのだと主張する。何のために、どういう目的なのか、その性格、性質が根本問題なのである。
マルクスはその論文の中で、社会主義とは共産主義に到達する前段階であり、だからまだ資本主義の母斑(残りかす)は残っている。これはさけられない。故にここでは商品経済も、価値法則も生きている。したがってそこは「能力に応じて働き、働きに応じて得る」時代である。生産力が高度に発展し、生産物がより豊かになった共産主義の時代、そのとき「能力に応じて働き、必要に応じて得る」という時代に達する、と主張している。
マルクスとエンゲルスが明確にしたとおり、独占資本主義と帝国主義の経済法則はまさに盲目的であり、無政府的である。それはスミスの古典経済学が説くように、人間欲望の自由放任と自由主義が生み出す必然の法則である。それは現実の資本主義世界そのものが立証している。世界の歴史は土地と領土と財産をめぐる対立と抗争に明け暮れ、そのための戦争は絶えることなく、その度に国家と社会は破壊され、そのことを通じて小民族と小国家の大国支配が実現されていった。
資本主義経済の歴史を見ても、常に破壊を繰り返し、そのことを通じて大衆収奪と大衆の貧困化は進み、巨大独占資本の支配が実現されていった。最近の実例、世界大恐慌を引き起こした一九二九年十月二十四日のニューヨーク株式大暴落(暗黒の木曜日、ブラックサーズデー)も、一九八七年十月十九日、史上最大の株式大暴落(暗黒の月曜日、ブラックマンデー)、これらの大小繰り返される経済上の事件は日常化している。そして現代、二〇〇七年夏からはじまった「サブプライム問題」を根源とする世界的規模の金融、経済不安と混乱と混迷、それらはみな資本主義の自由主義、盲目主義、無政府主義という経済法則の産物である。ここで肝心なことは、このような自由主義経済法則は必然的に、その結果として、徹底的な大衆収奪、大衆の貧困化、その反映としてのすべての分野における独占支配と独占化が進み、格差社会は無限となる、ということである。
現代世界最強のアメリカ、巨大独占資本支配のアメリカこそ最大の格差社会であり、貧困社会であることがこのことを証明している。現実に、国際通貨基金(IMF)は二〇〇七年十月九日に世界経済見通し(WEO)の分析結果を公表したが、そこでははっきりとつぎのことが述べられている。「所得の格差がすべての国と地域でますます拡大している。所得の絶対額が増大する中で貧困層が増加し、それを上回るペースで富裕層が増加している。格差社会の代表格はアメリカであり、中国はその米国を追い越す勢いで格差が拡大している」と。
人類の歴史は自由主義・盲目主義・無政府主義か、目的意識的・計画的・社会主義的計画経済か、という根本問題を提起している。歴史は科学的法則のもとに立ち返るよう求め、転換せんと爆発している。
第1節
マルクス主義経済学とは、目的意識的で、科学的であり、計画的で、社会的(社会主義的)計画経済である。その正しさはレーニン・スターリンのソビエト社会主義建設の四十年が、偉大な勝利としてはっきり証明している。その歴史的事実、客観的事実をしっかりと確認せよ!
マルクス主義の科学的経済学は、レーニンとスターリンによって、実際にこの世で、そのソビエト社会主義建設の四十年によって、みごとにその正しさが立証されている。その四十年間のソビエト社会主義は、マルクス主義的計画経済の勝利の四十年であった。レーニン、スターリン時代のソビエト社会主義建設の四十年間がいかにすばらしいものであったかということは歴史が証明している。観念論でなく、歴史上の事実として、多くの証人と証言に照らして、率直に確認しなければならない。
ロシアは非常に遅れた農業国であった。ロシアが資本主義に移行したのは一八六一年、ツアー(皇帝)による農奴解放令の公布からであった。しかしそのとき、世界はすでに資本主義時代の発展期にあった。イギリスは一三〇〇年代に農奴は解放され、一六四一年にはピューリタン革命が実現され、完全に資本主義社会であった。ロシアはそういう遅れた国であったから、一九〇五年の日露戦争ではアジアの小国・日本に敗北し、一九一四年にはじまった第一次世界大戦ではドイツに敗北しつづけたのである。そしてロシア皇帝は退位した。この過程でロシア革命が実現し、レーニン、スターリンの社会主義時代が出現するのである。
レーニンの時代は外国干渉軍と国内反乱軍とのし烈な戦争とその勝利、「共産主義土曜労働」(社会主義競争)による社会主義の基礎的建設の勝利の時代であった。
レーニンとソビエト社会主義が成立したその直後の一九一八年のはじめから、世界中の資本主義国が、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本を中心に、全部で十六カ国が、いっせいにソビエトに攻め込んできた。それに呼応して、国内の旧時代の将軍たちも反乱軍を組織して蜂起した。こうしてあの過酷な国内戦が五年間もつづくのである。レーニンとソビエトはこれに対して「戦時共産主義」を発動し、義勇軍(遊撃隊、ゲリラ)を組織し、人類最初の社会主義祖国を守れ、というスローガンのもと、千五百万人の犠牲を払って戦い抜き、勝利した。この歴史的事実のなかに社会主義の偉大さ、その強じんさ、その優越性がある。
徹底的に破壊されたこの国土に社会主義を建設するにあたり、その苦難な経済建設に、若い青年たちが決起する。それが「共産主義土曜労働」である。土曜日の半日休業を返上し、無償労働で祖国と社会主義建設に奉仕しようというこの運動は全国に広がった。レーニンはここに真の競争「社会主義競争」があると高くたたえた。戦争時の「戦時共産主義」、平時の「共産主義土曜労働」、ここに資本主義の「弱肉強食の自由競争」と、ソビエト社会の「社会主義競争」の違いがある。
そしてレーニンは一九二〇年十二月に開かれた第八回全ロシアソビエト大会の席上「社会主義とはソビエト権力プラス全国の電化である。エネルギー革命によって国の工業化と近代化を達成しよう」と呼びかけた。そして直ちに「全ロシア電化委員会」を設立、翌年にはこれを「ゴスプラン」(ソビエト連邦閣僚会議国家計画委員会)に改組、本格的な計画経済に取り組んでいったのである。
レーニン、スターリンのソビエト社会主義建設の偉大な勝利を証明する世界の記録と、多くの証言をみよ。客観的事実の中から社会主義計画経済の正しさを確認しよう。
レーニンのあとを継いだスターリンは、遅れた農業国のロシアを、近代的な重工業と化学技術工業国へ向けた計画経済を実施。一九二八年から開始された第一次五カ年計画は、つぎつぎに継続して実現され、その中から新たな社会主義競争も展開された。その一つがスタハノフ運動である。一九三三年から始まった第二次五カ年計画の中で、ドンバス(ウクライナ南部の炭鉱)で働くスタハノフ(一九〇六―一九七七)は、技術の研究と改良、作業手順の綿密な検討と合理化の中で、今までの十四倍という生産量の増大を実現させた。スターリンはここに社会主義競争の見本があるとして「スタハノフ運動」を全国的に展開した。
レーニン、スターリンの社会主義経済建設の巨大な発展については、世界の新聞、雑誌、統計資料、学者知識人の発言などによってそのことは証明されている。その代表的な実例の中には、一九八五年度版『共同通信社・世界年鑑』がある。そこでは、ソビエト経済について「工業の成長率は第一次五カ年計画(一九二八)以来、一九五九年まで、第二次世界大戦中を除いて最低でも一〇%という高度成長を達成した」と記録されている。
そして学者・知識人の証言についてはジョン・K・ガルブレイス(一九〇八―二〇〇六)がある。アメリカ経済学会の大御所で、一九七〇年代のアメリカ経済学会会長で、二十世紀経済学の巨人、アメリカ知性の代表といわれたガルブレイスは、一九八九年四月出版の著作『資本主義、社会主義、そして共存』の中でつぎのように書いている。「資本主義諸国が一九三〇年代に大恐慌と不況にあえいでいたとき、ソ連の社会主義経済は躍進に躍進を続け、アメリカに次ぐ世界第二位の工業国になった。そして完全雇用と社会保障をやってのけた。そして三〇年代、四〇年代の科学と技術、兵器と軍事技術、原子エネルギーと宇宙開発、大西洋横断とジェット機開発、などの近代科学と技術の分野ではソビエトは当時世界をリードしていた」と。ガルブレイスはその本の中で、このソ連経済が崩壊しはじめたのは一九七〇年代以後(フルシチョフの修正主義によってソビエトの党と国家が変質したあと)のことであったことを論じている。
そしてもう一人、日本では小泉信三(一八八八―一九六六)の発言をあげることができる。小泉氏は日本の有名な経済学者で、慶応義塾の学長を務め、現天皇の皇太子時代の教育係を務め、文化勲章の受章者であり、昭和日本を代表する最高の知識人であった。氏は名高い反マルクス主義の闘将であり、マルクス主義批判を展開するその氏が、一九三三年に出版した『マルクス死後五十年―マルクシズムの理論と実践―』(好学社・刊)の中で、スターリンの五カ年計画の巨大な発展に目を見張り、つぎのように書いている。「ソビエト経済の発展は従来、しばしば、局外観察者の予想を驚かせた。ことに一九二八年以降における累次五個年計画の成績は、懐疑的批判者の意表にでるものが多かった。この点において、著者もまた対ソビエト観察において一再過ちを犯したことを自認しなければならぬ。…勿論ソビエト経済は、ソビエト当路者少数人の力によって発展して来たものではなく、当路者その人がすでに一面環境の所産であることは、これを争うべくもない。しかもそれ自身一面環境の所産に外ならぬソビエト政治家その人の洞察眼と実行力とが、最も重要の点でその発展を左右して来たことは、否定し難きところである。著者はこの予測し難きものの予測において一度ならず誤った」と。小泉氏はこのように自らの認識不足を認め、ソビエト経済の驚くべき発展を謙虚に認め、率直にスターリンの力量に脱帽しているのである。一流の人間こそがこのように事実を事実として認めるのであり、二流三流の小人物は事実を事実として認められないのである。
スターリンのこのような計画経済と社会主義建設の勝利が第二次世界大戦におけるソビエト軍の大勝利を生み出したのである。事実を見れば明らかである。ソビエトの化学重工業の産物たる、連続多発式ロケット砲「カチューシャ」はドイツ軍だけでなく世界を驚かせた。最強度鋼鉄製重戦車「T34」はドイツ軍が誇る対戦車砲の弾をことごとくはねかえした。やがて世界最速の戦闘機「ミグ」を生み、二十一世紀の現代でも世界中の地上戦における第一級の自動歩兵銃「カラシニコフ」(AK)を生み出した。この銃は軽く、故障なく、壊れなく、そして最も威力があり、今でも第一級である。
一九四九年には原爆の開発に成功してアメリカと並び、一九五七年にはアメリカに先がけて人類初の人工衛星・スプートニク一号の打ち上げに成功。一九六一年にはガガーリン少佐を乗せた世界最初の人間宇宙船が軌道に乗り「地球は青かった」とのメッセージとなった。世界中が〝ガガーリン・ショック〟と、〝ガガーリン・フィーバー〟に沸いた。
第二次世界大戦におけるソビエトの勝利は、国の重工業化、化学産業の充実、という物質的勝利と共に、ソビエト国民(人民)の思想意識の高さもまたこれを保障した。それを象徴することのなかに「党員前へ!」というスローガンがある。ドイツ軍との決戦期、白兵戦の時期、そして突撃隊出動のとき、常に指揮官は「党員前へ!」を叫び、そして共産党員は常に一歩前へ出て、非党員の先頭に立ち、身を投げ出していった。それは第二次世界大戦のすべてに出現した革命的伝統である。その一例にフランスにおけるレジスタンス(ナチスの支配に反対する抵抗運動)がある。フランス国民は多くの犠牲を出してナチスと戦った。その先頭にフランス共産党員が立った。そして最大の戦死者を出し、当時フランス共産党は「銃殺される者の党」と呼ばれたのは記録に残っている歴史的事実である。
イギリスの軍事科学者、リデル・ハートもソビエト社会主義の巨大な発展に目を見張ったというこの事実を確認せよ!
レーニン、スターリンのソビエト社会主義のこのような巨大な発展と前進、その科学技術の高度な成果を証言したいまひとつの記録を紹介しておきたい。それはリデル・ハート(一八九五年パリに生まれ、一九七〇年一月イギリスにて没)の著作『第二次世界大戦』(日本語版・一九九九年九月中央公論社刊・上下二巻)である。リデル・ハートはケンブリッジ大学に学び、第一次世界大戦には将校として従軍、重傷を負い、以後軍事科学の研究に没頭、軍事科学に関する多くの著作を発表した。彼の軍事問題に関する科学研究はヨーロッパ各国で高く評価され、その功績により、イギリス女王から「ナイト」の位を授けられた。彼は前記の著作の中で、客観的事実として、ソビエト軍の高度な科学技術についてつぎのように書いている。
「ソ連軍の戦車はどこに出してもひけをとらないばかりか、多くのドイツ軍の将校にいわせれば、最高のものであった。……戦車自体の性能、耐久性、備砲では最高度な水準に達していた。ソ連軍砲兵は質的に優秀であり、またロケット砲の大規模な開発が行われ、これがきわめて有効であった。ソ連軍のライフル銃はドイツ軍のものより近代的で、発射速度も大きく、また歩兵用重火器の多くも同様に優秀だった」と。このことは、われわれが先に書いたとおり、戦車は「T34」であり、ロケットは「カチューシャ」であり、歩兵銃は「カラシニコフ」であった。そのことをリデル・ハートもはっきりと確認している。
またソビエト人民とソビエト赤軍兵士の戦闘能力についてもつぎのように書いている。「ソ連の一般国民は鋼鉄(スターリン)の名をもった彼らの指導者よりもずっと剛毅だった。……彼らは長蛇の列をつくって前線行きを志願した」。「ソ連軍の改革は上層部から始まった。当初からの高級指揮官を思い切って整理し、そのあとがまに大部分が四十歳以下の、若い世代の活動的な将軍を登用した。彼らは前任者よりもいっそう専門家であった。かくしてソ連軍統帥部は平均年齢でドイツ軍のそれよりも二十歳近くも若返り、活動性と能力の向上をもたらした」と。
このことのなかに、トハチェフスキー事件を通じてスターリンが実行したソビエト赤軍内の粛清と、根本からの赤軍再編成の偉大な成果がくみとれる。(この事件とくわしい歴史的事実については〈学習のすすめ〉第二節を参照されたい)。
さらにリデル・ハートはスターリン指導下のソビエト国民の一致結束ぶりについてつぎのように書いている。「ソ連兵は、他国の兵なら餓死するときにも生きつづけた。ソ連軍は西欧の軍隊なら餓死するはずの環境にも生存でき、他の国の軍隊なら破壊された補給が再開されるまで停止して待つはずの場合にも、彼らは前進を続行することができた。このときの印象を、ドイツ軍のマントイフェル将軍(独ソ戦開始時、第七装甲師団長)はつぎのように要約している。ソ連陸軍の進撃ぶりは西欧軍の想像を超えたものがあった。兵士はザックをひとつ背負い、その中に前進の途中、畑や村々から集めた乾いたパンの外皮や生野菜を詰め込んでいた。馬匹は家々の屋根わらを食べさせていた。ソ連軍は前進にあたって、このような原始的な訓練によっても長期の戦闘に慣れていたのである」と。
リデル・ハートはもちろん資本主義陣営の将軍である。だから政治的には反ソ陣営の人間であるが、先に紹介した日本の小泉信三氏のように、それでも事実は事実としてスターリンとソビエトの科学技術の偉大さと、ソビエト国民の英雄主義を認めざるを得なかったのであり、このことがこの著作の中に事実として記録されている。観念論者と違ってわれわれはあくまで客観的事実を重視する。なぜなら事実の中にこそ真理と問題の本質がかくされているからである。
第2節
ソビエト社会主義の偉大な勝利とその成果が崩壊したのは、フルシチョフによる「スターリン批判」という、反マルクス主義的ブルジョア思想によって、ソビエトの党と国家がブルジョア的に変質した結果であった。そしてこれは、マルクスが予言し、レーニンが予告し、警告していたことであり、社会主義が最終的に勝利するため必要な全歴史過程における、必然性の中の偶然性であった!
経済学については第四章においてそれは社会科学であることをくわしく論じた。あわせて、資本主義的ブルジョア経済学は、人間欲望の自由放任、個人主義的自由、盲目主義、無政府主義であること。反対にマルクス主義経済学は、科学的で目的意識的な計画経済、社会主義経済であることをくわしく論じた。
そして第五節の(一)の項では、マルクス主義経済学の正しさと、その偉大な成功と勝利の事実を、レーニン、スターリンのソビエト経済建設の四十年という歴史的事実を通じて正確に検証した。これは記録された経済統計、第一級の経済学者、知識人の証言でも確認されていた。そしてこれらの証明、証言を通じて、レーニン、スターリンの偉大な社会主義が崩壊したのは、実にフルシチョフの「スターリン批判」という名のブルジョア思想によって、ソビエトの党と国家が資本主義に変質し、変色した結果であったことも明らかにした。ソ連の社会主義がおかしくなり、崩壊していったのはフルシチョフ以後であったことを明らかにした証言はその他にもたくさんあるが、代表的なものの二、三についてここに紹介しておきたい。
一九九〇年九月二十四日付『毎日新聞』は「どうなるソ連の経済改革」という特別記事を掲載したが、その中に次の一節があった。「戦後ソ連経済は目覚ましい発展を続けたが、ブレジネフ時代の後半から経済成長が止まり、生産設備の老朽化が進んだ」と。つまり、フルシチョフからはじまってブレジネフに続くソ連の変質と国家の崩壊をこう論じているのである。
また一九九一年三月号の月刊誌『世界』は「社会主義はどこへいくのか」という議論を掲載しているが、そこにはつぎのような一文があった。「人工衛星・スプートニクを最初に打ち上げたのがソ連であったように、一九六〇年代の半ば過ぎ頃までは生産力の拡大という点に関しては、むしろ計画経済の方が、あるいはソ連型社会主義の方がより有効である、というふうに資本主義陣営の人間も等しく考えていた。その結果として生まれてきたのがケインズ理論であり、別の言葉で言い換えれば、それは修正資本主義であった。このような社会主義が七〇年代のいつ頃からか、経済がこのように崩壊し始めたというのはいったいどういうことか」と。ここでも同じように、フルシチョフ、ブレジネフという、ソ連の党と国家の変質以後におかしくなったことを証言しているのである。
そしてまた一九九〇年三月六日付『日本経済新聞』は「ソ連経済の再建」と題する一文を掲載しているが、その中につぎの一節がある。「一九三〇年代は資本主義諸国が経済不況と失業、生産と貿易の不振という大混乱の間に、ソ連経済だけは高度成長を続け、後進国の希望の星となった。そしてアメリカ、ドイツにつぐ巨大な重工業を建設し、よくヒトラーの侵略に耐えたことは否定できない事実である」と。ここでも、レーニン、スターリンのソビエト経済建設の偉大さをたたえているのであり、これはまったく小泉信三の言質と一致している。
ここでよく注意しなければならないのは、あらゆる論評、記事、文書に共通するのは、前はよかったのに、後でおかしくなったのはなぜか? ということ。つまり途中でおかしくなったのはなぜかと言いながら誰も答えが出せない、ということなのである。
それがわからないから、解答が出ないから、その結果として一番手っ取り早い方法として「ソ連型計画経済の失敗だ」、「マルクス主義の誤りだ」などという、あの古い反共、反社会主義、反マルクス主義のスローガンを持ち出しているのである。ブルジョアジーが昔から使ってきたあの手法を新しい装いをこらして吹聴しているのである。
われわれは一貫して、昔からこういう種類のブルジョア的言論とは闘ってきたので何もめずらしいことではない。われわれは思慮分別があり、時流に流されることもなく、科学的知識と歴史を科学として見る目をもっているから、この問題についても明確である。つぎがわれわれの見解であり、結論である。
フルシチョフとはマルクス主義運動の歴史上において、最大の修正主義者、変節者、最大の裏切り者であった。その理論上・思想上・政治上の本質を見よ。その結果、ソビエトの党と国家が変質したこと(内因論)によって、それ以後のソビエトは資本主義に転換したのである。社会主義の敗北ではない!
一九五六年二月二十四日、開催中のソビエト共産党第二十回党大会の席上、党の最高責任者たるフルシチョフ第一書記は、いわゆる「スターリン批判」という秘密報告を行ったが、その内容は六月四日にアメリカ国務省によって公表され、全世界に大きな衝撃を与えた。それは誠に驚くべきもので、まさにスターリンとは血の粛清による独裁者であった、というもので、すべての人びとをあぜんとさせた。フルシチョフはアメリカへ通告し、連絡を取り、アメリカはフルシチョフの了解のもと公表したのである。
さて、このアメリカ国務省による「スターリン批判」の内容を知った全世界のあらゆる分野で大騒ぎがはじまった。右も、左も、中間も「これはどういうことだ」というわけである。しかしこのとき、われわれ正統マルクス主義者、真正共産主義者は誠に冷静であり、毅然たるものであった。なぜならわれわれは、マルクス主義の理論上の原則、科学思想の原則、万物を認識し支配する根本原理たるマルクス主義哲学を正しく認識し、この哲学からすべてを理解し、判断する能力をもっていたからである。そしてフルシチョフの如き人物はいつかは出てくるものであることを、レーニンが予告し、警告していたことも知っていたから、これこそソビエトにおけるブルジョア思想の出現であり、復活であることを知ったからである(レーニンの予告と警告の文献についてはあとで紹介する)。だからわれわれは覚悟を固めて闘争の準備をしなければならないと決意した。そしてもう一度哲学に立ち返ること、第一歩から哲学を学ぶよう呼びかけたのである。
エンゲルスは『ドイツ農民戦争』(一八七五年)の中で「ドイツ哲学がなければマルクス主義は生まれなかった」と書いている。そしてレーニンは『マルクス主義の三つの源泉と三つの構成部分』(一九一三年)の中で「マルクス主義は十九世紀ドイツ哲学の正しい継承と発展、完成であった」と言っている。
そのマルクス主義哲学とは「唯物論」であり「弁証法」であり「史的唯物論」である。そのくわしい内容は〈学習のすすめ〉の第三節で展開されている。それはつまり「弁証法的唯物論」である。その「弁証法的唯物論」の核心を集約すればつぎの三項目となる。
第一は、宇宙と万物はすべて運動する物質である。ここに客観的事実がある。そして運動する物質の本質が人間の知的頭脳に反映し、頭脳を通して実現したものこそあらゆる政治思想であり、理念と理論であり、認識や自覚、という主観なのである。この客観と主観はまったく別のものであると同時に、運動するものの統一された二つの側面である。
第二は、物質の存在とは運動であり、運動とは発展、前進、飛躍、転換である。そのためのエネルギーは、物質内部に内包された熱、電気、化学作用、生命本能である。人類と人間の生活と社会的運動においてはその主観としての政治思想、理念と理論、認識や自覚であり、これが内因としてその運動を支配していく。
第三は、物質運動の基本法則(方法)は〝止揚〟である。止揚(しよう、揚棄、アウフヘーベン)とは、古いもの、過去、現在そこにあるものから出発し、それを引き継ぎながら、その中の発展的で、先進的で、革命的なものを引き出し、育成し、成長させ、こうして運動の飛躍と転換を通じて新たなものを獲得していく、ということである。
以上の三つは、弁証法的唯物論の根本原理であり、その核心である。この原理と核心が現実に、この宇宙と万物の運動を支配し、貫徹している。
マルクス・エンゲルス・レーニン・スターリンはマルクス主義運動の一系列である。
マルクス主義哲学の第一原理と核心からフルシチョフの「スターリン批判」をどう見るか。それはまったくマルクス主義の否定、社会主義と共産主義運動の否定、そこから必然的に実現されるブルジョア思想への堕落、資本主義への転落、なのである。
なぜか。宇宙と万物とは運動する物質であり、それが客観的存在である。この物質運動の存在が生み出すのが政治思想であり、理念と理論であり、自覚と認識である。故に存在と意識は統一された二つの側面である。この原理からマルクス主義運動、社会主義運動、共産主義運動をみるとき、その存在としての物質運動は明らかなごとく、それはまさにマルクス・エンゲルスと第一インターであり、レーニンとロシア革命と第三インターであり、スターリンとソビエト社会主義の建設とコミンフォルムであった。この一系列こそ、マルクス主義、社会主義、共産主義運動の物質的表現であり、その思想上、政治上の理念と理論がマルクス主義、レーニン主義なのである。
この哲学原理と核心からみたとき「スターリン批判」とは、まさしく、マルクス主義運動、社会主義運動、共産主義運動の否定であり、その物質運動を否定することによって、その意識的表現としての思想と政治も否定してしまったのである。
マルクス主義運動の物質的存在とは、マルクス・エンゲルスと第一インター、レーニン・スターリンとソビエト社会主義建設、こういう人間と運動体(組織)と国家・社会・権力なのである。歴史上、マルクス主義と社会主義と共産主義運動の物質的表現はこれしかなかった。この一系列以外に、哲学が示す客観的存在という物質運動は、他にはなかった。この物質運動としてのマルクス・エンゲルス・レーニン・スターリンというこの存在を認めるのか、認めないのか。フルシチョフは「スターリン批判」によってこの物質運動としての一系列を否定した。そのときフルシチョフは自己の属性を離れ、その系列から離れ、脱落し、他の属性と陣営(資本主義陣営)に脱走、脱落していった。こうしてソビエト社会主義は内部から変質し、変節し、資本主義に脱落していった。ソビエト連邦とソビエト社会主義のフルシチョフ以後の歴史はこのことの正しさを見事に証明している。
なお、トロッキズムについていえば、そういう政治思想と理念や理論というものは、物質として、つまりは歴史上の運動としてはどこにも存在せず、空想に過ぎなかった。物質的運動の世界に、物質的運動としてはどこにも何もなかったのである。ただトロツキーという一人の人物が、個人的にいわゆるトロッキズムといわれる論理をとなえていたということだけのものである。
なお、理論と実践の相互関係について明らかにしておきたい。思想・理論というものは実践(物質運動)が生み出すものであり、物質運動という実践が知的頭脳に反映して生まれる。だからその理論が正しいかどうかは物質運動という実践によって証明されていなければならない。また本当の正しい実践と行動は、正しい理論によって導かれないかぎり勝利しない。理論と実践は運動上の統一された二つの側面であることをはっきりと認識しなければならない。
哲学的内因論を認識せよ。物質運動はすべてその内部、内因によって運命は決定される。
マルクス主義の弁証法的唯物論の第二の核心たる「内因論」から「スターリン批判」をどうみるのか。内因論とは、物質の運動(発展、前進、飛躍、転換)のエネルギーはその内部にあり、運動の過程から生まれ、内包する熱、電気、化学作用、生命本能である。人間と人類社会では物質運動の反映としての政治思想、理念と理論、自覚と認識である。人類史は対立する階級の相互作用(階級闘争)から生まれる政治思想がエネルギーとなる。まさに「思想が物質的な力となる」(マルクス)のである。外的条件(外因)はすべて内因(内部のエネルギー)を通じて作用する。
一八五三年(嘉永六年)七月、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが軍艦四隻を率いて浦賀に来航し、日本の開国を迫ったというこの外圧(外因)が、日本国内の政情を刺激した。それが「尊皇攘夷」という統一スローガンによる徳川幕府打倒の内圧(内因)を引き起こし、明治維新が一八六八年(慶応四年)四月に実現したという歴史的事実も、歴史科学が教える内因論の見本である。
あとで紹介するレーニンの文書にあるとおり、独占資本と帝国主義の包囲下では、常にブルジョアジーの思想的・政治的外圧があり、それがソビエト内部の弱い部分に影響して、ついにフルシチョフを通じて爆発した。それが「スターリン批判」という名のブルジョア思想の展開であり、以後ソビエトは資本主義への道をばく進していく。
フルシチョフは一九五七年七月に各国共産党の代表を集めて国際会議を開き、そこで世界の各国の共産党はそれぞれ独自の道を自由に(自由化)進むことを確認し、新しいモスクワ宣言を採択した。このとき、マルクスの『共産党宣言』の精神と、「万国のプロレタリア団結せよ!」とのあの気高いプロレタリア国際主義は完全に放棄されてしまった。そして一九六二年十月に発生した、あの世界を震撼(かん)させた「キューバ危機」において、アメリカ帝国主義に屈服してキューバから撤退。わずか十年で一九六四年十月、フルシチョフは党から追放された。
しかしフルシチョフの「反スターリン主義」はそのまま引き継がれていく。ブレジネフ時代はいよいよ本格的にソビエト社会主義が崩壊する時代となる(前項・序論を見よ)。一九七三年六月にはブレジネフが訪米、米・ソ和解の共同声明を発表して、ソビエトを資本主義陣営の一員たることを確認。一九七六年六月には全ヨーロッパ共産党代表者会議を開催、いわゆる社会主義の多様性と自由化を確認してマルクス主義的本質を放棄。一九八五年三月にゴルバチョフが登場するが、その十月には党中央委員会総会を開催「ペレストロイカ」(改革開放というブルジョア自由化)を採択。一九八九年にはアメリカとの間で東西冷戦の終結を宣言。一九九〇年十一月にはソビエト最高会議にて社会主義という制度を放棄することを決定。一九九一年八月にはソビエト共産党を解散、自らも党最高責任者としての地位を退いた。こうしてそのあとのエリツィンによって十二月二十六日、ソ連邦最高会議の席上、ソ連邦の解体を宣言し、各共和国(各民族)は別々の道を進むことになった。
以上の歴史的事実が示すとおり、すべては内因論であり、すべては思想と政治であり、すべてはソビエト内におけるブルジョア思想の復活とブルジョア支配の実現、それにもとづく資本主義の復活であった。
はっきりしているように、マルクス主義の敗北や、社会主義の失敗ではなく、すべては内部の裏切りによるマルクス主義と社会主義の放棄が根本原因であり、マルクスの予言、レーニンの予告したことの出現であった。
万物の運動法則は〝止揚〟である。その反対は〝否定〟である。そして否定は否定される。
弁証法哲学の発展と前進に関する運動法則の第三の核心と原理たる〝止揚〟という認識論を正しく理解しなければならない。つまり、古いもの、過去、現在そこにあるもの、そのことを確認し、認識し、そこから出発し、これを引き継ぎながら、その中から新しいもの、先進的なもの、革命的なものを認識し、育成し、成長させ、飛躍させ、こうして新たなものを作り出していく、というこの法則は万物を支配する鉄の法則である。
宇宙と人類世界も止揚の法則による産物であった。最新の物理学が教えているとおり、約百四十億年前のビッグバン(大爆発)によって宇宙は誕生した。しかしそれは、その以前の世界、つまり無の世界、見ることもできない真空のエネルギー(暗黒物質)の運動が引き起こしたインフレーションによるビッグバンであった。宇宙とはまさに止揚の世界である。そしてこの宇宙は、過去と現代を引き継ぎながら、今なお、無限の世界で膨張し続けている。止揚は無限である。
われわれ人類、人間もまた止揚の産物である。地球が生れ、生命が生まれ、生物となり、動物(猿)から人間は進化していった。そして人類世界、その社会もまた、生産力の発展に応じた生産関係のなかで成長、転化しつつ、今日の時代を迎えている(くわしくは〈学習のすすめ〉第四節・経済学、をみよ)。
われわれ一人一人の人間個人を見てもわかるとおり、親があってわれわれがある。親を否定すればわれわれの存在自身が否定される。マルクス主義もまた止揚の産物である。レーニンは一九一三年に書いた『マルクス主義の三つの源泉』の中で「マルクス主義とは人類が十九世紀にドイツ哲学、イギリス経済学、フランス社会主義という形でつくりだした最良の英知の正統な継承であり、その完成であった」と言っている。つまり、止揚することによって完成させたのである。
そしてマルクス主義は、その物質的運動として、ヨーロッパにおける共産主義運動、第一インタナショナル。レーニンのロシア革命と第三インタナショナル。スターリンのソビエト連邦社会主義建設とコミンフォルム、へというふうに、その一系列として存在しつづけたのである。故に、真のマルクス主義は、弁証法的唯物論の運動法則の第三の原理たる止揚の法則にもとづいて、この一系列を引き継ぎ、これを発展させ、前進させるため、内因論にもとづき、その運動の中で闘いつづけることである。これを否定すること、「スターリン批判」という名の否定をすることは、マルクス主義の否定であり、自己否定である。結果として、ブルジョアジーへの屈服であり、社会主義から資本主義への脱落である。現実にフルシチョフ以後のソビエトは、そのあとを引き継いだブレジネフ、ゴルバチョフ、エリツィンらによって、完全に資本主義に脱落したではないか。フルシチョフに従ったユーロコミュニズムも、中国の鄧小平とその後の党と国家も、日本の宮本顕治とその党も、みなフルシチョフと同じ運命をたどっているではないか。
マルクスは『ヘーゲル法哲学批判・序論』(一八四四年)で、レーニンは『哲学ノート』(一九一四年)のなかで「否定するものは必ず否定される。否定の否定である」と言っている。現実にフルシチョフはスターリンを否定したが故に自分もまた歴史によって否定されてしまった。彼がその後存在したのはたかが十年であり、その最後は誠にみじめなものであったという歴史がこのことを証明している。
第3節
レーニン、スターリンの偉大なソビエト社会主義が内部からの変質によって崩壊したこと。それはフルシチョフや鄧小平の裏切り者が出現したからだということ。こうして社会主義は一度、はじめから再出発するに至ったこと。これらはみな、マルクスやレーニンがはやくから予言し、予告し、警告していたことであり、その歴史的意味をよく理解しなければならない!
第五節「社会主義経済学と社会主義的計画経済について!」の前文と(一)で、マルクス主義経済学の理論を実際にこの世の中に実現させたレーニンとスターリンのソビエト社会主義の偉大な勝利と発展の歴史的事実を、あらゆる記録と証言と歴史を通じて明確に立証した。人類の歴史とその将来は、近くはっきりとこのことを歴史として確認するであろう。現代の歴史時代がその遠くないことをわれわれに確信づけている。
そして歴史は、このようなソビエト社会主義の偉大な勝利とその成果が崩壊したのは、フルシチョフによる「スターリン批判」という、反マルクス主義的ブルジョア思想によって、ソビエトの党と国家がブルジョア的に変質した結果であったこと、つまりは哲学的内因論にあったこと。そしてまたこのことは早くからレーニンが予告し、警告し、マルクスもまた予言していたことでもあった。そしてなおこのことは社会主義が最終的に勝利するために必要なステップであり、全歴史過程における必然性の中の偶然性であったことも歴史が確認するはずである。
フルシチョフの出現を予告、警告したレーニンの言葉
レーニンは一九一九年十月に執筆した論文『プロレタリアートの独裁の時期における経済と政治』のなかでつぎのように論じ、われわれに強く予告した。
〔「社会主義とは、階級をなくすることである。プロレタリアートの独裁は、これをなくするために、できることはなんでもやった。だが、階級をいっきょになくすることはできない。そして、階級は、プロレタリアートの支配する社会主義の時期を通じて残っており、また今後も残るであろう。階級が消滅すればプロレタリアートの独裁は不必要となるであろう。そして階級はプロレタリアートの独裁なしには消滅しないであろう。階級は残っているが、プロレタリアートの独裁の時期には、どの階級も変形をとげた。階級間の相互関係も変わった。プロレ夕リアートの独裁のもとでは、階級闘争は消滅しないで、別の諸形態をとるだけである。……
搾取者、地主、資本家としての階級は、プロレ夕リアートの独裁のもとでも消滅しなかったし、またいっきょに消滅することはできない。資本家階級は、うち破られたが絶滅されてはいない。彼らには、国際的な基盤が、そして国際資本が残っており、彼らはこの国際資本の一支店である。彼らには部分的にいくらかの生産手段が残っており、金も残っており、そして巨大な社会的つながりが残っている。彼らの反抗力は、まさに彼らが敗北したために、百倍にも千倍にも増大した。国家行政や、軍事行政や、経済行政の〝技術〟は、彼らにきわめて、大きな優越性をあたえており、そのために彼らの力は、人口総数のうちに占める割合とは比べものにならないほど大きい。旧社会への復古の願望はいっそう強くなるばかりであり、旧社会の古い残りかすは根強い。倒れた搾取者と、勝利した被搾取者すなわちプロレ夕リアートの階級闘争は、はるかに激しいものになっていく。……
われわれの任務と責任は階級闘争を闘いぬくことであり、プロレタリアートと大衆を正しく指導すること、彼らに強い影響力をおよぼすために闘うことであり、動揺する者、ぐらつく人びとをひきいて前に進むことであり、これこそがプロレタリアートとその党がなすべきことである〕と。
レーニンは世界革命が勝利するまで、階級闘争の手をゆるめてはならず、裏切り者の出現に備えて、常に党と大衆の闘いに磨きをかけておけ、と予告している。
レーニンはまた、一九二一年六月に開かれた「共産主義インタナショナル第三回大会の基調演説」において全世界の共産主義者に向ってつぎのように呼びかけ警告している。
「われわれは革命に勝利したからといってけっして安心してはならない。まだわれわれの内部、社会主義国家の内部には、旧世界の生き残り組や、旧思想を捨てきれない者たちや、旧支配層の子孫や、社会主義に移行しきれない落ちこぼれや、国外の資本主義と通ずる裏切り者たちはいくらでも存在している。彼らは常に資本主義の復活をねらっている。世界革命が終了するまでは国際資本主義の圧力と攻撃は終わらず、故にプロレタリアートとその国家と党は絶対に油断してはならず、階級闘争を忘れてはならない」と。
このようにレーニンは世界革命の勝利の日まで、原理・原則どおりに闘うこと。プロレタリア国際主義、インタナショナルを忘れるな、と強く主張している。レーニンのこの血を吐くような叫びを忘れてはならない。
マルクスの「一度、はじめからやり直せ」という予言をよく知り、その歴史性を認識せよ
マルクスもまた、社会主義運動と共産主義運動はその歴史上において、一度は途中で立ち止り、はじめからやり直すことも必要であり、そのような歴史時代が必ずあることを予言していた。
マルクスはエンゲルスと共同執筆した『ドイツにおける革命と反革命』(一八五一―五二年)において、そして同じ年にマルクス自身が執筆した有名な論文『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』の中でつぎのように書いている。「歴史を見ればわかるとおり、革命にはいろいろあるが、その多くは短命である。しかしプロレタリア革命は人類史上では最後の革命であり、プロレタリアートは人類史における最後の階級であり、最後の勝利者である。故にこの革命は、どんな勝利の時代、平和な時代にも有頂天になることなく、むしろ中途で一度立ち止り、勝利と敗北から深く学び、ときには徹底的に破壊し、ぶち壊し、はじめからやり直す。ときには迷い、尻ごみをし、動揺する。しかしこれは歴史が解決する。歴史がプロレタリア革命を要求し、プロレタリアに決断を求め、プロレタリアはこれに答えて最終革命にむかって立ち上がる」と。
マルクスが言っているのはつぎのことである。つまり、科学的に正しい法則といえどもすべてが一直線で進むものではない。多くの実験、検証、失敗や敗北の中から真の勝利への道は開かれていく。プロレタリア(人民大衆)の運動と闘いもまた、その法則から免れることはありえない。最後の勝利者であるだけに、有頂天になることなく、一度は、はじめからやり直すことも必要なのだ、という。学びながら前進せよ、とマルクスは予言している。この意味を深く、高く認識し、理解しなければならない。そして現代のマルクス主義、社会主義、共産主義運動は、マルクスの予言どおりに進んでいることを確信しなければならない。
社会主義建設と社会主義の勝利の要(かなめ)は党であり、それは理論上(思想上)の原理・原則に忠実な党、理論と実践の統一的指導力の党、社会主義国家を正しく運営する方法としての二本足の権力を執行することができるような党である!
ここでわれわれが特に留意すべきは、レーニンの予告と警告である。レーニンは強く呼びかけている。社会主義建設期においては、形の違った階級闘争がますます激しく、きびしくなる。党は断固として階級闘争の手をゆるめてはならない、と主張する。そのような党が存在しなければならないのである。歴史上初めて社会主義を実現させたレーニンは、自らの実践と行動から学んで強く主張する。社会主義建設時代のマルクス主義党の歴史上の任務について、その党としての責任について、前記のとおり、社会主義の時代には必ず変節者、変質者、裏切り者が出現するものだと、われわれに強く警告した。だからレーニンは、そのためにこそ党建設を、党の強化を、党活動の原則性を強く、強く主張した。その党とは何か、党はどうあるべきかを、レーニンの有名な論文『何をなすべきか? われわれの運動の焦眉の諸問題』(一九〇一―二年)でくわしく論じている。その核心は、マルクス主義の理論上の原則を守り、基礎理論を離さず、すべては理論を導きにして実践活動を律せよ、理論の導きなしに革命運動の勝利はない、ということであった。
そしてレーニンは、理論闘争、政治闘争、思想闘争は、軍事闘争や、経済闘争とは別の、独自の分野の闘争であり、この闘争は党の独自闘争、独自の任務として実践し、行動せよ、と強く主張した。
そしてレーニンはその具体化、具体的実践として示したのがソビエト赤軍内の「軍事コミッサール」である。外国干渉軍と国内反乱軍との死闘の中で、ソビエト権力の主柱たる赤軍を維持し、その能力を高めるためにレーニンはコミッサール制を確立した。軍事機構(行政機関)としての上から下までの指揮命令系統の機関とあわせて、それに併行して党(思想・政治司令部としての党組織、党機関)を代表するコミッサール(政治委員)を配置(組織)した。このことについて、フルシチョフ出現前の正式の『ソビエト連邦共産党(ボリシェビキ)歴史小教程』(一九三八年)の第八章では「軍事コミッサールがなかったならば、われわれの赤軍はなかったであろう、とレーニンは語っている」と記している。そしてレーニンはその後ソビエト社会主義建設期を通じて、国家行政機構と機関に併行して、ソビエト共産党(ボリシェビキ)の党とその組織と機関を独自に作り上げ、その独自活動(思想闘争、政治活動、人民大衆の中での社会主義と共産主義運動)の展開を進めた。つまりは社会主義国家における二本足の権力執行である。この二本足の権力執行というレーニン的原則が崩れたとき、権力はブルジョア化し、社会主義は崩壊していく。フルシチョフ以後のソ連邦は完全にこれは崩壊してしまった。
ここに一つの参考文書がある。株式会社新潮社発行、中村逸郎著『東京発モスクワ秘密文書』(一九九五年六月十五日発行)である。著者は一九八八年から九〇年にかけてモスクワ留学をしたソ連問題研究家であり、氏はソ連共産党の実態を調べるべく、下部機関、地区委員会に接近し、内部文書や資料を手に入れて検討を加えた。結論は、ソビエト共産党は、実は日本でいえば町内会(自治会)の世話役であり、日常業務のすべてが、日本の区役所、村役場のような仕事であった、という。
これはもう完全に党ではなくなっている。
社会主義建設期におけるマルクス・レーニン主義党の任務は何か。それはさきに明らかにしたとおり、一方には国家行政機関がある。人類全体(世界的規模)で社会主義が勝利するまでは、一国における国家と行政機関は、経済建設と社会秩序の維持のため、法律と制度にもとづく実務行政機関として機能しなければならない。一方にはこれと分離した、まったく別の、人も、場所も、組織も、完全に分離した思想・政治組織としての党があり、党はもっぱら実務から解放された政治組織として機能しなければならない。その主要な任務は、マルクス主義の理論上の原則のもとでの社会主義建設、人民へのマルクス・レーニン主義に関する宣伝と教育活動。内外情勢とソビエト人民の任務、ソビエト社会主義建設における課題と当面の行動計画についての宣伝・教育。および全党員に対する思想教育、である。党と行政機関は、お互いにその任務を分離しつつソビエト社会主義の勝利のための統一目標に向かって補完しあいつつ前進するのである。
マルクス主義的前衛党にして、科学上の核としての政治・思想組織たるわれわれの日常活動(大衆運動と大衆工作、政治運動と政治工作、直面する闘争と課題、団体と組織への指導工作等)においては、その独自的任務と責任を完全に全うしなければならない。とくに経済建設、組織建設、社会建設など、常に緊急課題の遂行を任務とする行政執行機関と組織の活動とは併立した独自性を発揮しなければならない。これは権力執行の二本足であり、その一方における決定的な側面である。レーニンが確立した社会主義建設期の党とはまさに二本足の中の思想・政治部門(コミッサール)であった。ソビエト社会主義がフルシチョフの裏切りを防止できず内部から崩壊したこと。そして中国革命も鄧小平の裏切りで内部から変質して敗北したということ。歴史科学からみて避けられなかったとはいえ社会主義と共産主義運動上の教訓と課題がここにもあったのだという原理と法則を忘れてはならない。
第4節
マルクスが提起し、レーニンが実現した、社会主義建設勝利のカギとなる、プロレタリア独裁(労働者階級と人民の支配とその権力)の物質的表現たる「評議会」(ソビエト)の思想的(理論的)意義をしっかりつかみ、これを堅持し、これに依拠して権力を執行せよ!
プロレタリア独裁とは何か?
プロレタリアとは働く労働者階級のことである。プロレタリア独裁とはその労働者階級と人民大衆(巨大独占資本の支配に収奪されている非独占的中小商工業者、農民、多くの人民)の同盟にもとづく支配体制・支配権・その国家権力のことである。だからこれは個人的独裁ではない。階級的支配権のことである。巨大独占資本主義(ブルジョアジー)が、彼らの支配政党たる政治勢力を使って実現するその階級的独裁支配に反対し、これを覆し、それにかわって労働者階級と人民の支配権を打ち立てるもの、これがプロレタリア独裁である。故にこれは階級闘争と階級支配の道具なのである。
プロレタリア独裁というのはマルクスによって提起された学説・理論上の表現であり言葉である。マルクスがはじめてこのことを提起したのは『共産党宣言』(一八四八年)であった。マルクスはつぎのように言っている。「社会主義実現の第一歩は労働者階級の支配権を打ち立てることである。労働者階級の権力を利用して、資本主義的生産関係を一歩一歩社会主義的に変革する。こうした革命的変革の手段としてプロレタリア独裁がある」(大月版マルクス=エンゲルス全集、第四巻)
そしてマルクスが正確に、理論上の表現として「プロレタリア独裁」を使ったのは一八五〇年に執筆した『フランスにおける階級闘争』であった。この中でマルクスはつぎのように書いている。「プロレタリ革命と社会主義の実現は、人類社会における階級制度の廃止と、階級的諸観念の変革に到達するための必然的通過点としてのプロレタリアートの階級的独裁である」と。
つづけてマルクスは『ゴータ綱領批判』(一八七五年)のなかでつぎのように書いている。「資本主義社会から共産主義社会に到達する過程には社会主義をふくめて、政治的、社会的な過渡期がある。この時期に存在する国家とは、必然的にプロレタリアートの革命的独裁以外のなにものでもありえない」と。
エンゲルスもまたマルクスと同じことを言っている。エンゲルスが一八七五年三月十八日から二十八日にかけて友人のアウグスト・ベーベルに送った手紙の中でつぎのように書いている。「プロレタリアートがまだ国家を必要とするあいだは、プロレタリアートはそれを、自由のためにではなく、その敵を抑圧するために必要とするのです。本当に自由となったとき、もはや国家としての国家は必要でなくなり、国家は存在しなくなります」と。
だからレーニンはつぎのように断定した。「ただ階級闘争をみとめるだけではマルクス主義者ではない。階級闘争の認識をプロレタリアートの独裁の認識にまでおしすすめる人だけが真のマルクス主義者である」(一九一七年八月『国家と革命』)と。
そしてまたレーニンはつぎのように言う。「権力手段と権力機関をにぎっている暴圧者に対する暴力なしには、人民を暴圧者から解放することはできない。……そしてこのプロレタリア独裁にもとづく新しい権力は空から降ってくるのではなく、旧権力と併行して、旧権力に対抗して、旧権力との闘争のなかで発生し、成長する」(『独裁の問題の歴史によせて』一九二〇年十月)と。
そしてこのプロレタリア独裁は、真のマルクス主義的前衛政党なしに、これをぬきにしては成り立たない。マルクスはつぎのように言っている。「共産主義者は、実践的には、すべての国の労働者諸党のうちで、最も進歩した、断固たる、たえず推進していく部分である。理論的には、プロレタリア運動の諸条件、その進路、その一般的結果を理解している点で、残りのプロレタリアートの大衆的前衛である」(『共産党宣言』第二章「プロレタリアと共産主義者」一八四八年)と。
そしてレーニンもまたつぎのように言う。「歴史上ただ一つの階級も、運動を組織し、指導する能力のある自分の政治的指導者たち、自分の先進的代表者をおくりだすことなしに支配権を獲得したものはない」(『われわれの運動の緊要な諸任務』一九〇〇年十一月)と。
またレーニンはつぎのように言う。「プロレタリアートの独裁の本質、その主要な本質は、労働者階級の先進部隊、その前衛、その唯一の指導者であるプロレタリアートの組織性と規律とにあるのです。プロレタリアートの目的は、社会主義を創建し、社会の階級分裂を廃止し、社会の全成員を勤労者に変え、人間による人間のいっさいの搾取の基盤を取り除くことです」(『ハンガリアの労働者への挨拶』一九一九年五月、大月版レーニン全集、第二九巻)
そして最後にレーニンはわれわれに決定的な思想原則を提起した。レーニンはつぎのように強く主張した。「革命的理論なくして革命運動はありえない。流行の日和見主義の説教と、実践活動のもっともせまい形態への心酔とが抱合しているような時代には、どれほど強くこの思想を主張してもなお足りない。先進的な理論に導かれた党だけが先進的な役割をはたすことができる」(『何をなすべきか?』一九〇一年―二年)と。
プロレタリア独裁の物質的表現としての評議会(ソビエト)
「プロレタリア独裁とは何か?」については以上のとおりである。この原理・理念・理論に従って実践し、行動し、現実の社会主義革命と社会主義建設を実現させる物質的なもの、その力、その武器、その体制こそまさに「評議会」(ソビエト)である。それは歴史上はじめて実現されたロシアにおける社会主義革命とレーニンによって出現した人類史上初のプロレタリア独裁の物質的形態とその表現であった。
一九〇五年に発生したロシアにおける第一革命は、一九一七年に勝利したロシアにおける社会主義革命の予行演習であった。一月十六日、ペテルブルグのプチロフ工場におけるストライキと一月二十二日の「血の日曜日」から開始され、六月二十七日の戦艦ポチョムキンの反乱から、十二月二十三日から三十日にかけての武装労働者の蜂起と政府軍との市街戦、政府軍による鎮圧、というこの革命戦争の中でソビエトは生まれた。
十月二十六日、ペテルブルグのプチロフ工場に最初の労働者代表ソビエトが結成され、それはモスクワ、バクーなどロシアの主要都市に拡大された。工場毎のソビエトは地域ソビエトへ、産業別ソビエトへと進んだ。労働組合、非組合員、政党、政派、宗教に関係なく、そこで働き、そこで生活しているすべての人びとの共通の意志によって決議され、承認された、真に大衆を代表する機関としてのソビエトであった。このモデルは軍隊にも波及し、「兵士代表ソビエト」が軍内に、そして農民の間には「農民ソビエト」が生まれた。こうしてレーニンとボリシェビキの指導のもとに、全ロシアに、地域ソビエトから、全国ソビエトへと広がった。これを拠点に、一九一七年十月の社会主義革命では「全権力をソビエトへ!」という統一スローガンにもとづくロシア社会主義革命へと成長転化したのである。
事実が証明したとおり、「評議会」とは、人民大衆による「直接民主主義」の形態である。そこで働く、そこで生活する人民大衆が生産点と生活点で、共通の意志と、共同の認識を集団の意志と政策として集約し、これを機関としての「評議会」で確認し、権力の意志として執行していく。これである。
レーニンはロシアにおける第一革命から学んで、十月革命の直前の一九一七年八月―九月に『国家と革命』という論文を発表したが、その中ではっきりとつぎのように書いている。「二十世紀初頭の帝国主義段階におけるプロレタリア革命はパリの労働者が生み出したコミューン型でなければならない。そのロシアにおける具体化がソビエトである」と。
そしてレーニンはロシア革命の勝利後の一九一九年三月に創立された第三インタナショナル(コミンテルン)の第一回大会での開会の辞でつぎのように言う。「わがソビエト制度はプロレタリア独裁を実現するその形態である。プロレタリア独裁というこの言葉は今まではラテン語だったが、ロシア革命の勝利によってそれはソビエトという現代語に翻訳されるに至った。ここにプロレタリア独裁の実践的形態がある」と。
さらに一九二〇年七月に開かれたコミンテルン第二回大会で採択されたコミンテルン規約ではつぎのような一節が確認されている。「共産主義インタナショナルは、プロレタリアートの独裁をもって、人類を資本主義の支配から解放する唯一の可能な手段であると考える。そして共産主義インタナショナルは、ソビエト制度をもって、プロレタリアートの独裁の歴史的形態であることを確認する」と。
マルクスが提起し、レーニンが実現した労働者階級と人民の支配、その権力とは、まさに「評議会」という直接民主主義であり、愚民主義とごまかしの議会主義ではないことをはっきりと確認しなければならない。
投票による議会主義とは、愚民政治であり、衆愚政策であることをしっかり確認せよ。
資本主義から社会主義への変革、社会主義建設期の国家のあり方、そのための労働者階級と人民の支配権としてのプロレタリア独裁の本質とその形態、などは以上で明らかになったとおりである。そこでいつも問題になるのが議会主義についてである。ブルジョア自由主義とブルジョア政治の見本であるこの議会主義と議会政治について、労働者階級と人民はどう考えるのか。はっきりしているように、これはまさに愚民政治、衆愚政策そのものであり、ブルジョア独裁とその権力支配の本質を覆いかくす鎧(よろい)の上の衣なのである。
この問題について、前記、コミンテルン第二回世界大会の『議会に関するテーゼ』では明確につぎのとおりに規定されている。「独占と帝国主義の今日的条件のもとでは、議会は虚偽や欺瞞や暴力やおしゃべりのための道具となってしまった。……共産主義者にとっては、今日では、議会は、どんな事情のもとでも、かつて以前の時代にそうであったように、労働者階級の運命を好転させるための手段とはなりえない。政治生活の重心は、決定的かつ終極的に、今では議会の外に移ってしまった。……したがって、この機関を支配階級の手から奪取し、それを破壊し、全廃し、そのあとに新しいプロレタリアートの権力機関を置き替えることは、労働者階級の当面の任務である。……プロレタリアートの独裁のとるべき形態はソビエト共和制である」と。
レーニンが右のように、明確に規定するとおり、ブルジョア的愚民政治の見本たる議会主義に迷わされてはならない。ブルジョア権力は常に議会の外で、「政・官・財の癒着構造」、「ステルス複合体」(中川秀直著『官僚国家の崩壊』)によってすべては執行されている。これに対抗するにはプロレタリア独裁としての「評議会」以外にはない。
投票によって政府や政治家を選ぶという方法が出現したのは紀元前五世紀の古代ギリシャであった。ギリシャには当時多くの都市国家(ポリス)が生まれたが、その中のアテネは早くから市民参加型の政治が発展し、やがて投票によって政治指導者を選ぶ方法が採用されるに至った。そして投票用具に用いられたのが陶器の破片であった。投票の結果、市民に人気のない指導者は追放された。そこから歴史上「陶片追放」という言葉が生まれた。結果としてこの制度は、結局は人気投票となり、そこから大衆迎合(ポピュリズム)という悪しき風習が作り出されてしまった。そしてそこからこの方法は政治指導者や、政党間にとって人気取りの政争道具になってしまった。アテネでは政治の無能力と分裂を生み出し、国力は低下し、やがて隣国のスパルタに敗北してしまった。
しかしこの制度は大衆支配の手段、ブルジョア自由主義の装飾物として、より巧みに引き継がれていくのである。つまりは大衆の理性・自覚ではなく、その本能を利用し、本能を駆り立て、自由主義を叫びたて、風の吹くまま、気の向くまま、行き当たりばったり、そのときの個人的感情によって誰かに投票するという、まさに無政府主義、愚民主義、衆愚主義という、ブルジョア政治の根幹になってしまったのである。
ここで改めて、はっきりと、投票とは何かということを考えてみなければならない。選挙と投票に人びとを駆り立てる行動、何が人びとを投票に行かせるのか。それはあくまでも個人の自由主義、自由行動なのである。すべて個人的事情が根底にある。その契機となるものは、あるときは気の向くままであり、そのときの気分であり、風の吹くままであり、付和雷同である。ある人にとっては個人的知り合い、同郷の人、学閥、同好会、宗教心、名誉欲、そして金であり、物品であり、強制である。ここに個人行動と自由主義と無政府主義がある。だから投票というのは、大衆の後れた部分、社会と切り離され、孤立した個人、個人的幻想と錯覚と夢想にもとづく行動であり、ここに愚民性と衆愚性の本質がある。
そういう愚民政治・衆愚政治の生きた実例、歴史上の実例はブルジョア議会政治のいたるところに、日常茶飯事として山ほどあるが、大きな、代表的でわかりやすいものとしてナチス・ドイツのヒトラーと、国内的には田中角栄の例に見ることができる。あの第二次世界大戦を引き起こした元凶たるナチスとヒトラーの出現はドイツ国民議会が生み出したのである。一九三三年十二月に実施されたドイツにおける議会総選挙、ナチスとヒトラーへ全権委任するための総選挙では実に九六%の投票率と九二・二%の得票率という、世界史上最高の投票結果からナチスとヒトラーは生み出されたのであった。そして、日本の総選挙史上最高の勝利を得たものは、一九八三年十二月総選挙で田中角栄が得た二十二万票、四六・五%という史上最高の得票であった。しかもそれは、日本史上はじめての現職総理大臣の疑獄事件(ロッキード事件)で有罪判決を受けた直後の、いわゆる「ロッキード総選挙」で、国内世論の八〇%が田中退陣を求めるという社会風土の中での出来事であった。こういう歴史上の事実が証明しているように、投票による議会主義というものが、いかに愚民政治、衆愚政治であるかということをわれわれはよく知らねばならない。これはブルジョア政治の出現以来続く伝統であり、ブルジョア思想に毒された人間には理解されないが、歴史は労働者階級と人民によって必ず打破される。
そしてまた、選挙における投票率も考えてみればならない。あらゆる選挙をみればわかるとおり、平均すれば五〇%の投票率である。だからそのなかの七〇%を獲得して第一党となったとしても、政権をとったその政党は全有権者(全国民)の三五%しか代表していないのである。これが大衆参加、国民の支持、選挙での勝利といえるのか。民主主義という名に値(あたい)するものだろうか。否である。ここにも愚民性、衆愚性がある。
真の民主主義とは、自覚された人民大衆の共同の意志、共通の認識、協同行動にもとづく政策の確立と確認、である。人民大衆は、生産点、生活点、つまり労働と生活の中で、互いに協力し、共同し、共通の要求にもとづく運動と闘いの中で、連帯し、交流し、自らのコミュニティーを作り上げていく。ここに真の民主主義がある。その集大成されたものこそ「評議会」である。
最後に一言付け加えておきたいのは、マルクス主義のこの根本理論を忘れて、ブルジョア議会主義という、愚民主義、衆愚政策におぼれた結果、自らもブルジョア政党に堕落してしまった社会主義(共産主義)政党が歴史上たくさん出現した例(ユーロコミュニズム、日本の宮本修正主義、ロシア、中国の修正主義、その他)を絶対に忘れてはならない。
プロレタリア独裁に関するレーニン主義を忘れてはならず、堅持せよ。
ロシア革命とソビエト社会主義に実際に勝利したレーニンは、『何をなすべきか?(1902)の中で、プロレタリア独裁の思想的原則を次のように述べている。
◎理論と実践の堅固な統一(革命理論に導かれた実践活動の発展)。
◎プロレタリア独裁と民主主義の統一(プロレタリア独裁の理論とイデオロギーを堅持し、そのために必要な民主的方法を採用する)。
◎戦略と戦術の統一(一貫した戦略目標の追求と、情勢・状況に応じた多様な戦術の実行)。
目的と手段の統一(目的を明確にし、それを達成するために必要な、その時点で採用すべき戦術を策定する)。
◎必然性と偶然性の統一(目標や目的への必然的な道筋は、必ず偶然に遭遇する。偶然を必然に変える決定的な力は、指導者の決意と勇気である)。
以上のように、すべてはこの二つの側面の統一に鍵がある。すべては相反するものの統合である。この2つを分断したり、一方に偏ったりしてはならない。そうなれば、存在は消滅する。ここにも哲学がある。
第5節
われわれはレーニン、スターリンの偉大なソビエト社会主義建設の勝利とその成果を〝止揚〟しなければならない。つまり、その原則的で基本的な勝利の部分を断固として継承する。同時にその時代には解決し勝利に至らなかった部分は、後継者たるわれわれによって必ず解決し、新しいものを付け加えて完成させる、ということである。これが哲学原理と科学法則たる〝止揚〟である。
哲学的・科学的法則の原理は "止揚 "である。
マルクス主義の思想的原理は哲学であり、それは〝弁証法的唯物論〟である(<学習のすすめ>第五回、第三節・マルクス主義哲学の項をみよ)。その核心は、すべては物質運動であり、思想・政治・イデオロギーもこの物質運動と結びついており、その反映である。
マルクス主義、社会主義、共産主義運動も近代労働運動、資本主義社会における階級闘争と結びつき、その物質運動の一系列の物質運動としてマルクス・エンゲルス・レーニン・スターリンの社会主義が存在している。
その発展と前進の核心は〝止揚〟である。つまりは古いものを土台に、これを引き継ぎつつ、その中から新しいものを生み出していく、ということである。ここに弁証法の運動法則がある。
この弁証法的唯物論の科学的・哲学的原理から出発するとき、マルクス主義、社会主義、共産主義運動の発展と前進は、まさに、レーニン、スターリンの社会主義を〝止揚〟すること、つまりは、レーニン、スターリンの偉大な社会主義建設の勝利とその成果を断固として継承しつつ、その時代では解決できなかったことについては、後継者たるわれわれが必ず解決する、ということである。この哲学・科学法則に違反したものは、哲学原理たる「否定するものは否定される」という法則どおりに、必ず歴史によって否定されていく。これはマルクスを否定したブルードン、ブランキ、ラッサール、バクーニンのごとく、レーニンを否定したカウツキー、スターリンを否定したフルシチョフとその同伴者たるユーロコミュニズムなどを見れば明確である。すべては科学的法則なのである。
この哲学的・科学的法則にもとづいて、われわれはここに、レーニン、スターリンの社会主義をいかに〝止揚〟すべきかを明確にしたい。
▼ すべてはプロレタリア独裁が決定する。
マルクスが理論的に提起し、レーニンが実際にこれを実現し、スターリンが忠実にこれを継承したその内容については、<学習のすすめ>第十五回・第五節・(四)の項でくわしく展開されている。理論と実践の両面から論じられているこの内容をよく学び、忠実に実践するところにすべてのカギがある。いつ、いかなるときでもこの思想を離さず、忠実に実行、実践することは正統マルクス主義者にとっては義務であり、生命線である。
▼ プロレタリア独裁の執行にあたっては必ず二本足で歩くことを忘れてはならない。
この問題に関しては<学習のすすめ>第十四回、第五節・(三)の項でくわしく論じられている。この二本足の権力執行は、レーニンがロシア革命勝利直後の一九一八年から一九二二年まで五年間にわたる外国干渉軍と国内反乱軍との間の過酷な戦いの中で生み出した「軍事コミッサール」(政治委員)制度が基本となり、やがて社会主義建設におけるソビエト制度の根幹となった。われわれは権力機関における、実務行政機関と政治・思想部門という、二つの機能を補完させるというレーニンのこの教えを忠実に守って実行しなければならない。
▼ 社会主義経済建設の方法は計画経済であり、ここに目的・意識性がある。
この問題に関しては<学習のすすめ>第十二回、第五節・序論の項で、マルクスとエンゲルスがその著作の中で展開した計画経済論の中でくわしく展開されている。そしてレーニンはマルクスの教えにもとづいて、一九二〇年十二月の第八回全ロシアソビエト大会の決議にもとづいて「ゴスプラン」(ソビエト連邦閣僚会議国家計画委員会)を組織し、社会主義計画経済にとりくんでいったのであり、これはそのままスターリンの計画経済へと引き継がれていった。この社会主義計画経済の優越性と実際に勝利したその歴史的事実については<学習のすすめ>第十二回、第五節・(一)の項でくわしく紹介されている。これらの理論と実践の両面から社会主義計画経済についての優越性を深く認識しなければならない。
▼ レーニン、スターリンの社会主義建設勝利の八項目の経験と教訓を継承せよ。
先に明らかにしたとおり、社会主義建設における勝利の基本法則は、プロレタリア独裁であり、プロレタリア独裁の執行における二本足であり、そして目的・意識性としての計画経済であった。これらの基本原則のもと、特に注目し、特に意識的に継承しなければならないのはつぎの八項目である。
① 労働者階級の党、共産党のボリシェビキ的純化であり、理論上の原則にもとづく党の思想的・政治的統一の保持であり、鉄の団結である(一九二一・三~第十回党大会決議)。
レーニンはすべては党にあり、その党は理論的、思想的、政治的に純潔でなければならず、そのことを基準にした鉄の統一と団結が生命であると強く主張した。
② 思想と政治が国家を支配し、思想と政治が人民大衆を動員し、思想と政治が経済を支配する。一九一八―一九二二年にわたる外国干渉軍と国内反乱軍との内戦に勝利した「戦時共産主義」と、そのあとの荒廃した国土を再建した「共産主義土曜労働」、そしてレーニンの「ネップ」(新経済政策)であった。
③ 「社会主義とはソビエト権力プラス全国の電化である」(一九二〇・十二~第八回全ロシアソビエト大会でのレーニンの演説)。レーニンは社会主義経済建設勝利の最大課題は全国の電化であり、農業もふくめた全産業の電化、機械化、重工業化、科学技術の向上にあると演説「全ロシア電化委員会(ゴスプラン)」を設立、自ら責任者となった。
④ 「ネップ」の正しい思想的・政治的認識にもとづく実践である。つまり、農業、農民問題(中小ブルジョアジー)に対する社会主義政策は、教育(言って聞かせ)と実践(やってみせる)、そして自覚と認識に応じて着実に共同化―社会主義化を実現する(やらせる)ことであった。
⑤ プロレタリア国際主義の実現としての第三インタナショナル(コミンテルン)の創設である(一九一九・三)。国際的革命運動の勝利なしに社会主義の最終的勝利はない。
⑥ 社会主義とは目的・意識的な計画経済である(一九二九・四~ソビエト共産党第十六回党会議でのスターリンの演説)。第一次五カ年計画(一九二八―一九三二)から連続した計画経済によって国の重工業化を達成、この力が第二次世界大戦を勝利させた。
⑦ 社会主義建設とは新しい形の階級闘争、政治闘争であり、その力は人民大衆の思想的・政治的動員であり、それは真の社会主義競争として「スタハノフ運動」に実現された。レーニンの「共産主義土曜労働」の再現がここにあった(一九三五・十一~第一回スタハノフ運動全国大会におけるスターリンの演説)。
⑧ 最後はカードル(幹部と活動家)が決定する。ロシア的革命精神(思想)と、アメリカ的実務能力(科学技術)の結合した幹部と活動家の配置がカギとなる(一九三五・五~赤軍大学卒業式でのスターリンの演説)。
以上。これがレーニン、スターリンの真正社会主義の四十年が生み出し、実現した社会主義建設である。われわれはこの歴史的遺産をしっかり守り、維持し、さらに発展させねばならない。
第6節
レーニン、スターリンの偉大な社会主義を〝止揚〟すべきもう一つの側面たるもの、すなわちレーニン以後の社会主義運動が、歴史上の制約によって未解決となった諸課題、そして歴史がわれわれにそれを解決し、マルクス主義運動をさらに発展、前進させるよう託し、止揚させるよう求めた課題とは何か!
<学習のすすめ>・第三章・(四)の項・哲学でくわしく論じたとおり、万物の運動法則、その弁証法的発展の法則の中の重要項目には〝止揚〟という法則が提起されている。具体的にはそれはどういうことかについて<学習のすすめ>第五節・(二)の項でくわしく論じられている。それはつまり、過去(歴史)を引き継ぎつつ、その中の前進的・発展的な核心を擁護すると同時に、歴史的にみてまだ未解決で、まだ達成できなかった諸課題は、後継者たるわれわれの手によって必ず解決し、達成する、ということであった。だから〝止揚〟にも二つの側面があるのである。
そしてその二つの側面の中のレーニン、スターリンの社会主義建設について継承すべき課題については前項第五節・(四)・(五)で明らかにした。
したがってこの(六)の項では、〝止揚〟のもう一つの側面たるレーニン以後(スターリン、毛沢東時代)の歴史では未解決となり、未達成となっていたいくつかの課題について明らかにする。もちろん、歴史的には、将来、国際的に、新たなインタナショナルのなかで、大いに議論し、討論されるべき問題であることは明らかである。そのためにこそわれわれはここでわれわれの見解を明らかにしておきたい。その止揚すべき歴史の一ページに付け加えるべき課題はつぎの諸点である。
①、社会主義建設を最終的に勝利させるカギはプロレタリア独裁である。故にその理論上の原則は忠実に守り、忠実に実行しなければならない。
社会主義運動、共産主義運動、革命運動の勝敗を決定づけるものはまさにプロレタリア独裁の理論と実践である。
このことについては<学習のすすめ>第五節・(四)の項でくわしく提起されている。理論的に、実践的に、具体的に提起されている。
特にブルジョア議会主義の欺瞞性について徹底的に明らかにし、評議会(ソビエト)こそプロレタリア独裁下における直接民主主義、真の民主主義であることをくわしく論じられている。だから投票や選挙というものはブルジョア的愚民主義、衆愚政策である。このことから社会主義政権がこの愚民主義と衆愚政策を実行すれば、そこから、その党がブルジョア政党に堕落するのである。
だから真の社会主義党はこのプロレタリア独裁の理論と実践を忠実に守りぬかねばならなかった。
②、プロレタリア国際主義、その具体化であるインタナショナルをあくまで守りぬき、忠実に実践しなければならない。国際主義を忘れると民族主義に堕落することを知らねばならない。
マルクスとエンゲルスは『共産党宣言』の最後の結びのスローガンに『万国の労働者団結せよ!』と書いた。この一言の中にマルクスとエンゲルスの万感の思いが凝縮されている。
そしてマルクスとエンゲルスはその具体化、その実践活動としてインタナショナルの結成、組織化、その運動を一貫して指導した。一八六四年九月二十八日に創立された『国際労働者協会』(第一インタナショナル)の創立宣言はマルクスが執筆したが、その中では強くつぎのことが強調されている(大月版「マルクス=エンゲルス全集」第十六巻)。
「さまざまな国の労働者は兄弟のきずなで結ばれ、このきずなに励まされて、彼らのあらゆる解放闘争でしっかりと支持し合わなければならないのであって、この兄弟のきずなを無視するときには、彼らのばらばらな努力は共通の挫折という懲らしめを受けることは、過去の経験が示しているところである」と。
レーニンはマルクスの教えを忠実に守り実行した。一九一七年にロシア革命が勝利するや、早くも一九一九年三月に「第三インタナショナル」(コミンテルン)を結成して、全世界の革命運動の連帯と統一を実現した。そしてレーニンはつぎのように主張した。
「プロレタリア国際主義は第一に、一国のプロレタリア的闘争の利益を世界的な規模のプロレタリア的闘争の利益に従属させることを要求し、第二に、ブルジョアジーに対する勝利を実現しつつある民族に対しては、国際資本を打倒するために最大の民族的犠牲をも甘受する能力と覚悟を持つことを要求する」(一九二〇年『民族植民地問題に関するテーゼ原案』)と。
③、農業(農村)の社会主義化(中小ブルジョアジーの社会主義化)については、マルクス主義の理論上の原則を守り、レーニンの実践から学ぶ。そして「内容の独裁・方法の民主主義」という政治手法(作風)をしっかりと実行しなければならない。
まず最初に、社会主義とは何か、その原理から出発しなければならない。このことについてエンゲルスは、一八四七年に書いた『共産主義の原理』のなかでつぎのように言っている。人間社会における真の自由と民主主義、真の平等と公平と人間性の豊かさは、国家と社会そのものが協力と共同のコミュニティーでなければならず、生産活動もまた個人主義ではなく、社会的欲望(社会の需要)に答えられる目的・意識的、計画的生産、計画経済でなければならない、と。
エンゲルスはまた、一八八〇―八二年に書いた『空想から科学への社会主義の発展』の中でつぎのように言っている。社会主義的計画経済を通じて、工業化、機械化、科学技術が発展し、生産力が高度に発達したとき、工業と農業、都市と農村、知的労働と肉体労働の差がなくなったとき、そのとき高度なコミュニティーとしての共産主義に到達する。そのとき国家は「廃止」されるのではなく「死滅する」のである、と。このエンゲルスが言っていることの本質はつぎの点である。つまり、人類社会の最終的到達点はコミュニティーであり、共同化であり、協同化である。そのための土台としての経済建設においては、すべての生産活動(特に農村において)の機械化、近代化である。機械化、近代化こそが、都市と農村、肉体労働と知的労働、工業と農業の差を解消していく。
ところで、都市と鉱工業における社会主義化は農業と農村にくらべると相対的に容易である。それは都市と鉱工業部門はその必然性から機械化と近代化が大いに進むものであり、客観的には社会化、社会主義化されている。それに対して農業と農村においてはその歴史性と社会性から、機械化と近代化は非常に遅れており、極めて個人主義的で孤立的で、農民や中小ブルジョアジーは社会的に大きく立ち遅れている。したがって労働者階級の政府と権力は、この中小ブルジョアジーに対する政策と指導方法には十分な注意が必要なのである。
この問題についてエンゲルスは、一八九四―九五年に『ノイエ・ツアイト』に発表した論文『フランスとドイツの農民問題』の中でくわしく論じている。ここで注意しなければならないのは、エンゲルスの論文は農民問題を論じながら、基本的には中小ブルジョアジーの社会主義化について論じているのである。エンゲルスはこの中でつぎの基本点を強く主張している。
第一に、ブルジョア大地主(不在地主)の土地はこれを没収して国有農場とする(レーニンはソビエト時代、これをソフホーズとして、小農、農村プロレタリアを結集し、機械化された大規模国営農場とした)。
第二に、中小地主の土地は没収せず、説得と教育と国営農場の実地見聞にもとづいて、自らの自覚にもとづく共同化、協同組合をめざす(レーニンのソビエトでは、コルホーズ、協同組合的集団農場として社会主義化を進めた)。
第三に、小農や農村プロレタリアは共同化農場に結集する以外に生きる道はないのだということを認識させ、自覚させ、国営農場か、協同組合農場かを自らの意志として決定させていく(レーニンのソビエトでは、コルホーズか、ソフホーズか、いずれかに組織されていった)。
これがマルクスとエンゲルスが理論化し、レーニンが実践した農業と農民(中小ブルジョアジー)に対する社会主義政策なのである。
ソビエト社会主義における農業・農民問題についてレーニンは多くの指針を発表しているが、それはすべてさきに明らかにしたエンゲルスの三項目にわたる基本方向を堅持し、その具体化へ向けたものであった。つまりは、農民への社会主義思想の宣伝教育を十分に行うこと(言って聞かせる)。そして小規模経営ではなく、共同化された、大規模農場こそが農民の生きる道なのだということを、ソフホーズを通じて実際に見聞させ、体験させた(ソフホーズという国営農場を作って見せた。つまりはやってみせた)。そうして一歩一歩、自らの力で共同、協力を推し進めた。レーニンの実行した作風は、言って聞かせ、やってみせ、そのうえでやらせる、という、徹底した民主主義の実践であった。つまりは「内容の独裁(社会主義は実行する)、方法の民主主義(そのための手段と方法は民主主義を徹底的に運用する)」というマルクス主義党の作風であった。
一九一七年五月十二日に開かれた、農民代表第一回全ロシア大会における演説でレーニンはつぎのように言った。「共同化、協同組合化は非常に困難な仕事である。このような協同組合化を上からの決定として押し付けることができると考えるとしたら、それは気狂い沙汰というものである。なぜなら、幾百年にわたる個別経営の習慣は、いっぺんに消えてなくなるものではない。多くの時間が必要なのである」と。
またレーニンは一九一九年三月に開かれた、ロシア共産党(ボリシェビキ)第八回大会での、農業・農民問題に関する演説のなかでつぎのように語っている。「農業のすべての基礎を改造する仕事は長くかかる仕事である。農業における変革を上からおこなってはならない。農村の社会主義化を、力ずくでやることほどばかげたものはない」と。
そしてレーニンは一九二〇年十二月に開かれた第八回全ロシアソビエト大会の席上「社会主義とはソビエト権力プラス全国の電化である」と演説したが、これはすべての産業、農業と農村における社会主義の勝利の土台は、電化、機械化であることを訴えたのである。農業における機械化、近代化によって、都市と農村の格差をなくすることによって、社会主義的生産活動、生産力は発展し、前進するのである。農業と農村における社会主義の勝利に関するエンゲルスとレーニンの教えをわれわれは絶対に忘れてはならない。
結語
人類の歴史は、哲学・科学的真理たるマルクス主義が示す法則に従って進む以外にない。そして二十一世紀の歴史時代はこのことをはっきりと今証明している。そのためにこそ歴史は絶対的真理としてのマルクス主義の純化、浄化、原点からの再出発を求めている。歴史はあくまで必然性をもって、到達すべきところに必ず到達するであろう!
二十世紀における人類史上最大の事件は、ソビエト社会主義の崩壊と、それにつづく社会主義・共産主義運動の退潮と衰退、そして全世界の左翼運動の消滅であった。世界中に「歴史の終わり」という言葉が広がった。
このときわれわれ正統マルクス主義者は、慌てず、焦らず、泰然自若として歴史に立ち向かった。われわれ正統マルクス主義者は、歴史を科学としてとらえることを知っており、すべては科学的法則によって歴史は動くことを知っているからである。宇宙のはじまりから地球と人類の誕生、人類社会の歴史的発展法則(原始時代―奴隷制―封建制―資本主義―独占と帝国主義―帝国主義の崩壊からコミュニティーへの発展法則)を知っているからである。現実に、いま、アメリカ帝国主義はイラク戦争を通じて崩壊しており、以後の世界は混乱と動揺と激動を通じて、コミュニティーをめざす。現代の戦争と内乱、対立と抗争、テロと暴動はみな、そのための産みの苦しみであり、こうして人類は最終目的に向かっていく。ビッグバン以降の宇宙と地球と人類の歴史はみな、そのような歴史だった。
マルクス主義はこのような人類史の総括であり、その哲学・科学的発展法則の体系化である。このマルクス主義の基本原理、基本理念、基本原則を、改めて明確にしたものこそ<学習のすすめ>と題する、全五節にわたる正統マルクス主義の基本文献である。
この全五節にわたる、マルクス主義に関する基本原理、基本理念、基本原則の展開は歴史の産物である。歴史がマルクス主義の最終的勝利のために、その浄化と純潔を求め、マルクス主義の原点から社会主義・共産主義運動の再出発を求め、新たなマルクス主義運動の復興を求め、そのための指針として生み出されたものである。
<学習のすすめ>の全五節の中にマルクス主義の原理、理念、原則があり、ここにマルクス主義の浄化と純潔、原点がある。歴史は必然性をもって、この道に従って社会主義・共産主義運動を力強く再出発させ、勝利させるであろう。
われわれは結語の最後に呼びかける。<学習のすすめ>の全五節をよく読み、偉大なマルクス主義の歴史的勝利に確信をもとう!
この全五節の核心たる〝止揚〟をしっかり認識する。歴史は止揚されるものであり、止揚なき歴史はすべて歴史によって否定されるであろう!
〝止揚〟における二つの側面をよく知り、その肯定的止揚と、否定的止揚をよく知り、特に歴史の教訓として否定的止揚をよく学べ!
歴史を止揚せよ、止揚せよ、そして止揚せよ!
人類の未来展望とそのスローガン
私たちは、すべてを哲学的・歴史的・科学的な世界観でとらえることを求めます。私たちは一貫して、次のような科学的世界観・歴史科学観を提起する。
① 人類とその社会は永遠の過去から永遠の未来に向かって運動し、発展し、爆発し、収れんされつつ前進していく。そのエネルギーは人間の生きる力であり、その物質的表現としての生産力である。
② 生産力の発展がその度合いに応じて生産関係としての人類社会(国家)を作り出していった。それは最初の原始共同体、次の奴隷制、封建制、資本主義制、そして社会主義へと一貫して生産力の発展が生産関係(国家)を変化させていった。これからもそうなる。
③ 物理学が証明しているとおり、すべての生物は環境が作り出していく。人類もまた環境の産物であり、進化していった。環境が人間を変えていく。新しい環境と新しい社会は新しい型の人間を作り出していく。
④ 人類の歴史を見ればわかるとおり、一つの支配権力、一つの国家形態が永遠であったことは一度もない。歴史は常に運動し、変化し、発展し、転換して次々と新しい時代を作り出していった。そして歴史を見ればわかるとおり、変化は静かで一直線ではない。爆発と収れんは歴史法則である。歴史は必然を持って前を目指すが、その過程では常に偶然が伴う。偶然は必然のための産物であり、偶然は必然のための糧である。そして必然の世界とは人民の人民による人民のための世界であり、より高度に発展したコミュニティー社会である。歴史は到達すべきところに必ず到達する。
⑤ コミュニティーとは何か。人民による人民のための人民の世界とは何か。それは国家、社会、生産活動の運営目的を、最大限の利益と利潤追求のみに注ぐのではなく、すべてを人民の生活と文化水準と社会環境の安心・安全・安定のために注ぐ。
⑥ 生産第一主義、物質万能主義、拝金主義、弱肉強食の国家と社会ではなく、人間性の豊かさと人間の尊厳と人間としての連帯と共生の国家と社会にする。
⑦ 金と物がすべてではなく、人間の心と自然の豊かさが第一であり、姿や形だけの美しさではなく、働く人びとの生きる姿と心の美しさが第一であり、一人だけで急いで先に進むのではなく、遅くてもみんなが一緒に進む。
⑧ 人類とその社会は生まれたときから環境の産物であり、歴史的なものであった。環境が変われば人類とその社会も変わる。国家と権力が変われば人類社会は変わる。
⑨ そのための力こそ、すべてを人民のための・人民による・人民権力であり、その具体的表現たる人民評議会である。運動と闘いの中でいたるところに評議会を組織せよ。人民の要求、人民の意志としてここで主張する。そして権力として、歴史時代が求める自らの責任と任務を執行させる。
⑩ 人類が最初にはじめてつくった社会は、原始的ではあったが、そこにはまさに共同と共生と連帯の人間的社会があった。そしていくたの回り道をしたが、その間により大きくなってもとに帰る。つまりより高度に発達した近代的コミュニティー国家と社会へ。ここから本当の民主主義にもとづく人間社会、人民の社会が生まれる。こうして人類は総力をあげて大宇宙との闘い、新しい闘い、宇宙の開発と開拓の闘いに進軍するであろう。
(おわり)
《後書》
日本共産党(行動派)・大武礼一郎議長は、「人民戦線の旗のもとに」2007年2月25日号から17回・全5章にわたって「学習のすすめ」と題する一連の文書を発表した。
第1章・マルクス、エンゲルスとその生涯。 第2章・マルクス主義の哲学的・科学的世界観。第3章・マルクス主義哲学-唯物論、弁証法、史的唯物論。第4章・経済学。第5章・社会主義経済学と社会主義計画経済。ソビエト社会主義建設におけるレーニンとスターリンの偉大な勝利とその教訓が、理論と実践における統一された哲学的・科学的思想に基づいて詳細に展開されている。マルクス主義の基本思想、基本原理、理論的原則を明確に定式化したものであり、ここに正統派マルクス主義のすべてがある。
マルクス主義の哲学的原理、政治的原理、理論的原理を明確に定式化したものであり、ここに正統派マルクス主義のすべてがある。
特に、第5章「ソビエト社会主義の建設におけるレーニンとスターリンの偉大な勝利」では、「ソビエト社会主義は失敗し、計画経済は幻想であった 」というブルジョアジーの誤った宣伝に対して、決定的な反論を行っている。それは、理論と実践の両面における社会主義経済の優位性を歴史的に証明するものであり、人民に対する社会主義への信頼の表明である。われわれ)は、全ての皆さんがこの文書をよく学習されんことを心から期待する。 (中央委員会書記局)
《著者プロフィール》
大武礼一郎(おおたけ・れいいちろう)
1924年大分県生まれ。1948年から日本共産党大分県委員。九州地方委員会委員。中国地方委員会委員。関西地方委員会委員。中央委員会西日本局長。宣伝教育部長。1956年、ソ連共産党にフルシチョフが登場し、1958年には宮本顕治が日本共産党の実権を握った。こうして、国際的なマルクス主義運動、共産主義運動、社会主義運動は修正主義に支配され、すべての運動がブルジョアの影響を受けるようになった。この時点から、私たちはマルクス主義を擁護し、共産主義運動と社会主義運動の再生のために行動し始めた。マルクス・レーニン主義運動全国協議会議長、1980年日本共産党(行動派)再建、議長に就任。主な著作に『学習のすすめ』、マルクス主義の理論と実践の統一されたマルクス主義に関する百科事典としての『日本共産党(行動派)基本文献集・全5巻』などがある。
2011年7月15日初版第1刷発行
発行者
日本共産党(行動派)中央委員会